前
暗い夜に、真っ赤な傘を差した銀髪の男はフラッと私の前に立ち、
「傘ねェの?」
声を掛けてきた。雨の中で座り込んでいた私を気に掛けてくれたらしい。
「この雨だと待ってても微妙じゃね?なんなら送るけど。」
「…いえ、結構です。」
気遣いは不要。私はこの雨に困っていたわけじゃない。ここにいたのは―――
「家どこ?」
「…本当に結構ですから。」
「んなこと言っても、」
銀髪の男が私の方へ傘を寄せる。
「こんなずぶ濡れな女の子、無視できるわけねェでしょうが。」
「……、」
面倒見が良いのか、ヨコシマな考えの持ち主なのか。
「…あの、」
「ん?」
「肩が…濡れてますよ。」
何も考えずに傘を伸ばしたせいで、男の肩が濡れてしまっている。
「気にすんな。」
「でも…」
「そんなことより早く立てよ。」
「…私はいいですから。」
「……。」
「……、」
「……ああそう、わァった。」
その言葉にホッとした。ようやく諦めてくれた、と思ったけれど。
「じゃあパフェ奢れ。」
「…え?」
またよく分からないことを言い出す。
「お前は俺の善意と時間を無駄にしようとしてる。申し訳ないと思わねェか?」
「…ですから私のことは放っておいて結構だと、」
「俺の思いを無駄にした分、パフェ奢れよ。」
…何なの?この人。
「そんな警戒すんなって。」
銀髪の男はフッと笑い、
「何も取って食おうとしてるわけじゃねェんだ。ほら、行こうぜ。」
まるで野良猫をなだめるように話し掛けてきた。私の前に屈み、真っ赤な傘へ入れる。見計らったように雨が酷くなった。
「ほらな?」
男は得意げに笑う。
「傘があって良かったろ。」
「……ありがとうございます。」
「どういたしまして。」
今から思えば、この瞬間からもう私の心は溶かされ始めていたのかもしれない。

「で、家はどこよ。」
「……ありません。」
隣を歩く男がギョッとする。同じ傘の下だから、前を向いて歩いていても相手のことは目の端で見えた。
「なに、家出?」
「いえ。」
「じゃあマジで家がねェの?」
「はい。」
「…そうか。」
浅く溜め息を吐く。
「まァあんな場所で雨に打たれてんだ。そんなこともあらァな。」
「……。」
「……、…。」
『面倒な相手に声を掛けてしまった』
彼はおそらくそう思っただろう。だから断っていたのだ。私に傘は必要ない。困っていたわけじゃない。私は、あの場所でただ雨を見ていただけだから。なのにこの男は…
「……、」
「…。」
一体どこまで歩く気でいるのか。目的地のない私を、一体どこまで送る気で……まさか、警察?それは困る。
「お前さ、」
「っ…はい。」
「明日も家、ねェんだよな?」
「はい。」
「んー…、」
アゴに手をやり、横目で窺ってくる。一体感のない銀髪が、歩く振動でフワフワと揺れていた。改めて見ると、
「ならよォ、」
綺麗な銀髪だ。電柱の灯りで時折輝いてさえ見える。なんだか…眩しい。
「なら銀さんのところに来なさいな。」
「……、…え?」
なに?なんと言った?
思わず顔を向ける。彼は自分を指差してニッと笑った。
「銀さんって俺のこと。」
「…はぁ、」
「じゃあそれでいいよな。」
「…?」
「広くはねェけど、一人くらい増えても問題ねェから。」
…待って。この人、私を自分の家に住まわせる気?雨の中で座り込んでいた見ず知らずの私を?
「……、」
怖い。親切すぎて怪しい。
「ぷっ。わかりやすいな、お前。」
男は顔の前で手を左右に振った。
「大丈夫だって。俺ん家、大食いのガキと怪獣みたいな犬もいるし。」
大食いの子どもと…怪獣みたいな犬?
「だからお前一人くらい増えても大したことねェの。」
子どもまでいるのに私の面倒を見るの?…もしかして、相当なお金持ち?
「…結構です。」
危険だ。財力のある人間はどんな繋がりを持っているか分からない。もし幕府と繋がっていたら……、…一刻も早く離れないと。
「…私、ここまでで。」
「へ?」
「失礼します。」
軽く頭を下げ、男の真っ赤な傘から出た。しかし、
「コラコラ!」
―――グッ…
手首を掴まれる。
「!」
「なに勝手に出て行こうとしてんの。」
「…。」
この人…一般人じゃない。私の手首を握る、この手の感覚…かなりの手練だ。
「つーかどこ行く気だよ、家ねェのに。」
「……。」
「俺が納得できる行き先を言えるまで、逃さねェからな。」
「……。」
面倒くさいのに引っ掛かってしまったのは私の方だった。
「……どうしてそこまで…」
「今さらお前みたいな家なき子、あっさり見送れって方が無理あんだろ。風の噂で何かあったと聞いた日にゃ寝覚めも悪ィし。」
「噂には…なりません。どこの誰とも分からない私が…噂になるなど」
「はいはい、何を言ってももう遅ェぞ。着いたから。」
「え…」
「ここ、俺ん家。」
アゴを差す。二階建ての、決して新しいとは言えない建物があった。二階部分には何やら看板が掛けてある。
「万事屋…銀ちゃん?」
「そ。俺が銀ちゃん。万事屋やってる坂田銀時でーす。」
ブイサインをしながらニィッと笑う。
…なるほど、だから面倒見が良かったのか。
「じゃあ中に入るぞー。」
「…いえ、私は」
「わかったわかった、話は中でいくらでも聞いてやる。」
「っあの、」
「今はもう22時だから静かになー。」
「っ、」
手首を掴まれ、外階段を上った。鉄骨の階段が不規則な二つの足音をより響かせる。
「……、」
ここで抵抗すれば、逃げ出せるかもしれない。いくら男が手練でも逃げるくらいなら…
「……。」
…だけど…
「お前の名前、何つーの?」
「……。」
なぜか彼に…坂田銀時に付き従ってしまう。見ず知らずの男なのに、どうしてか。
「言えねェなら適当に付けるぞ。」
「…、」
私も相当、変わっているのかもしれないな。
「じゃあお前の名前はー……引き戸だ!」
玄関の引き戸を開けた後、坂田銀時が振り返った。
「どうだ、嫌だろ。」
「…嫌です。」
「なら何か名前言え。友達に呼ばれてたアダ名とか、花の名前とか漫画のキャラでも何でも――」
「紅涙。」
「え?」
「…紅涙です、私の名前。」
「…紅涙な、りょーかい。」
頷きながら玄関へ入り、坂田銀時は私に手を差し出した。
「じゃ、よろしく。」
これは…握手?…なぜ?
「……。」
「…なんだよ。ほら、握手しようぜ。」
「…。」
…必要ない。握手などしたら、まるでこれから世話になり続けるみたいじゃないか。そんな気はないのに。
「んだよ。冷てェヤツだな。」
頭をガシガシ掻き、坂田銀時が奥へと歩いて行く。
「あ、ちょっと俺電話するから。」
「…。」
私は立ち去る背中を見送り、玄関先で家の中を見回した。
一見したところ、これといった財力は感じない。少なくとも私の知るお金持ちではないようだ。…いや、そう見せないだけなのかも。
「ああ、…じゃあよろしくな。」
坂田銀時の声が聞こえる。続けて、
「ありゃ?そっかそっか、そうだったな。」
話し声がする。電話中かと思いきや、廊下に顔をだした。
「悪ィ、今日俺と二人っきりだわ。」
「……。」
「いや、神楽と定春を志村家で飯食わした日でよ。そのまま泊まるっつー流れが最近の通例になってたの忘れてた。」
「……。」
「ほっほんとに忘れてたからな!?わかっててお前を連れ込んだんじゃねーから!」
「……そうですか。」
「やめて!その微妙な間で圧力かけるのやめて!!」
賑やかな人だな…。……あ、そう言えば。
「肩、」
「ん?」
「肩、…早く拭かないと。」
私に傘を優先し続けたせいで、肩の濡れがひどい。
「ああ、コレな。大したことねェよ。」
「…すぐに拭いた方がいい。」
「大丈夫だって。こうしておけば、」
―――パンパンッ
濡れた箇所を手で払う。
「すぐ乾くし。」
「とてもそんな程度では……」
「それより紅涙の方が問題だろ。」
「…私は結構です。」
「結構っつーレベルじゃねーよ。…ああ、風呂。風呂使え。」
「結構です。」
「結構結構って…。せめてタオルか風呂くらい選べ。どっちだ?」
「……。」
「選ばねェなら強制的に風呂連れてくぞ。」
「……タオルで。」
「よし。」
坂田銀時はどこからかタオルを持ってきて、
「ほい。」
ポンと私の頭にタオルを置く。
「しっかり拭けよ。あと、そこに座ってろ。なんか飲み物持ってくるから。」
指された場所は、居間らしき部屋にある長椅子だ。坂田銀時は台所と思わしき場所へ歩いて行く。
「……、」
言われた長椅子に座ってみた。ジャンプが置かれていたり、傍に仕事用と思わしき机を置かれていたり、何かと生活感がある。
「糖分…。」
部屋に掛けられた字を読んだ。なぜあの文字を掲げたのだろう…。
「なに飲む~?」
離れたところから坂田銀時の声が聞こえた。
「…結構です。」
「あァん?何だってェ~?」
「何もいらないです。」
「じゃあ俺のおまかせな。」
「……。」
万事屋を営む人というのは、こうも人に親切なものなのだろうか。それとも歌舞伎町の民そのものが、人に親切な体質なのか。
でももし私が坂田銀時でなく、違う人と出逢っていたら…こうはならない気がする。坂田銀時が強引だから……
「おまたせー。」
―――カタンッ…
私の目の前に、コップ二つとイチゴ牛乳のパックを置いた。坂田銀時は向かいの長椅子に座る。
「銀さんオススメのイチゴ牛乳をお持ちしましたー。」
「……。」
「あァ?…なんだよ、イチゴ牛乳嫌いとか言うなよ。」
「…嫌いでは」
「だよな~?イチゴ牛乳が嫌いなヤツなんて絶対いねェと思うわ俺。イチゴ牛乳嫌いなヤツは人間じゃねェよ!」
極端なことを言いながら、コップにイチゴ牛乳を注ぐ。
「ほい、お前の分。」
「…ありがとうございます。」
コップを持つ。と同時に、坂田銀時は飲み終えた。
「っプハ~!うめェ~!やっぱイチゴ牛乳はウメェわ!な!」
「…はい。」
「飲んでから言えよ。」
「…すみません。」
「いやべつに責めてるわけじゃ…」
「……。」
「…、…だァァっ!もういい!早く飲め!俺も飲む!」
自分のコップにイチゴ牛乳を注ぐ。勢い良く飲みきると、コップを下ろした口の周りに淡いピンク色のヒゲが出来ていた。
「……ヒゲ、」
「あん?」
「ヒゲ…出来てます。」
「イケメンだろ。」
「……。」
「なんか言えよ!」
「すみません。」
「それが一番傷つく!」
本当に賑やかな人だな…。こんなに話す人、久しぶりに会った。なんかちょっと……楽しい。
「……、」
…『楽しい』?
「どうした?」
「……、…いえ。」
私の感情が小さく波打つ。
こんな感覚、もうずっと忘れていた。私には、…隠密の私には、ずっと必要のないものだったから。
『仕事だ、早雨』
私は、将軍直属の隠密だった。
痕跡を残さず任務を遂行し、一度たりとも失敗は許されない仕事。対象を再起不能にしたり、暗殺ばかりの日々だったけど、相手の性格も始末される理由も何も知らされない私達が心を病むことはなかった。
…そう思っていたのに。
ある日突然、私は全てを投げ出してしまった。
『紅涙!馬鹿なことはやめろ!』
『今戻れば我らの心に秘めておく!戻れ!』
『……戻らない。さようなら』
今や私はただの『逃亡者』。飼い主から逃げ出した排除対象。じきに幕府は私を消しにかかるだろう。江戸には真選組という組織もある。これまで手合わせする機会はなかったが、腕の立つ集団と聞いている。おそらく私の未来は…短い。
『逃げ出したところで生き延びられぬぞ』
…だとしても、私は逃げたい。逃げて、今まで感じたことのないものを感じて終わりたい。
街の音、空の色、雨の匂い。夜の静けさと、楽しげな人々の声音。なんということのない、この日常を感じてから…終わりたいのだ。
「あーやべ、寒くなってきた。」
坂田銀時が着物から腕を引き抜く。中に着ている黒い服が、肩の辺りから色濃く変わっていた。
「俺も結構濡れてたみてェだわ。」
……そうだと思っていました。
「ちょっと着替えねェと本気で風邪ひいちまうな…っと。」
黒い服から腕を引き抜く。が、肌に張り付いて脱げないらしい。薄い生地で脱ぎづらいのだろう。ああなると腰の辺りから裏返して脱ぐしか―――
「ちょっとちょっと。紅涙さん?」
「…なんですか。」
「何って、そんなにジロジロ見ないでもらえます?」
坂田銀時が自分の身体を抱きしめた。
「えっち。」
「……。」
「…なんか言えよ。」
「他で着替えてください。」
私はこの部屋しか知らない。見ないでほしいなら他で脱ぐか、私を……、…そうだ。
「出て行きます。」
「へ!?」
私が出て行けば済む。
「ちょっ、ちょい待ちィィ!」
慌てた様子で坂田銀時が立ち上がった。ドタドタと足音を立てて私の前に立つ。
「そういうつもりで言ったんじゃねーから!」
出て行かせまいと両手を広げた。
「……どうして、」
どうしてそこまで私を引き留めるんですか。
「あん?」
「……、…なんでもないです。」
「…はァ~。」
溜め息を吐かれる。坂田銀時は先程まで私が座っていた長椅子に腰を下ろした。
「お前、焦らすタイプだよな。」
「え…?」
「しょっちゅう言葉は途切れさせるし、意味深に黙り込むし、俺のことは見つめてくるし。」
「…見つめてません。」
「そうか?俺は何回か見つめられてると思ってたけど。」
―――グッ…
手首を掴まれ、下へと引っ張られた。同じ長椅子に隣合って座らされる。
「こんな風にジッと俺のこと見てたじゃねーか。」
「……。」
「……。」
「……。」
「……、…っ…負けた。」
握られていた手が放れる。
「なんで平気なんだ…?つーか紅涙、感情がねェよな。」
「…感情はあります。」
そのせいで投げ出してしまった。
「笑えんのか?」
「…笑えます。」
「じゃあ笑ってみろよ。」
「……そういうのは。」
首を振る。坂田銀時が小さく笑った。
「まァ笑えって言って笑えるヤツは、初めから笑ってるわ。…でも、」
おもむろに私の頬へ手を伸ばす。遠慮なくペタりと触られた感覚と、その手の冷たさに目を見開いた。
「俺はお前の笑顔に興味あるぞ。」
「……そうですか。」
「いつか見せてくれよな。」
「……。」
『いつか』
いつかとは、いつだろう。坂田銀時は、いつまで私といる気でいるのだろう。
「な?」
「…、…。」
『はい』
そう頷きたくなって、目を伏せた。自分で少し反省する。今の私は、心が…動きすぎている。
「あ、そうだ。これからパフェ食いに行こうぜ。」
また唐突な…。
「俺パフェ食いてェんだよ、甘味処 フシのパフェ!」
この人の口から『パフェ』と聞いたのは二度目だ。相当食べたいの?飲み物もイチゴ牛乳だし、かなりの甘党みたいだけど……ああ、だから『糖分』なんて字を掲げているのか。
「今日までの期間限定パフェがあんだけど、実物がかなりスゲェらしくてさ!知らね?」
「知りません。」
「じゃあ行こうぜ!」
目を輝かせて立ち上がる。そんな坂田銀時には悪いが、
「…行けません。」
私は行けない。
「なんで?まさかお前…っ、パフェ嫌いか!?」
「違います。でも……人の目が苦手で。」
私は追われる身。甘味処のような人が集まる場所へ出向くのは、とてつもないリスクを伴う。私にとっても、坂田銀時にとっても。
「人見知りってわけでもねェのに?どう苦手なんだよ。」
「…それは…、…、」
「……ん?」
「……、…すみません。」
「またジらすー。」
グダッと椅子の背もたれに倒れ込んだ。
「はァ…。わァったわァった。よく分かんねェけど、人の目がなけりゃいいんだな?」
「そう…ですね、まだ大丈夫かと。」
「よし、」
背もたれから身体を起こす。
「なら問題ねェぞ。そこの甘味処、24時までだから。」
「24時…、」
部屋にある時計を見た。もう23時だ。
「こんな時間から行く客なんて俺達くらいしかいねーよ。」
「でも……。」
「そこまで気にするなら、他の客がいた時点で諦めてやるから。諦めて明日にする!」
「……わかりました。」
「よしっ!じゃあ行こうぜ、お前の奢りで!」
「?」
なぜ?…ああ、こうして親切にしてもらった礼か。
「わかりました。」
「いいのかよ!?」
「いい…ですが。」
「マジ!?よっしゃァ!言ってみるもんだな!」
お金はある。それなりに握ってきた。誰も頼らず、数日は過ごせるくらいに。
「早く行くぞ紅涙!二、三個食っただけで店が閉まっちまう!」
「…一体いくつ食べる気なんですか。」
「ひーふーみー…まァ、たらふく?なんたって人の金だからな!」
「……。」
まさかとは思っていたが、
「オヤジー!期間限定のパフェと、こっからここまでのパフェを持ってきてくれ!急ぎで!」
坂田銀時は店に着くなり、本当に次から次へとパフェをたいらげていった。顔馴染みらしき甘味処の店主も苦笑している。
「銀さん、こんな時間から大食いして身体を壊さないかい?うちとしてはありがてェけど。」
「俺の身体は120%糖分で出来てるから心配ねェよ。それより紅涙、二杯目は何食う?」
「私は…これだけで充分です。」
「なんだよツレねーな。じゃあ俺一人で頑張るしかねェか。」
なにも頑張ってまで食べなくても…。
そのあと坂田銀時は、注文したパフェを残さず食べきった。会計を済ませたのは閉店五分前。もちろん私が支払う。
「ありがとうございましたー!」
のれんをくぐり、店を出た。直後、
「…ち、ちょっと紅涙さん。」
「はい。」
財布をしまおうとする私の後ろから、坂田銀時が声を掛けてくる。その顔が引きつっていた。
「お前…いくら持ってんの?」
「?」
「なんで払えちまうんだよって言ってんの!」
わけの分からないことを言いながら、私の手元を覗き込んできた。視線から逃れるように、財布を胸の辺りへしまう。
「くっ…さてはお前、金持ちか!?」
「…そんなことありません。手持ちは少しです。」
「どこが少しだよ!余裕で払えちまったじゃねーか!」
「…いけないことだったんですか?」
「ッ!?べっ…べつに?いけなくねェよ?いけなくねェけど、いっぱい食ったらテメェがあの店にツケるかと思って…あんなに食ったのに。」
…?
「いや幸せだったよ!?腹いっぱい食えて幸せだった!けども!!」
「……。」
わからない。
「あの、」
「なに!?」
「私にツケさせたかったんですか?」
「うっ…、」
「どうして?」
「……。」
「?」
「…もうこの話はやめにしよう。」
「え?」
「しばらくパフェの名前を聞いただけで戻しちまいそうだ。うぷっ、」
口元を手で覆う。
「今の今まで元気に話してたのに…。」
「っせーな。運動がてら、ゆっくり歩いて帰るぞ。」
「運動なら走った方が効果的です。」
「無理!詰め込み過ぎた夢が溢れちまうから無理!」
…パフェが…詰め込み過ぎた夢。
「ふふ、」
変なの。
「…なに笑ってんだよ。」
「え…?あ…いえ。」
ほんとだ、私…笑ってた。
「…なァ紅涙、」
「はい?」
「お前、絶対笑ってた方がいいって。」
「……、」
「普段からもっと笑えよ。な?」
「…そう言われても。」
ついさっきまで、笑い方も笑い時も忘れていた私だ。その辺を歩くような人達のようには…まだなれない。
「安心しろ、これから毎日俺が笑わせてやる。」
「……『毎日』?」
「ああ、毎日だ。」
坂田銀時が、ニイッと笑う。
「笑ってるだけでも良い運ってのは回ってくるもんだ。」
「……、」
「信じろ。いつもバカ勝ちする常連のバァちゃんが言ってたから。」
「バカ勝ち…?」
「パチンコ。でもまァ俺がバカ勝ちするのなんて数年に一度くらいしかねェんだけどな!」
…坂田銀時は、
「……銀さん、」
「ぅおっ、おう。なんだ?」
「……ありがとう。」
綿菓子のような人だと思う。ふわふわ軽くて形がないのに、触れた場所に甘い余韻を残す。私の…胸の中みたいに。
「…急に礼なんて言うなよ。死亡フラグでも立ったか?」
「そうですね。」
「……バカ、んなこと言うな。」
「…自分で言い出したくせに。」
「…だな。……、…あのよ、紅涙。」
頭を掻き、私を見る。
「俺はべつにいいんだからな。」
「?」
「お前にどんな過去があっても。」
「!…、」
それは……、
「それはどういう意味ですか。」
まるで私を知っているかのよう。街に住む人間が私を知ることなんてありえないのに。
「…お前がどれだけ俺ん家に居座ってても、どれだけ飯食ってもいいって意味。」
「……。」
「…だからよ、紅涙さえ良ければ…」
その時だった。
―――ウゥ~
パトカーのサイレンが聞こえた。まだ音は遠いが、確実にこちらへ近付いてきている。
「俺はいくらでも面倒―――」
「銀さん。」
坂田銀時の手を取った。
「っえ、なに!?いきなり何!?」
「少しこちらに。」
店と店の狭間へ入り込む。出来ればこの場から逃げ出したいが、土地勘がないせいで下手に動けない。
「……。」
「おいおい、どうしたんだよ紅涙。」
「静かに。」
サイレンが止まった。
「こっちだよ真選組さん!」
……来る。
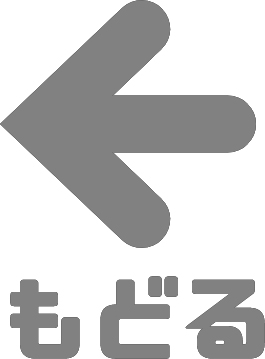 |
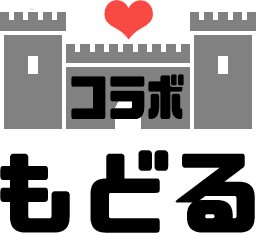 |
 |
