後
女性の声を聞きながら、路地裏で息を呑む。
もし…もしあの女性がここへ呼びつけたのなら……やるしかない。
「…銀さん、」
「ん?」
「その木刀、貸してください。」
「はァァ?なんで。」
「…何かの時のために。」
路地の方を見たまま、後ろへ手を出した。けれど、手に触れたのは柔らかい感触。見れば、ギュッと手を握られている。
「…銀さん?」
「俺がいる。」
「…え?」
「何かの時には俺がいる。」
「……、」
「あー面倒くせェ。」
「!」
「大丈夫だ、紅涙。」
坂田銀時が私の手を強く握った。真後ろの通路を二つの足音が通る。
「野郎はどこでさァ。」
「こんな場所にいるってことは、あのラーメン屋に行った帰りですかね。…じゃあ怪我は治ったのか。」
「怪我ァ?誰が。」
「桂です。なんでも街中でぶっ倒れたらしくて、知り合いの家で療養してたとか。」
「…ほほう?そりゃあ興味深い話じゃねーかィ山崎。そんな情報を握っていたにも関わらず、上に報告しなかったと。」
「え!?ちっ違いますよ!最近知ったんです!べつに知ってて隠してたわけじゃ…」
「そっくりそのまま土方さんに報告してみなせェ。」
「え、ちょっ、沖田隊長!誤解!誤解ですからァァ~!」
徐々に話し声と足音が遠ざかっていく。
どうやら目的は攘夷志士の桂だったらしい。…よかった。
「ったく、アイツらは相変わらずうるせェな。」
坂田銀時が私の手を握ったまま、路地裏から顔を出す。辺りを見渡し、軽く手を引いた。
「今のうちに帰るぞ。」
「……銀さん、」
「ん?」
「私のこと…何を知ってるんですか?」
「『何を』?」
顔色は変わらない。
「何ってなんだよ。」
「……私の、…過去とか。」
「知らねェけど。」
「…嘘。」
「なんでそう思う?」
「…何も聞かないから。」
なぜ隠れるのか、なぜ真選組を恐れているのか。今の私の行動を少しも不思議がらないのはおかしい。
「お前は『知ってる』って言ってほしいのか?」
「…真面目に答えてください。」
「俺はいつだって真面目だよ。」
「っ銀さん!」
手を振りほどく。
「大切なことなんです!」
「…声。」
「え…?」
「声には気をつけろ。せっかくやり過ごせたのに、アイツら戻ってきちまうぞ。」
「っ…。」
「わかったなら、ほら。」
再び手を差し出す。
「さっさと帰るぞ。」
私はその手をじっと見て、首を横に振った。
「……帰りません。」
「ガキみてェなこと言うなって。」
「なら答えてください。」
「だから答えてんだろ?俺は何も知らねェ。この答えに不満なら、納得するまで俺を見張ってろ。」
…この人は、本当に私を受け入れようとしているのか。
「手、紅涙。」
何も聞かず、何も知らないままに…私を。
「……。」
そんなのダメだ。成り立たない。いずれ私が駄目にする。私のせいで、坂田銀時が駄目になる。 …だから、
「…銀さん、」
「んー?」
去らなければ。
「……ありがとう。」
そんなことを考えながら、

差し出されていた手を握った。
「…だから礼を言うのはやめろって。」
坂田銀時が小さく笑う。
「お前の礼は妙に重いんだから。笑って言えるようになるまで礼は禁止。な?」
「……はい。」
帰り道、坂田銀時は私の手を放さなかった。鼻歌を歌い、足取り軽く歩く。私の頭は、いつどうやってこの人の前から去るかばかり考えていた。タイミングさえあれば、すぐにでも行動したい。……すぐにでも。
「あ~腹いっぱい!」
万事屋に帰り着いた後、坂田銀時は居間の長椅子に寝転がった。
「風呂入るの面倒くせェなー。」
「…入った方がいいです。雨に濡れたんですし。」
「紅涙もな。」
「私は……、…。」
必要ない。どうせまた濡れる。明日も雨…いや、今は深夜二時。もう今日か。
「じゃあちょっと寝てから風呂入るかなァー。」
うんと伸びをして、
「紅涙は向こうの部屋使えよ。」
「…わかりました。」
「布団に入るのは風呂入ってからな!」
「はい。」
「よし。じゃ、おやすみー。」
長椅子の上で寝返りを打ち、私に背を向けた。部屋に響くのは時計の針の音だけ。それを数秒聞いていたら、寝息が聞こえてきた。
「……早い。」
相当疲れていたらしい。もしくは急激に糖分を摂取したせいかもしれない。…どちらにせよ、去るなら今だ。
「……。」
坂田銀時の背中を見る。言いえぬ気持ちが喉まで出てきた。
…不思議な人。長居は危険な人。この人の傍にいると、心まで弱くなる。…頼りたくなる。
「…ありがとう。」
お世話になりました。
私は足音に気をつけ、慎重に廊下へ出た。廊下は歩いた分だけ軋む。こればかりは避けようがなく、息を殺して歩くしかなかった。
玄関先に入り込む外の光は、薄い青と淡く白い光が混じっている。
「…銀さんみたい。」
たった数時間でも、私には与えてもらった物があまりに多く。
「……、」
名残がないかと心に問うのはやめた。立ち去ることに代わりないのだから。…行こう。
その時、
「…?」
ふと屋根を叩く優しい音が聞こえてきた。この音は、
「……雨。」
雨音だ。私の逃亡道中は、つくづく雨に恵まれているらしい。音に気を遣いながら玄関の引き戸を開けた。
―――ガラガラ…
「どこに行くつもりだ?」
「っ!?」
背後から掛けられた声に心臓が冷える。ゆっくり振り返れば、眠そうな顔をした坂田銀時と目が合った。
「銀、さん…。」
「どこに行くつもりなんだよ。」
この人、気配もなくどうやって…?
「俺に言えねェとこへでも行く気ですか、
紅涙さんよォ。」
「……。」
「ちゃんと帰って来るなら行ってこい。けど、帰ってこねェなら話は別。」
「……、」
視線を下げる。今の私には、その場しのぎの嘘すら出ない。
「…、…なァ紅涙。」
彼の声が、私を責めているように聞こえる。
「出て行くなら、別れのセリフくらい言って行けよ。一緒にパフェ食った仲じゃねーか。」
…言えるわけがない。私自身のことさえ言えないのに、さよならなんて…言えるはずがない。
「……ま、当然と言っちゃ当然だろうけどな。」
「…?」
首を傾げる私に、坂田銀時は大きなアクビをした。そして、
「お前、幕府の忍なんだろ?」
「!!」
まるで明日の天気でも聞くかのように軽く問う。
それとは逆に、私は言葉を失くした。何かに勘づいているとは思っていたけれど、まさか雇い先まで知っているとは。
「逃走中の紅涙。…早雨 紅涙。」
「嘘…ついてたんですか。」
『俺は何も知らねェ』
「そこまで嘘じゃねェよ。知らねェことの方が多いし。」
「……あなたはどこでその情報を?」
「手配書。」
「えっ…」
手配書って……私の?
「どこで…手配書を……?」
「歌舞伎町の電柱。」
「!?」
「歌舞伎町の街中いーっぱいに貼ってあったぞ、お前の手配書。」
そんな…。
私は手配書なんて一枚も目にしていない。気付かなかっただけ?…いや、そんなまさか。…じゃあ何?この人、手配書を見た上で私に声を掛けてきたってこと?
「なんのために…」
「そりゃお前を捕まえるためだろ。」
「あ…いえ、どうして銀さんは私を…ここへ連れてきたのかと。」
「ああ…、……なんでだろうな。」
坂田銀時はやはり幕府の内通者ではないだろうか。私の気が緩んだところで、幕府に連絡するつもりだったのでは…?
「俺さ、今日…いやもう昨日か。パチンコに負けちまってよ。」
「え?」
「そりゃもう久しぶりの大惨敗。なのに店出たら雨降ってて。昼間は晴天だったから傘なんて持ってるわけねェじゃん?何ですかこの仕打ち。俺なんか悪いことしましたか神様って感じで。」
「はぁ…」
何の話だろう…。…でも、
「あの時…傘、持ってましたよね。」
私は玄関の傘立てに目をやった。赤い傘にはまだ雨粒が付いている。
「そいつは多串君からの預かり物。」
「オオグシ君…?」
「あーそれはいい。気にすんな。」
ひらひらと左右に手を振る。
「俺が雨に濡れてる時にタイミング良く通りがかったモブ男だ。なんでもゴリラがその赤い傘をストーカーしてパクッてたらしくな。今から返しに行くって言うから、じゃあ俺が返してやるよって受けてやったわけ。」
ゴリラが…ストーカー……。
「で寒くて鼻水出てきたから、ティッシュねェか?って聞いたら……」
『ティッシュはねェが、紙ならあるぞ』
『マジか!くれ!』
「その紙、何だったと思う?」
「…まさか、」
「そ。お前の手配書だ。」
「!」
「硬くて拭けねェわ!って投げつけようとしたら、あの野郎、もういなくなってやがって。仕方なく手配書見たら、手配されてるのが女の忍ときたもんだ。」
「…。」
「なかなか珍しいじゃん?コイツ、どんなスゲェことしたんだろ~なんて妄想しながら、傘差したわけよ。そしたらその手配書、もう街中の電信柱に貼り倒してやんの。」
…私がこの街に来た時には、既に幕府は動いていたということか。
「アイツらもバカだよな。歌舞伎町だけでそこまで貼り倒してどうするよ。そいつがこの街にいるとも限らねェのに。」
「……分かってたのかもしれません、歌舞伎町にいることが。」
「そりゃねーわ。もし分かってたらアイツらは早々に街に包囲網を敷いてる。俺がお前を見つけること自体出来なかったはずだ。」
「…、」
そう…なのだろうか。
「お前を見つけた時は正直驚いたよ。何の引きだコレ、こんな運あるならパチンコ勝たせろよ!ってな。…でも、」
坂田銀時は、
「紅涙の目を見たら、まるで大罪人のように書かれた手配書の内容に腹が立った。こいつは純粋に逃げただけだ、自分のために飛び出しただけじゃねーかって。だったら…」
私に小さく笑いかける。
「誰かが手ェ貸してやらねェと、って思ってよ。」
「……。」
私は無意識に胸の辺りを握り締めていた。意思を保つために、坂田銀時の優しさに心を揺らされないように。
「…質問、してもいいですか。」
「何だ?」
「歌舞伎町の手配書を…私は一枚も見ていません。今も貼ってありますか?」
「あー悪ィ。もしかして記念に見たかった感じ?俺、全部剥がしちゃった。」
「えっ…?」
「まァ正確には『剥がさせた』だけど。」
剥がさせた…?
「誰に…?」
「古いツレ、っつーかバカな男っつーか。まァ気にすんな。手配書を貼られ慣れた野郎だから、もうこの辺り一帯でお前の手配書は一枚たりとも残ってねェよ。」
「…どうしてそんなことを?」
「そりゃアレだ…、……。」
「?」
坂田銀時はガシガシと頭を掻いた。
「その…なんだ?紅涙の居場所を…作ってやろうと思って。」
「居場所…?」
「手配書なんてもんを目にしたら、この街から逃げたくなるだろ?だから…全部剥がしちまって、万事屋に住ませる計画だった。もしここに乗り込んでくる輩がいたら、俺が相手すればいいだけの話だし。」
少し恥ずかしそうに話す。その姿に、私の胸は潰れてしまいそうなくらい痛くなった。
「…俺は、お前の過去なんて気にしねェし、直接関係がある立場でもねェ。同居人の神楽や定春も、お前を慕うのは目に見えてる。」
「銀さん…、」
「だからここで…お前も一緒に楽しく過ごせたらと思ったんだ。」
この人は、一生懸命に私へ手を伸ばしてくれている。
「…、」
ここにいたい。この人の傍にいたい。ずっとこの優しさに触れて、生きていきたい。…けど、
「っ…。」
私は唇を噛んで、首を左右に振った。
私がここにいると、坂田銀時の日常は日常でなくなる。どう言ってくれても、私は重荷でしかないのだから。たとえ坂田銀時が心から平気だと思っていても、私自身が自分を重荷だと思っている以上……どうしようもない。
「…っ、ごめん、なさいっ、」
喉が痛い。鼻の奥も痛くなって、視界がにじんだ。私…泣いてるんだ。
「…だよな。」
坂田銀時は自嘲するように笑い、溜め息を吐いた。
「わかってんだ。この街じゃあまりに幕府が近すぎる。いくらなんでも、お前の気も休まらねェだろって。でも…予想より早かった。」
「…予想?」
「お前が出て行くの。もう少し様子見てくれんのかなーって、勝手に思ってた。」
はは、と乾いた笑い声が響く。
「…やっぱこうなっちまったらよ、」
「…はい、」
「もう俺がどれだけ引き止めても…出て行くよな。」
「……、…はい。」
「…じゃあよ、言うだけ言っていいか?」
「?…何を…ですか。」
「聞いてくれるだけでいいから。」
坂田銀時が私と真っ直ぐに向き合う。こうして真剣な眼を見たのは、思えばこれが初めてだ。
もっと…もっとちゃんと接しておけばよかった。私も分かっていたはずだ。ここへ来た時から、いずれすぐ出て行くことになると。ならばもっと…
「紅涙、」
坂田銀時を、
「お前を支えたい。…俺じゃダメか?」
「っ…、」
見ておけばよかった。
「銀、さん…っ、」
苦しい。坂田銀時を想って、坂田銀時が愛しくて。
「っ、」
あなたで良かった。思い出したこの気持ちが、あなたで良かった。
「…聞いてくれてサンキュな、紅涙。」
ポンポンと頭を撫でられる。それを引き金に、まるで走馬灯のように坂田銀時との時間が甦った。ほんの僅かな刻の中でも、思い返せることは山のようにある。それが今は、
「…っ。」
苦しくて…つらい。
「…泣くなよ、紅涙。」
柔らかな感触に包まれて気付いた。坂田銀時の腕の中はこんなにも温かくて、…落ち着くのか。
「お前が泣いたら…、…俺まで泣いちまうだろ?だから……泣くな。」
おそらく彼は知っている。抜け忍が生きられるほど、この世は甘くない。つまりここを出た私が、再びこの街に帰る可能性は…限りなくゼロに近いことを。
「銀さんっ…!」
私が泣く真の意味を、坂田銀時は知っていた。別れを惜しむその重さを、…さよならの意味を。

「泣くなって…。」
だから彼は、
「頼むから…、泣かないでくれ…。」
そう言ったんだと思う。
「…俺は目に見えねェものなんて信じねーけど、お前と逢ったのは偶然じゃねェと思ってる。」
そうだといい。
…でも、それならそれで神様は残酷だ。私だけを苦しめず、この人までもを巻き込んで苦しめてしまったのだから。
「…鍵は玄関の脇に隠してある。戻ってきたら使えよ。」
…そうか、これは罰なのだ。私が幕府を裏切り、逃げ出した罰。叶わない想いだからこそ、出逢ったのかもしれない。
…それなら、神様。もし、…もし私が生きながらえることが出来た暁には、どうか自由にさせてください。自分の想いを抱き、自分の足でここへ戻ってきたいから。
「傘、持っていけ。派手だが、濡れて歩くより目立たねェはずだ。」
「でもその赤い傘は返す物じゃ…」
「やるわけじゃねェぞ。ちゃんと返しに来い。」
「!」
「持ち主にも、いつか返すって言っとく。だから今は借りて行け。」
「……はい。お借りします。」
この傘は、証だ。私達が今日ここにいた証。そして、この証はいずれここへ戻ってくる鍵となる。
「…お前のこと、待ってるからな。」
いつかまた、あなたに出逢える日まで。
「早く…帰って来いよ。」
今は未来のために身を潜める。時間が私を許す、その日まで。
雨の音。雨の匂い。
暗い夜に、私の真っ赤な傘が映える。
「傘、ないんですか?」
パチンコ屋の軒先でしゃがみ込む男性に声を掛けた。うなだれる銀髪は、まるで気分を表しているかのよう。
「この雨だと待ってても微妙じゃないですか?なんなら送りますけど。」
「!」
私の言葉にピクりと身体を動かす。けれども未だうつむいたまま、男性は首を左右に振った。
「…お構いなく。」
短く拒む。いつかの私のように。
「そう警戒しないでくださいよ。」
「……。」
「何も取って食おうとしてるわけじゃありませんから。…ふふ、ほら。行きましょう。」
傘を差し出した。途端に雨が酷くなる。
「ね?傘があって良かったでしょ。」
「……。」
「……顔、上げてくださいよ。銀さん。」
「……、」
癖のある銀髪に微笑めば、ようやく顔を上げた。その表情は、思っていたよりも苦い。

「…遅ェぞ。」
そういうことか。
「すみません。ようやく政権内部が変わり、当時私が属していた組織も潰れました。」
立ち上がった彼に、腕を伸ばして傘を差す。
「…追っ手はねェのか?」
「はい、もういません。」
「……そうか。」
「…あ、肩。濡れちゃいますね。」
もう少し腕を伸ばした。
「…あれから、」
「はい?」
「…あれから、何年経ったと思う?」
銀さんは私を睨むように見た。先程から全く笑っていない。私は随分と笑えるようになったのに。
「三年…、でしょうか。」
「ああ…三年だ。三年もだ。」
「銀さん…。」
逃げている間、私の時間は短かった。身を潜めること、逃げること、生きることに必死で。毎日が終わる度にホッと胸を撫で下ろして過ごしてきた。だけど、
「遅ェよ…、お前。」
彼はどうだろう。
私と違って、そう大差ない時の中での生活。もしかしたら何倍も長く感じていたかもしれない。
「…もう戻って来ねェのかと思った。」
銀さんが私の手から傘を取る。
「俺のこと…忘れたのかと思ってた。」
そんなことない。そんなのありえない。
「俺だけが…、お前を覚えてるのかと思ってた。」
銀さんはそう言って、ギュッと眉を寄せた。一度大きく息を吐き、ようやく弱く笑う。
「…おかえり、紅涙。」
ああ…、
「お前を、待ってたよ。」
帰ってきた。ここは、私の家だ。私の…居場所なんだ。
「…っ、銀さん!」
抱き合えば、その感触に鳥肌が立つ。ずっと覚えていたつもりだったのに、今確かに思い出した。
「…雨が止まねェうちに帰るぞ。」
銀さんの顔は見えない。けれど、喜んでくれているのは分かる。あの日の夜のように掴まれた手は、あの日よりも強く、もう逃がさないと言われているみたいだった。
「銀さん、」
「ん?」
「待っててくれて、ありがとう。」
「……、」
微笑む私の顔を見た後、銀さんはフッと小さく笑った。
2012.8.21up
illust…くろだうらら様
novel…にいどめせつな
2020.6.30 novel加筆修正
 |
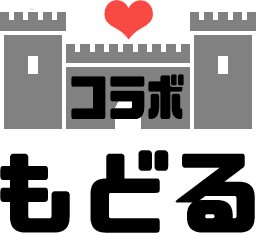 |
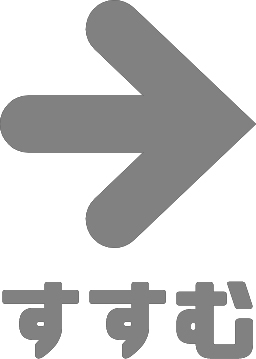 |
