勘違いした日+恋に堕ちた日
「「ギャァァァァッ!!!」」
屯所に響き渡る怒声と悲鳴。
「…うるさ。」
吐いた言葉と一緒に、ブンッと竹刀を振り下ろした。あれは私の機嫌を損ねる元だ。稽古場で練習していても、気が散って仕方ない。
「コルァァァァ!!」
「「ギェェェェェッ!!!」」
どこにいても聞こえてくる。きっと屯所の外まで漏れているに違いない。
「……恥ずかし。」
『毎回あれだけ怒らせてる方が悪い』なんて言われそうだけど、あのスイッチは些細なことでも入ると知ってほしい。特に本人が書類に忙殺されている時。あと、面倒なトラブルに巻き込まれている時。
もちろん私がスイッチを押す…いや、踏むことも例外ではない。
なんたって私は土方さんと馬が合わないことで有名な一人。一方的にそう思ってるんじゃなくて、土方さんもそう思っている間柄だ。
「…土方さん、」
向かいの席を見る。早朝のせいか、日中の三倍ほど深い皺を眉間に刻んでいる。
「…あァ?」
長机の上を見渡しながら、気怠そうに返事した。
「そこにありますよ。」
「何が。」
「土方さんの探してる物。」
顔をこちらに向ける。私が指し示す方を目で辿り、舌打ちした。
「…ったく誰だよ。俺のマヨネーズ使ったヤツは。」
先にお礼言えよ…なんて思わない。
むしろここで怒鳴らなかったことに驚いていた。だってマヨネーズは土方さんが愛してやまない物。いつもなら激高スイッチが入ってもおかしくない展開だったはず。…変なの。
「土方さん、そのマヨネーズは皆のものです。どこに置いていても文句は――」
「うるせェ。」
「…。」
私をギロッと睨み、他人のことなどお構い無しにマヨネーズを絞り出した。真剣に使う様は、とても副長の名に相応しくない。
「…土方さん。」
「っせーな、なんだよ!」
「どれだけ使う気ですか。もう二本目ですよ?」
「一本目がちょっとしかなかったんだよ!押したらブシュブシュ言って全然使えなかったんだよ!!」
必死だ。そして嘘だ。
私は知っている。一本目のマヨネーズ、半分くらいありましたよね。
「はぁ…。」
どうしようもない、このマヨ副長。
プライドの高さに加え、三秒に一度はキレるキレ症を患っている上に嘘まで下手ときた。
「いつまでもこんな副長でいいのかな…。」
時と場合によって、嘘をつくことも必要だ。どちらかというと、うちの一番隊隊長である沖田君の方が向いてると思う。
「…紅涙、今なんつった?」
「こんな副長でいいのかな、と言いました。」
「んだとコラァァァ!!」
あ、キレた。
「そりゃどういう意味だ!」
「そのままです。…土方さんって悩み事とかあります?」
「あァん!?」
「ちょっと気になりまして。でもあまりなさそうですよね。」
「なっ…、」
「キレることで発散できてそうだし。いいなぁ。」
「テメェ…ッ、俺に喧嘩売ってんのか!?」
バンッと机に箸を叩きつけた。
「上等だコラァァッ!!表出ろッ!!」
「…。」
やっぱりおかしい。ここまでけしかけないと怒らないなんて。…なんでだろう。思えば三週間くらい前から元気ないんだよね。
「おいおいィィ!何してくれてんだよ、早雨~!」
食堂にいた原田さんが頭を抱えながらやって来た。
「お前、仮にも同じ副長だろ!?なんで朝から着火しちゃうかなァ!」
「…一番隊の副長と土方さんを一緒にしたら怒られると思いますよ?」
「んな細かいことはどうでも――」
「早雨~っ!表出やがれェェ!!」
「おっ落ち着きましょう副長!」
「うるせェ!テメェらには関係ねーだろうが!」
「おい誰か高級マヨネーズ持ってこい!!」
なんか…大変なことになってきたな。
「早雨、頼むから飯食う時くらいゆっくり食わせてくれ…。な?」
「…そうですね。以後気をつけます。」
確かに、わざわざご飯時にすることじゃなかったかな、……反省。
周りの隊士達が連携して動き出す中、チラッと土方さんを窺う。土方さんは今もなお、フンスフンスと鼻息荒くして私を睨みつけていた。そこへ、
「持ってきたぞー!!」
隊士の一人がマヨネーズを掲げて走って来る。
「ほら副長~、落ち着いてくださ~い、高級マヨネーズが来たっすよ~!」
「っるせェッ!邪魔すんな!!」
「「!」」
「も、もうダメだ…。」
「高級マヨネーズが効かないなら、俺達に出来ることはない…。」
「…早雨、皆のためにちゃんとなだめろよ。」
なだめろって言われても……。
「わかりました。…土方さん、表に出ましょう。」
「「「違ァァァうッ!!」」」
原田さんを含んだ数人の隊士が私を抑えつけに来た。
「ちょっなんですか!」
「誰が決闘しろっつった!?」
「俺たちゃ副長をなだめろって言ってんの!」
「わかってますよ!だから土方さんの望み通りにしようと――」
「「「そうじゃねェだろ!!」」」
なによ、みんなして…
「もっと謙虚な姿勢で対話しろ!」
謙虚な……対話?
「わかったな!?」
「…わかりました。」
「よし、行け!」
原田さんが離れる。土方さんを見ると、土方さんも別の隊士に気をそらされていた。…まるでボクサーとセコンドのようだ。
「…土方さん、」
「……なんだ。」
「……本当は悩み事があるんですか?」
「あァ!?」
「私で良ければ聞きますよ。」
「おまっ、…、…。」
「ア、アイツ…。」
「ダメだ、俺達の言葉の意味を履き違えてやがる…。」
「なかなか解決できない悩みなんですか?」
「……、」
「どうりで最近、土方さんの元気が……、…。」
って、こんな気軽に悩み事を聞き出しても大丈夫なのかな。だって土方さんの悩みでしょ?到底、私に解決できるわけないだろうし…
「…すみません、やっぱりなかったことにしてください。」
「「「早雨~ッ!?」」」
「っな…何をだよ。」
「土方さんの悩み事を聞いたところで、私には解決できないと気付きました。」
「はぁァァ!?」
いつもより静かでいてくれるなら過ごしやすいじゃないか。稽古に集中できるし、良い事ずくめ。なら、わざわざ解決する必要もない…でしょ?
「~ッ、ああそうかよ!立て紅涙!やっぱ表に出ろ!」
「わかりました。でも朝ご飯を食べ終えてからにしましょう。じゃないと、そろそろ女中さんが――」
「副長さん!朝っぱらから何やってんだい!」
「!?」
「…怒られますよ。」
食堂の女中さんは強い。ありがたいことに、階級関係なく叱ってくれるタイプ。…だから、
「ご飯くらい静かに食べなっ!消化に悪いんだよ!?」
「…す、すんません。」
これには土方さんも素直に従う。大人しく座り、マヨネーズまみれな定食を食べ始めた。隊士達もホッとしたのか、各自席に着く。
「…。」
「…、」
とは言っても、食後にリスタートだろうな。
…なんて思っていたのに、土方さんは朝のテンションを引きづったのか、改めて呼び出すことはなかった。食堂を出た足で自室へ向かうと、そのまま部屋にこもる。
「…やっぱりいつもより元気ない気がする。」
そんな日の午後。
特に出動要請もなかったので、私は隊士と廊下に座り、世間話をしていた。
「俺さ~、甘味屋でバイトしてる子が気になってんだよねー。」
「へー、ああいう子がタイプなんだ。」
「もうモロタイプよ!」
暖かい日差しが入るこの場所は、程よく風が抜けて心地いい。よく昼寝場所としても使われている。…主に、
「なんでィ、紅涙。見廻りは?」
右手にアイマスクを握る、この人に。
「失礼だね沖田君、もちろん済ませたに決まってるじゃない。さっき帰って来たとこだよ。」
「そーかい、そりゃお疲れさん。っと。」
私の隣へ腰を下ろし、うんと背を伸ばした。
彼は一番隊の隊長。つまりは私の直属の上司。だけどプライベートな話も出来る、良き友人の一人。
「紅涙が帰ってきたっつーことは、今日もストーキングが完了してきたってわけかィ。」
「ほんと失礼だよね沖田君は。私、女だから。ストーキングじゃなくストークィーンだから。」
「はい、つまんなーい。己を恥じながら毒で死ね。」
「いっそひと思いに殺して!」
「…あ、あの、そんじゃあ俺行くわ。」
「あ、うん、お疲れ~。」
「お…沖田隊長、お疲れ様です。」
「お疲れー。」
先ほどまで話していた隊士が腰を上げ、いそいそと去って行った。
「…なんか邪魔しちまったようで。」
「そんなことないよ。」
聞いたところによると、隊士の大部分は沖田君のことを怖がっているらしい。特に役職のない隊士は、あまり深く関わらないようにしているのだとか。
「あ~…今日も良い昼寝日和でさァ。」
当の本人はそんなことなど全く気にしていないけど。
「んで、紅涙。さっきの見廻りは今日何回目の巡回だ?」
「んー…五回目。」
「昼の真っ只中で既に五回目たァ、見廻る回数が多くて仕方ねェや。」
「良いことでしょ~?街を愛してる証拠♡」
「よく言うぜ。」
鼻で笑う。
「どうせ何もしてねェんだろィ?一言くらい話しかけてくりゃいいのに。」
…この意味深な言い回しは、ストークィーンに関係している。私がわざわざ面倒くさい巡回に何度も出るわけ、それは一重にあの姿を見るため。
「さっきの見廻りでの遭遇は?」
「……なし。」
運命の出逢いは一ヶ月前にさかのぼる。
「じゃあ今日五回分の遭遇確率は?」
「…………ゼロ。」
あの人がいなかったら、私は今ここに存在していない。
「会ってねェのにそれかよ。…紅涙、『キュン死に』って言葉を知ってるか?」
「もちろん。」
「じゃあ紅涙もしてくんねェかな、キュン死に。」
「それってマジで死んでない!?」
…あれは一ヵ月前。
天人による大規模な密輸組織との戦闘中、私は目の前に振り下ろされた刀に気を取られ、
「ッあ!」
建物から足を踏み外した。
完全なミス。それでいて最大のミス。副長にあるまじき恥。ここは三階。おそらく落ちればきっと……
「くっ…!」
隊士生命の終わりを覚悟し、私は衝撃に目をつむった。その時、
「危ねっ!!」
―――ドンッ
「!?」
身体が何かに包まれる。
「大丈夫か?」
固く閉じていた目を開いた。
視界に映るその人は、まるで太陽を味方につけたかのように神々しく、眩しい人。
「あ……」
「お前、真選組?」
「はい…、……。」
思えばあれが人生初のお姫様抱っこだった。
「あの……お、お名前は?」
「…、…可愛いのに危ねェ仕事してんだな。」
「っ、かっ、かわっ…」
かわいいだってェ~!?言われたことないよ!真選組の人達から一度も言われたことない!!
「あ…あの…、あなたのお名前は?」
「あとで面倒だから俺のことは忘れろ。」
そう言って私を下ろし、
「あんま無茶すんなよ。」
軽く右手を上げて去って行った。
「……、」
男らしさと爽やかさ。そしてあとを残さない、いさぎよさ。
「……好き。」
私は呆気なく恋に落ちた。
摘発を終えて屯所へ戻った後、すぐに沖田君へ報告する。
「銀髪の男の人だったんだけど、名前が分かんなくて…!」
「ああ…ここらで銀髪なら旦那しかいねェな。」
「旦那!?」
「街を歩いてりゃすぐに見つかりまさァ。」
「じゃあ歩こう!一緒に!」
「はァ?なんで俺まで…」
と言いつつ腰を上げてくれた沖田君と共に街へ出た。市中見廻りを名目に歩いていると、甘味屋にいた彼と再会。
「旦那ァ、さっきうちのが世話になったみてーで。」
「っあ、あのっ、先程はありがとうございました!!」
「おお。なに、沖田の部下だったの?」
「出来の悪い部下ですぜ。」
「ちょっと!」
「じゃあパフェ奢ってくれ。」
「…え?」
「パフェ。俺に感謝してんだろ?なら奢れ。好きなんだよ。」
『好きなんだよ』
『好きなん……』
『好きだ』
私のことが!?
「紅涙、奢ってやりなせェ。」
「もちろんです!」
激しく頷いた。
「奢りますよ、いくらでも!何杯でも!」
「お~!?なんだよ、すげェいい部下じゃん。名前は?」
「はい!真選組一番隊副長、紅涙と申し――」
「へー。じゃあ俺はイチゴパフェお願いな。」
「…えっ、」
「そんじゃ俺はチョコパフェで頼みまさァ。」
「え、……あれ?」
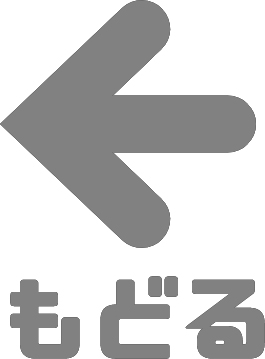 |
 |
 |
