「…すまない、紅涙殿。」
長くて艶のある黒髪が、風を受けて優しく揺れる。
「やはり俺は…長く居すぎたようだ。」
曖昧に欠けた月が低い雲を照らしていた。
「これ以上は害しか生まれぬ。紅涙殿にとっても、…俺にとっても。」
背を向け残酷に告げるその人は、まるで額縁に入った絵のようで。
「今ならまだ間に合う。まだ何も…生まれてはいないのだから。」
果てしなく、遠い人だった。

「トシ兄~!」
私が兄のように慕うのは、真選組副長の土方 十四郎。人相は悪いけど、とても人情味溢れる人だ。
「おう、紅涙。なんだよ、遣いか?」
「うん、夜ご飯のね。」
「おばさんは元気にしてんのか。」
「元気だよ。今度の休みに来なよ、マヨ丼作ってあげるからさ。」
「そうだな、久しぶりに顔でも出すか。」
私がトシ兄を慕うきっかけになったのは母。
数年前、母が些細なトラブルで真選組のお世話になった時、担当についてくれたのがトシ兄だったらしい。その際の対応に惚れきった母は、私の武道教育係りにとトシ兄を指名。無理を言って、引き受けてもらったのが始まりだ。今だと考えられない状況だけど、当時の真選組はまだ模索中だったらしく、
「困ってる市民の力になるのも職務の一つだ!トシで良ければいくらでも使ってやってください!ガッハッハッ!」
と、局長さんも全面協力してくれて実現した。
「トシ兄は見廻り中?」
「ああ。この辺りに桂がウロついてるって情報が入ってな。」
「桂って…攘夷浪士の?」
「そう。お前も帰り道は気を付けろよ?まァ野郎が一般市民を巻き込むことはねェだろうけど。」
『一般市民を巻き込むことはない』
じゃあそう悪い人でもないの?…なんて、口が裂けても聞けないけど。
「じゃあな。」
「うん、また連絡してね。」
トシ兄はひらりと右手を上げ、立ち去った。私はその背を見送り、買い物リストを取り出す。
「えっとー…買わなきゃいけないのは――」
―――ドンッ
「っわ!?」
突然、後ろから強い衝撃を受けた。あまりに容赦ない強さに足がふらつく。
「なっ、何!?」
体勢を立て直し、振り返った。すると視界の端に人影が映る。既に私の横を通り過ぎていたその人は、目を引くほど綺麗な長い黒髪を風になびかせて歩いていた。
「…あれ?」
どうやら身につけている着物は男物だ。長い黒髪の…男……?
「もしかして…、」
もしかしてあの人、攘夷浪士の桂じゃない?さっきトシ兄が言ってた……え、引き留めた方がいいのかな。トシ兄に連絡してあげた方がいいの!?
スマホを取り出そうと手荷物を探る。ふと、自分の左肩に目が留まった。
「…ぅ、ええっ!?」
ななななな何よこれ!!
「っち…血ィィィィ!?」
どす黒く赤いもの…、いや紛れもなく血が、べっとりと付いている。
「…ハッ!」
しまった、こんな大声で言ったら騒ぎになる…!
と思ったけれど、私に注目している通行人は少ない。なぜなら、
「おい大丈夫か、あんちゃん!」
「しっかりしな!」
目と鼻の先で、先程すれ違ったばかりの長髪の男性が倒れていた。傍らに血溜まりを添えて。
「ということは…!?」
私の肩に付いてた血は、あの人の血!?
「っだ、大丈夫ですか!?」
すぐさま駆け寄った。何だかよく分からないけど、少なからず無関係でもない。ぶつかったせいで傷口が開いたという可能性もあるわけだし…。
「おい、嬢ちゃんも怪我してんのか!」
「いっいえ、これは私の血じゃありません。さっきそこでこの人とぶつかって…」
「アンタ、あんちゃんの知り合いなのかい!?そりゃ良かった!」
「え!?いっいや知り合いでは…」
「早く病院へ連れてってやりな!だいぶ血が出ちまってるよ!」
「いやっ、え……あ、は、はい…。」
まぁいいか…、急ぎの用があるわけでもないし、この人のことも心配だし。
スマホを取り出す。が、
―――パシッ…
「!?」
操作を妨げるかのようにスマホを握られた。握っているのは、今まさに救急車が必要であろうその人。
「医者など…無用だ。」
長髪の隙間から私を見る。向けられた視線は鋭く厳しいもの。だけどなぜかとても魅入られた。
「…あなたの怪我、かなり酷いですよ?」
「こんなもの…、…日常茶飯事。なんということはない。」
日常茶飯事?…もう完全に攘夷浪士じゃん。
「そなた…名は?」
「え、…あ、早雨 紅涙です…けど。」
「知らんな…、すまぬ…。」
…そりゃそうだと思いますよ。
「立てます?救急車を呼ばないなら、せめて手当てを…」
「触るな!」
「!」
触れる直前の手を止めた。
「俺のことは……いい。放っておいてくれ。」
立ち上がろうとする。けれど、
「くっ…、」
立てない。当然だ、こんなに血を流しているんだから。
「無理に動かないでください、死んじゃいますよ?」
「…女…、」
「はい?」
「余程の…世間知らずと……見える。」
「……、」
途切れ途切れに話すその額に汗が滲み始めている。
「…知ってますよ、あなたのこと。攘夷浪士の桂…さんでしょ?」
「ふっ…そうか、知った上での行いであったか。ならば…仕方あるまい。」
吐き捨てるように笑い、自分の傷口に目を落とす。溜め息を吐きながら空を仰いだ。
「…好きにしろ。」
「え、…いいんですか?」
「そのつもりであろう。と言っても、突き出されたところで幕府の犬如きに俺を…捕らえておくことなど……出来ん。」
『幕府の犬』?
そっか、救急車より真選組に連絡すべきなのかな。トシ兄もすぐに来てくれそう…だけど……、
「…わかりました。」
私はスマホを握り直す。
「それじゃあ救急車呼びますね。」
やっぱり病院が先だろう。…ごめんね、トシ兄。あとでちゃんと連絡するから。
「救急車…だと?」
「はい。病院に行きましょう。先に怪我をどうにかしないと。」
「っバカか貴様は!まずは真選組に連絡すべき事案であっ…て……くっ、」
腹部を押さえる。これだけ苦しんでいるのに、
「い、医者など不要だ…!」
まだ拒む。
「…もしかして、病院が嫌いなんですか?」
「そうではない。…ただ、」
「『ただ』?」
「よく分からん物を…体内に入れたくないだけだ。」
うーん…、
「これまではどうしてたんです?」
「無論、自力で治してきた。…数日じっとしていれば、自ずと治る。」
「でも今回はそうにもいかないと思うんですけど…」
「治る。いや治す。この程度どうということ…ッ、くっ、」
「動かないでください!」
話してる場合じゃない。とにかくこの人を手当てしないと…!
「行きますよ。」
「っ、俺は病院には…ッ」
「わかってます。だから、私の家に行きましょう。」
「!?……正気か?」
「正気です。このまま真選組へ通報する気にはなりませんし、このまま放っておくことも出来ませんから。」
それしかない。
「病院、どうしても行きたくないんですよね?」
「…行かぬ。」
「じゃあ私が支えるので、少しだけ我慢して歩いてください。大丈夫ですよ、そう遠くはありませんから。」
「…、……女。」
「はい?」
「そなたの名を…もう一度教えてくれないか。」
「紅涙です。早雨 紅涙。」
「…紅涙殿、」
「!」
「…すまぬな、世話になる。」
困ったように笑う表情を見て、小さく胸が鳴った。
「い、行きましょう…。」
私は色んなものに目をそむけ、桂さんの肩へ手を回した。
こんな人を連れて帰ったら、お母さんはきっと驚くだろう。血まみれなビジュアルにも、桂さんの存在にも。だけど必ず、
「まぁっ!どうしたのよ、その人!!」
「怪我をして倒れてたんだけど、病院に行きたくないって言うから…」
「早く横にしてあげなさい!お母さん、タオル持ってくるから!」
必ず受け入れてくれると思っていた。こういう精神を含めて学ばせるために、トシ兄を教育係に選んだようなものだもの。…まぁ今回の件でトシ兄を出すのは可哀相かもしれないけど。
「治るまでちゃんとうちで大人しくしてくださいね、桂さん。」
「…かたじけない。」
支えられながらも小さく頭を下げる。
こうして、私の家に攘夷浪士の桂さんを匿う生活が始まった。
…とはいえ。
これまで自力で治しきたと言うだけあり、治癒力は凄まじく高い人だった。パックリ開いていた傷口は瞬く間に塞がり、自由に動き回れるようになるまで二日。たったの二日だ。
「早雨殿、手伝えることはないか?」
「あら桂さん、まだ寝てないとダメじゃない!紅涙、アンタもちゃんと見てないと。」
「言っても聞かないんだもん。」
「俺の怪我は問題ない。二人のおかげで、早々に傷も閉じた。」
「閉じただけで治ったとは言わないよ?」
「治ったも同然だ。となると、じっとしているのは落ち着かんのでな。身体が鈍らぬよう、何か用事を与えてもらえると助かるのだが…」
「そうねぇ…それじゃあ――」
「あっ、でも桂さんはお遣い禁止だから!頼むなら掃除とかにしてよね!」
「はいはい。じゃあ窓の拭き掃除でもしてもらおうかしらね。紅涙も手伝いなさい。」
「はーい。」
お母さんには、桂さんが攘夷浪士であることを伝えていない。わざわざ言わなくても知っているかもしれないけど、それならそれで今さら口にしなくてもいいかなと思う。おそらくこの様子だと、そう長くは住まないだろうし…。
「ああそうだわ、紅涙。あとで買い物も行ってきてちょうだいね。」
「えー。窓拭きがいつまでかかるかも分かんないのに…。」
「紅涙殿、こちらは任せて買い出しへ行ってくれ。」
「…でも桂さんを見張ってないと、力いっぱい窓拭きしちゃいそうだし。」
「はは、心配はない。ここにいる間は無理などせぬ。」
「……うん、じゃあ行ってくる。」
「気を付けて。」
あと二日もすれば、この人の傷は本当に完治しまうかもしれない。
「…何だか拍子抜け。」
悪意はないけど、そんな気になる。
『ここにいる間は無理などせぬ』
…ここにいる間は。
「……はぁ。」
わけもなく溜め息が出た。
『今日』が続くのは、あとどのくらいなのだろう。
「楽しかったな…。」
まだ終わってないけど。
家を出て、買い物リストを見る。当たり前のように書かれていた三人分の材料にすら、なんとも言えない気持ちになった。
桂さんを匿ったこの二日、とても楽しい。特別面白いことがあったわけじゃないし、単に非日常な状況でそう感じているだけかもしれないけど、それでも確かに楽しかった。
「怪我が治っても、うちに住めばいいのに…。」
そうだ、そうすればいい。
トシ兄はああ言ってたけど、桂さんは悪い人じゃない。それどころか印象は良くなる一方。きっと皆は桂さんを知らないから悪いように言ってるんだ。私が話せば、これからの対応だって変わるかもしれない。
「そうなったら怪我が治った後も住める…?」
ごく普通に。この二日間よりも、もっと一般的に。……いや、どうだろう。問題はそこだけじゃない。
「誰か…いるのかな。」
桂さんを待っている誰かがいるのかもしれない。仲間とかじゃなく、そういう…特別な人。結婚はしてなさそうだけど、恋人くらいはいてもおかしくない。
「…どこに住んでるんだろう。」
うちを出たら、どこへ戻るつもり?またすぐに会える場所なのかな。この街で手配されてるんだし、近くに住んでるはず…だよね。
「…また、」
私の家を去っても、また…
「会えるよね…?」
…きっと。
「……、…。」
…ダメだ、今は考えないようにしよう。まだ出ていく日が決まったわけじゃない。落ち込むのは、決まってからでいい。
「落ち込む…?」
……うん、そうだ。私、桂さんがいなくなったら落ち込む。それってつまり―――
「紅涙じゃありやせんか。」
「っ!?」
身体が小さく跳ねた。視線を上げると、黒い隊服が目に入る。今は…あまり見たくない姿。
「お…お疲れ様です、沖田さん。」
「お疲れ。今日も親の手伝いですかィ?」
「…はい。」
沖田さんはトシ兄の部下。真選組隊士で…攘夷浪士の敵。
「いつも偉ェな、紅涙は。うちの隊士にも爪の垢を煎じて飲ませてくだせェ。なァ?」
ドンッと隣に立つ大きな人の背を叩く。
「原田、おめェも飲ませてもらえ。」
「はい!?俺かなり頑張ってる方っすけど!?」
「馬鹿言っちゃいけねェや。お前はハゲ方からして甘ェから。日頃からつまんねェハゲ方してんだから。」
「ここはデリケートな部分っすよ!デリケートな部分の話はタブー!イジらないで!!」
「あ、あの…私、買い物の途中なのでそろそろ……」
「ああすいやせん、つまんねェことに呼び止めちまって。」
「いえ…、…トシ兄にもよろしくお伝えてください。」
「そりゃご丁寧にどうも。」
「…では。」
頭を下げる。沖田さんの横を通り過ぎようとした時、
「あまり深入りしねェようにしなせェよ。」
「!」
そんなことを言われた。
「……失礼します。」
会釈をして立ち去る。あくまで冷静に、歩幅を変えずに。
「……。」
少し歩いた頃、細く息を吐いた。
「っ…、」
胸を押さえる。
やばいやばいやばい…!沖田さんのあの様子、絶対私の家に桂さんがいることに気付いてた!街であんな倒れ方をしたし、あっという間に噂が広がって真選組の耳に入ってたのかも…!
「じゃあトシ兄も……」
トシ兄も、知ってるのかな。知ってるんだろうな…。…悲しんでるかな。
「……ごめん。」
ごめんね、トシ兄。もう少しだけだから。
「……、」
『もう少し』には…したくないんだけど。
「はぁぁ…。」
今は家に帰れば大好きな空間がある。それでいい。…そう、まだあるんだから。桂さんが出て行くと決まったわけでも、真選組が私の家へ乗り込んでくるわけでもないんだから……
「明日にでも出ようと思う。」
「えっ!?」
安心して帰ったのも束の間、桂さんはその日の夜の食卓で突然告げた。おもむろに箸を置き、頭を下げる。
「二人のお陰で治りも早かった。長く世話になり、感謝している。」
「何言ってるのよ桂さん。長いだなんてまだ二日よ?もっとゆっくり身体を休めていかないと…」
「いや、もう十分に休めた。これだけゆっくりしたのは久しぶりだ。」
「忙しいのねぇ…。…ほら、紅涙も何か言いなさい。」
何かって…
「……よかったね、傷が早く治って。」
何を言えばいいのよ。
「本当に世話になった。」
やわらかく凛々しい笑み。この決断は揺るぎないものだと伝わる。だったら尚更、私に言えることなんて何もない。
「残念だわ…、」
お母さんは頬に手を当て、深刻そうに溜め息を吐いた。
「桂さんには紅涙の貰い手になってもらおうと思ったのに…。」
「ッ!?」
おっ、お母さん!?
「何言ってんの!?」
「アンタ懐いてたでしょ?こんなの土方君以来だったから…」
「あれはお兄ちゃんみたいなもの!今回とは別だし!」
「あら~、じゃあやっぱり桂さんには特別だったってことでしょ?」
「っ!?ちっ違っ…!!」
なんてこと言うのお母さん!
「違う!そんなんじゃないからっ!!」
「んも~、動揺しちゃって。」
「お母さんっ!!」
ほんとやめて!桂さんがいる前でこんなっ…
「っ…、」
「…。」
気まず過ぎる!!
「…うふふっ。」
お母さんは意地悪く笑った。ずっと静かな桂さんをそっと窺う。が、
「!!」
しっかり目が合ってしまった。
「っあっ、の…、」
「……。」
「……本当に…違う、から。」
「ああ。」
「特別とか…じゃないから…その…、…気にしないで。」
それしか言えない。そう言うしかない。
「わかっている。」
「……、…うん。」
出て行くと告げたこの人を引き留められる言葉なんて、私は知らない。
「……。」
「……。」
ひどく居心地が悪くなった。私はコップに入っていたお茶を一気に飲み干し、立ち上がる。
「……部屋に戻るから。」
「何言ってるのよ、桂さんと食べる最後のご飯なのよ?」
「!」
『最後の』
「もっとゆっくりここで――」
「最後とかっ」
「「?」」
「……最後とか、…わかんないじゃん。」
最後かどうかなんて…まだ分からないでしょ?ここを出て行ったらもう二度と会えないかもしれないなんて…
「そんな寂しい言い方…、…しないでよ。」
「紅涙…、」
「紅涙殿…。」
「……部屋に行く。」
「……さいあくだ。」
ベッドへ寝転び、うつ伏せになる。開けたままの窓から夜風が入ってきた。
「……。」
元々、別れは苦手な方だ。置いてけぼりにされる気持ちになって、寂しさが勝ってしまう。
『桂さんが回復してよかった、見送れることが嬉しい』
そう思わなければいけないのを頭で分かっていても、心の底からそう思えない自分がいつも嫌になる。
どうすれば満足な別れ方が出来る?私はどんな顔をして見送ればいい?笑って見送るなんて出来そうもない。けれど泣けば迷惑になる。
「でも……」
部屋に閉じこもって、このままさよならなんて…悲し過ぎる。
「……言えたらいいのに。」
何も考えず、誰の気持ちも考えず、『また会いたい』って。『また家に来て』って。『また一緒にご飯食べようね』って。
「素直に…なれたら……。」
きっともう少し、良い別れ方が出来るのに……
「俺は十分素直だと思うぞ。」
「!?」
声に飛び起きる。見れば、桂さんが「失礼している」と部屋の中で立っていた。
「ちょっ、なんで勝手に入ってるの!?」
「断りは入れた。返事はなかったが…」
「なら入っちゃダメ!」
「それは失礼。」
出て行こうとする。
「っべ、べつに!」
「?」
「べつに……、…出て行かなくてもいいけど。」
「そうか?ならば。」
桂さんがその場に腰を下ろした。
…この人、なんで来たんだろう。桂さんが私の部屋に来ること自体初めてだし。…え、ほんと何で来たの?…やばい…考えるとドキドキしてくる。
「ほう、」
袖の中へ腕を通し、両腕を組んだ。
「この部屋にはなかなか良い風が入ってくるな。」
「…普通だよ。」
「そうでもない。俺の住む場所ではこうした柔らかな風を感じることも出来ん。」
「……どこに…住んでるの?」
「ここより少々人の多い場所だ。と言っても仮住まいではあるが。」
仮住まい…。
「…本当の家は?」
「ない。」
「『ない』?」
「今は決まった家を持ち合わせていない。」
「……じゃあ、」
「ん?」
「じゃあここを…家にしたら?」
桂さんの家に。
「紅涙殿の家を?」
「…うん。帰る場所があると…、…帰らなきゃと思って怪我に気を付けるかもしれないし。」
本音半分、言えない気持ち半分。
「うちを…桂さんの家にしなよ。」
また会えると思いたいから、
「出て行っても…ここに帰ってくればいいよ。」
また来ると、言ってほしい。
「ね…?桂さん。」
それだけでいいのに、
「…出来ん。」
桂さんは、頷かない。
「……なんで?」
「今回の負傷で得たものは実に大きかった。二人に迷惑を掛けてなんだが、俺はあの時あの場所で倒れて良かったと思っている。…けれど、」
この人は、
「けれど俺がここへ帰ってくることはない。」
私に希望さえ与えてくれないんだ。
「…答えになってないよ。」
「すまない。」
「っ、だからっ……、…どうしてって聞いてるの。」
「俺は攘夷だ。」
「わかってる。」
「俺がいると、いずれ迷惑をかけてしまう。」
「私はそれも覚悟して言ってるの。」
「……、」
「…どうして、」
どうして『そうだな』って言ってくれないの?どうして『そうしようかな』って言ってくれないの?どうして、
「…すまない、紅涙殿。」
「っ…、」
嘘でも、私に合わせてくれないのよ…。
「…真面目すぎでしょ、桂さん。」
「すまない。」
…違う。そんな言葉が欲しいんじゃない。
「私はただ……、…。」
「……。」
「……もういい、わかった。」
どうしようもないなら、桂さんがここに何も残してくれないのなら…私から残させる。
「出て行くの、…明日だよね。」
「そのつもりだ。」
「私、明日は予定あるの。だからたぶん見送れない。」
そんなの嘘。予定なんてない。私は桂さんみたいに真面目じゃないから、こうやって嘘も吐ける。
「…だからさ、」
都合よく嘘を吐いて、
「だから今、…最後にキスしてよ。」
自分勝手に望むことだって出来る。
「……なに?」
「真面目だから出来ない?」
鼻先で笑った。顔では桂さんを小馬鹿にしながらも、右手は小さく震えている。その手を左手で握り締め、
「してよ、桂さん。」
私は桂さんを見た。
「何を…言っているんだ?」
「日本語。」
「いや…それは分かるが……」
真面目だなぁ…。
「いいじゃん、キスくらい。」
「『くらい』などと…」
「して。」
「……、」
こうなると分かってた。だけどそれをくつがえしてくれるかもしれない行動も期待していた。たとえ…
「…やはり、」
そうなる望みすら、与えてくれないような人でも。
「やはり俺は…長く居すぎたようだ。」
桂さんが立ち上がる。窓辺に向かい、欠けた月を見上げた。
「これ以上は害しか生まれぬ。紅涙殿にとっても、…俺にとっても。」
あなたは、真面目すぎる。
「…明日と言ったが、少し早めることしよう。」
真面目すぎて、
「今ならまだ間に合う。まだ何も…生まれてはいないのだから。」
…残酷だ。
「早雨殿には挨拶せずに立ち去ることを詫びておいてほしい。」
窓へ手を掛ける。髪が流れるように揺れた。
今手を伸ばせば、あの髪に届く。髪を掴んで、少しでも長くこの人を…ここに……
「二人と過ごした時間はどこか懐かしく…とても楽しかった。」
「……、」
「ありがとう、…紅涙殿。」
「…。」
振り返った桂さんが優しく微笑む。私は今にも伸ばしてしまいそうだった自分の手を握り締めた。
「俺のことを真選組に伝えなかったこと、心から感謝する。」
「…一つだけ、教えてほしいんだけど。」
「なんだ?」
「……うちの家族と、真選組に繋がりがあるって知ったのはいつ?」
「ここへ運んでもらった日だ。何の話だったか、早雨殿がそんな話をしていてな。」
そうだったんだ…。
「…じゃあどうして逃げなかったの?」
そんなに早くから知っていたのなら、警戒してその日のうちに出て行ってもおかしくなかったはず。
「質問は一つだけという話であったが…。」
「…真面目すぎる男はつまんないよ。」
「ははっ。ならばもう一つだけ答えよう。」
軽く笑い、あごに手をやる。
「そうだな、ここを立ち去らなかったわけは……強いて言うなら『家』だったからか。」
「家…?」
「ああ。遠い昔に置いてきた何かを感じた。俺がもう…手に入れることはないと思っていた何かを。」
目を細め、
「つまりは居心地が良かったのだ。…それだけのこと。」
ゆっくり目を伏せた。
「じゃあ――」
「いや、」
桂さんは私の言葉を予測していたように首を振った。
「ゆえにだ。」
目を開け、私を見据える。
「ゆえに俺は、ここを去らねばならん。」
……、
「…わかんない。」
どうしてそうなるの?
「わかんないよ。」
「それでいい。」
「っ、わかるように言って!」
はっきり言えばいい。居心地は良かったけど、もう用がなくなったんだって。私達との時間なんて、その程度のものだったんだって。そうじゃないと私、この生温い言葉を胸に抱いて明日を迎えなければならなくなる。もう期待なんてしたくないのに、
「…そなたのような女子に、こんなつまらぬ男は似合わんよ。」
「っ…」
期待したくなる。
「俺のことは忘れてくれ。」
「っ、そんなのっ、私の勝手だし!」
「ああ勝手だ。だが忠告はしておこう。」
桂さんが私の方へ歩み寄った。
「紅涙殿、」
これが最後。きっとこの会話が、桂さんとの最後になる。
「今後、会って三日と経たぬ男に唇を捧げようなどと思うてはならんぞ。」
「……え、」
「どれだけ良い振る舞いをしても、そやつがどんな化けの皮をかぶった野郎かは分からんのだ。」
「……、」
最後の最後で…お説教?
「あといくら負傷していたとはいえ、見知らぬ男を家へ招き入れるのもどうかと思う。ああいう時はまず救急車を…いや俺は救急車など不要であったが、通常は救急車を拒むような男を家へ連れ帰る行為は非常に危険であって……」
「ほんと真面目。」
「大事な話であろう。次に誰かを助ける時は、もう少し警戒してほしいのだ俺は。」
「はぁ……わかった、気を付ける。それでいい?」
「うむ。…では紅涙殿、」
ふわっと風が吹き、
―――チュッ…
「!」
唐突に、
「…さよならだ。」
桂さんは私の額に口付けをして、窓から消えた。触れるか触れないか分からない程度の、弱く優しい口付け。
「……なによ、」
渦中のその人は、もういない。
「わけ分かんない…!」
忘れてほしいと言いながら、こんなことして。私の記憶に痕を残して。
「…、……謝ってよ、桂さん…。」
まだ近くにいるんじゃないかと、声にする。けれどやっぱりあの人は、私の望みを叶えてはくれない。
「…ほんと……真面目すぎ。」
恋しかりける
私は今日も買い出しに出る。
非日常が去れば、また日常が戻るだけ。なんということのない日々は、まさに私の日常。
「あと買うのは……」
あの二日を忘れはしない。忘れはしないけど、落ち込んでばかりもいない。落ち込んだ先に、何か得るものがあるわけじゃないから。私の立っている場所で前を向く。…ちなみにこれはトシ兄の受け売りだ。
「……元気にしてるかな。」
桂さん。あと、トシ兄も。あれからまだ会えていない。偶然なのか、あえてなのか。久しぶりに真選組に差し入れでも持って行こうか。お母さんも気にしてたし、そろそろ行っても問題は……
―――ドンッ
「!?」
後ろから誰かに押されたような衝撃を受ける。振り返る前に、その原因であろう人影がドサッと倒れた。
「えっ…」
驚いた私の目に映るのは、いつかと同じ黒い長髪。心臓が波打った。
「……ぅ、…」
倒れたその人は、弱々しくこちらへ顔を向ける。
「また…会ったな。」
「……、」
鮮明に蘇る出逢い。私の全身に流れる伝わる喜び。それら全てを隠して、
「……呼びますか?…救急車。」
私は倒れる人影の傍に腰を下ろした。
「いや、救急車は不要…だ。」
「…それなら私の家で手当てしたいところなんですが、」
「…『ですが』?」
「少し前に、知り合いの男性から『無闇に負傷者を連れ帰るな』と注意されまして。」
「ほう…、それは至極真っ当な話であるな。」
フッと弱く笑う。
「…しかしその男、『会って3日と経たない男に気をつけろ』と言ってなかったか…?つまり、今の俺達には当てはまらぬ話だと…思うのだが。」
そうですね。…だけどその言い方だと、
「まるで私の前を狙って倒れたみたいに聞こえますね。」
違う?
「…さてな。」
「……、」
わかんない人だな…。でも、
「いいですよ、」
なんでも。
「…おかえりなさい、桂さん。」
私はきっと、この先もこの人が倒れていれば助ける。いつか、
「……今回も世話になる、紅涙殿。」
illust…くろだうらら様
novel…にいどめせつな
2020.11.3 novel加筆修正
 |
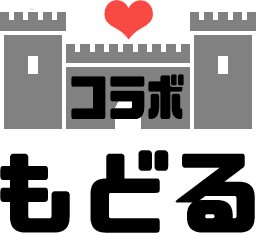 |
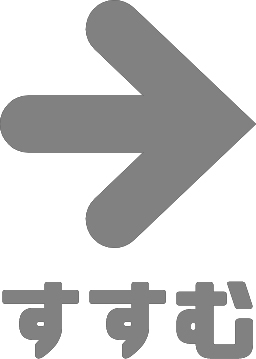 |
