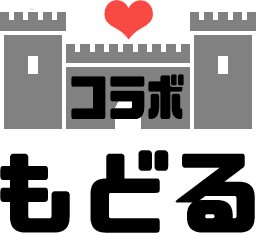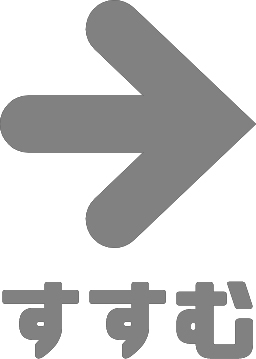「あー今日も疲れたなァ。」
赤毛の男が服を脱ぐ。『疲れた』と言ってはいるが、常時にこやかな笑みを浮かべているため真意は読み取れない。
「…ねえ、紅涙は?」
「お呼びしますか?」
部屋の入口に立っていた遣いの者が、うやうやしく問い掛ける。男は溜め息混じりに白いベッドへ腰掛けた。
「うん、呼んで。」
船の中ということもあり、ベッドの質は良くない。部屋も手狭で、どちらかと言えば居心地は悪い方だ。
しかし男はこの部屋へ帰るのが嫌いではなかった。
…なぜなら、
「『ご主人様のお帰りだよ』って伝えてきて。」
ここにしかない『モノ』があるから。

それはまだ鳳仙が吉原を統べていた頃。
地球に似た緑の多い小さな星は、以前から春雨の支配下に置かれていた。
「全く。何もねーじゃねェかよ。」
傘を差した大柄の男が、床に倒れた襖を蹴り飛ばす。…いや、先ほどまで襖だったもので、今やただの残骸。
「あのジイさん、いつも始末する時だけ俺達を星に入れやがるな。こちとら掃除係じゃねェっつーの。」
「そう?お片付けも悪くないでしょ。」
大柄の男と同じような傘を差し、赤毛を三つ編みにした男がニコニコして言った。
「憎しみがもたらす人の成長具合も分かるし、潰す時にはそこそこ楽しめる。」
「なら今回の星の評価は?」
「3.5。消しちゃうのが勿体ない感じだね、残念。」
「欠片も残念ぽくない顔つきだがな…。」
「そんなことないよ?ほんとに残念だと思ってる。…にしても俺も歳かな、随分と時間かかっちゃった。」
「よく言うぜ、充分に瞬殺だったじゃねーか。神威サマはまだまだご健在だよ。」
『神威』
ああ、聞いたことがある。絶望の根源。この世に存在してはならない人。
そんな男を生きて目にしてしまった私達は、一体どうなるのだろう。
「さてと。」
大柄の男が私達を見た。つまらなさそうにして、「手配するか」と言う。
「これだけ女がいたら、一人くらい貰っても分かんねーと思うんだが、」
端から私達に目をやり、「どう思う?」と赤毛の男『神威』を窺い見た。
「いいんじゃない?一人くらいなら。」
「だよな、じゃあ三人ほど貰ってくか。」
「ほんと好きだね、阿伏兎は。」
『阿伏兎』と呼ばれた大柄の男は、早々に見定める。自分が気に入った三人の手足にかかる縄を切り、引き寄せた。
「キャアッ!」
彼女達から小さな悲鳴が挙がる。
「ククッ、大人しくしてりゃ可愛がってやるからよ。」
どちらの未来がいいのか分からない。あの男に連れて行かれて人形になるか、売り飛ばされた吉原で一生を終えるか。
後者なら、良い人に見初められて好転するかもしれない…なんてのは夢だ。現実はそんなに甘くない。こんな形で吉原に入る私達なら、同胞となる女性達からも酷い扱いを受けるだろう。都合良く客をあてがわれ、雑用以下の仕事をさせられ、朽ち果てるように死ぬ。
「何だよ、団長はいらねーのか?」
もしこの男に連れ去られたら、使い古された挙句に殺される。ならばこんな一生、早く終えられる方が幸せかもしれない。
「どうしよっかなー。俺は阿伏兎みたいな犬じゃないし。」
「犬?」
「年中発情期じゃないってこと。」
「ケッ。」
ここにいる者は皆、絶対的な力を見せつけられている。恨みや憎しみを抱くことすら出来ないほど圧倒されている。
何せこの人達がたった二人で星を消そうとする光景を見せられたのだから。『生きたい』等という当たり前の権限すら、今は恐れ多い。
「ま、俺の方が断然マトモだもんな!アンタは血さえありゃいい吸血鬼。」
阿伏兎は数人の女を抱き寄せ、満足そうに笑った。
「所詮、人間じゃねーよ。」
「……そう、」
神威は変わらず笑みを浮かべ、
「そんなこと言っちゃうんだね。」
ポンと阿伏兎の肩に手を置いた。途端、阿伏兎の顔が強ばる。
「あっ、わっ悪い団長…ッ、」
「今日はすごくご機嫌みたいだけど、」
「いやっ、すまん、っ悪ふざけが」
「あんまりお喋りが過ぎると、」
―――メキッ…
「グアァァッ!」
「殺しちゃうぞ。」
「ッぐっ、」
阿伏兎が肩を押さえた。押さえている方の腕は力なくぶら下がっている。
「やだなー、大袈裟。折れたくらいじゃそこまで痛くないはずだよ。それとも落としてほしいっていうアピール?」
「ッわ、悪かった…、くッ、」
「ふふふ。…でもそうだなー、そこまで言うなら俺も一人連れて行くことにしようかな。」
「なっ!?」
神威の言葉に阿伏兎が驚いた。
「どういう風の吹き回しだよ、団長。」
「単に気が変わっただけだよ。」
「槍が降るぞ…。」
「槍なんて降らないよ。」
笑みを浮かべたまま、神威が私達を見た。
「んーっと…」
「どうせまた何か思い付いたんだろ?」
「まーね。ほら、さっき歳を感じたから。」
「それが?」
「早めに俺の血を遺して育てておこうと思ってさ。」
「はアァァァ!?ガキを作るってのか!?」
「子どもじゃないよ、作るのは俺の五体となる存在。まァ無理だろうけど、ないよりマシでしょ?」
「おいおい…そんなのが出来たら、星という星が壊滅しちまう。」
「そう出来るといいね。…よし、決めた。」
神威はスッと人差し指を出し、
「お前にしてあげる。」
私を指さした。
「え、…私?」
「待て団長!ガキを作る相手は誰でもいいのか!?」
「俺の遺伝子があるからどうとでもなるよ。使えない子が出来たら、まァ…それまでの話。」
「だからって何の素質もねェ女を…」
「それは分からないでしょ。だって、」
にこやかに細められた神威の目が、僅かに開く。
「だってコイツ、ずーっと何か考えてたみたいだから。」
私に向かって冷たく笑った。その眼に捕らわれた瞬間、血の気が引く。改めて私の命はこの男に握られていることを認識させられた。
「なんだ、逃げることでも考えてたのか?女。」
「っ…」
首を左右に振る。それを見た神威が頷いた。
「うん、そんなのじゃないよね。」
「団長は分かってんのかよ。」
「俺も分かんないよ?けど考えてた内容なんてどうでもいい。ただ、」
こちらへ歩み寄り、私の腕を雑に掴んだ。
「この状況下で冷静な眼をしていたことに評価したいんだ、俺は。」
私の手足にあった縄を切った。
「お前、名前は?」
「…紅涙。」
「そう。俺は神威。」
にこにこした笑顔を近づけ、私の耳元で囁く。
「今日からお前のご主人様だよ。」
「…お帰りなさいませ、神威さま。」
「うん、ただいま。」
こんな関係はこの部屋にいる時だけ。
一歩外へ出れば、神威さまは私など目にも入れない。必要な時にだけ呼びつけ、用がなくなれば檻へ戻す。牢獄とまで言わないが、私に与えられている部屋はベッドしかない質素なもので、外出なども許されない『檻』と同じ。
「あー今日も疲れたよ。」
ベッドに座る神威さまは、自身の左肩に手を置いて気怠そうに首を回した。既に服を脱いでいる上半身は、いつもと変わらず傷がない。
「…。」
古傷すらない綺麗な肌と、童顔に似合わない筋肉。
「…何してんの?」
「…、」
「遠いでしょ。」
言われて足を進める。手の届く距離まで来ると、腕を引っぱられた。
「ふふ、掴まえた。」
腰掛けたままで私を抱き締め、擦り寄るようにして胸へ顔を埋める。
「いい匂いだねー、紅涙。」
「っ、神威さま…」
この人の行動はいつも読めない。こうして甘えるようなこともするし、
「お前の血はきっと美味しいよね?楽しみだなー。」
最期を待ちわびているようなことも言う。それはどれも私に固執しているようにも聞こえるし、
「少しだけ確認してみようか。味見だけで済むか分かんないけど。」
私自身においてはどうでもいいようにも聞こえる。
そもそも自分の子を遺したくて連れてきたはずなのに、この人は数えきれない行為を重ねても成そうとしない。だからと言って、拒絶こそ許されないが、私を奴隷のように扱うわけでもない。
この、違和感。
「…今なに考えてんの?」
この違和感に神威さま自身が気付いた時、私の命は終わりを告げるはずだ。
「…神威さまのことを考えています。」
「ほんとかなー?」
今はまだ変わらない。にこにこした表情も、ずっと同じ。
「まァいいや。それよりほら、紅涙。」
私の唇に親指が触れた。神威さまの眼が薄らと開く。
「ボーっとしてないで、俺に血をちょーだいよ。」
唇を噛めという指示。
「…はい。」
私は唇の内側を噛み、その深く先の見えない瞳を見た。
「うん、いい子。」
傷口を指でなぞられる。私の血が神威さまの親指に付いた。それを紅い舌が舐め取る。私の血なんかよりも紅い、その舌で。
「…こんな少しじゃ分からないな。」
私の首の後ろへ手を回す。強く引き寄せたかと思うと、かぶりつくように下唇へ吸いついてきた。
「ぅッ、」
神威さまの舌が何度も傷口を舐める。今しがた出来たばかりの傷をこうも舐められると痛くて、眉を寄せた。
「痛い?」
「ん…、」
「痛いってイイことだよ。生きてる証拠だから。」
神威さまが不吉に笑む。そしてより強く吸いついた。
「っ、」
「…ふふ。」
小さな笑いを残し、唇から離れた。かと思うと、今度は伸ばした舌で私の首筋をなぞり始める。脈を確かめるように、何度も何度も動脈の辺りを執拗に。
「…お前は俺の何なんだろうね。」
「…、」
ぽつりと呟いた声は、
「…神威…さま?」
違和感に気付いたのかと思った。けれど、
「なに?」
私の目に映る顔は、いつもと同じ。
「…いえ、……何も。」
翌日、
「あー疲れた。」
神威さまは昨日と大差ない声音でベッドに腰掛けた。…でも、
「傷…、」
服を脱いだその肌に、いくつもの傷がある。それほど深くはないものの、傷があるのは初めてだ。初めてなのに、いくつもの傷。
「一体誰が…」
「ああ、これ?鳳仙の旦那。」
…え?それは……あの鳳仙?
「あなたの…師の?」
「そうだよ。でも昔の話。」
「『昔』……」
「今は俺の方が強いんだ。だって、」
にこにこした顔つきは崩れない。
「俺が殺したんだから。」
「…、」
彼は、何にも執着しない。
「最期は酷いもんだったよ。ただのジジィ。酒と女に呑まれた夜兔の恥晒し。」
人にも、情にも、過去という思い出すらも、彼の心に書き残すことは出来ない。
「俺は絶対ああはならない。」
神威さまが手を伸ばした。私が近付くと、腰かけたまま抱き寄せる。
「俺は違うんだ。」
「…神威さま?」
「俺は腐らない。」
私の胸に顔を埋めた。
「一生理解しない。闘争と力だけを求めて生きていく。」
これは…私に話しかけてるんじゃない。
「神威さま……。」
戦ってるんだ、自分自身と。自分の中にある弱さと。
…でも、それは単なる弱さなのだろうか。もしかしたらそれは…あなたの中に残る―――
「なら紅涙、」
神威さまが顔を上げる。いつもの笑みがない。
「お前はどうしてここにいる?」
「え…、」
…私は……、
「神威さまに…呼ばれたので。」
「だったら俺はなぜお前を置いてる?」
「……、」
「俺が渇望するのは女じゃない。力だ。」
この人がこんなことを口にするのは初めてだった。ましてや、私如きに。
「俺は、あんな腐った男にはならない。」
つまりこれは…、
「……はい。」
違和感に気付き、『私』を否定している。
とうとう終わる日が来たのだ。
おそらく神威さまはずっと、潜在的な部分で鳳仙のことを考えていた。そのせいで私を連れ帰るような事態になった。
本当は、鳳仙の変わり様に酷くショックを受けていたのだろう。自分の手で殺した今ではえ影響を受け続けている。…本人は認めないだろうけど。
「…神威さまの望むままに。」
「お前は賢いね。…よくわかってる。」
この人は自分の戸惑いを解決する手札が限りなく少ない。少ないから争い、倒す。そのために力が必要。
…でも、解決した時にはいつも誰もいない。何も残らない。ひとりぼっち。
「俺に女はいらない。」
だからまた一人で歩き出す。これまでと同じ歩き方で。一人ゆえに、より偉大な力を求めて。
「…だけど、」
「はい。」
「紅涙はいる。」
「…?」
それは…どういうこと?
「私は…いる?」
「あー勘違いしないで。紅涙は女じゃないってこと。」
私は…女じゃない?
「気付いたんだ、お前は生きるのに必要なものだって。言わば、瞬きや呼吸と同じ。だから俺は女として紅涙を置いてるわけじゃなく、生きる糧として置いてる。」
神威さまは満足そうに笑った。
「どうりで捨てなかったはずだよ。本能が言ってたんだね、きっと。」
「……、」
彼はいつから、こんな風になったのだろう。
「やっぱり俺は、あんな腐れジジィとは違う。」
私なんて、生きるのに必要なわけがない。
それでも今その答えを否定したら、彼はまた、誰もいない世界で歩き出してしまうのだろう。
「いいかい、紅涙。女になっちゃダメだよ。じゃないと俺、殺しちゃうから。」
大丈夫。この人はまだ壊れきっていない。まだちゃんと、人の子だ。
「ね?」
だからそんな風に脅さなくてもいい。私はここにいる。あなたがその手で消し去らない限り、私は傍にいるのだから、
「…はい、神威さま。」
大丈夫。
必ず、あなたが誰かを愛する日は来ます。たとえその口で愛を囁かなくても、心で受け入れる時が来る。
私はそう信じてるから、
「お傍におります、…いつまでも。」
共に生きていこう。この、狭い世界の中で。