望んだ日常+息を切らす日課
もし時間を戻せるなら、私は―――
「コルァァ!紅涙ッ!!」
「はいィィッ!」
屯所の入り口で、咥え煙草の土方さんが目を三角にする。
「テメェまた遅れやがったな!?2分の遅刻だぞ、わかってんのか!?」
「はいっ、すみません!」
「用意が遅ェんなら、事前に準備しとけっていつも言ってんだろ!?」
「はいっ、申し訳ありませんでした!」
「……ったく、返事だけはしっかりしやがる。」
「ありがとうございます!」
「褒めてねェよ!」
―――バシッ
「イタッ!」
叩かれた頭を手で押さえる。
そんな私を土方さんは鼻で笑い、煙草を咥えた。
…本当は、大して痛くなかったりする。
本当の本当は、わざと遅刻していたりする。
私は自室で時計を見ながら正座し、わざわざ2分遅刻するのを待っているのだ。
それも全て、
「とっとと見廻り行くぞ。」
「はい!」
少しでも、土方さんの中に印象を残すため。
土方さんが一日を思い返した時、そこに私を登場させるため。
…我ながら姑息な手段だけど。
「……ムフッ、」
「なに気持ち悪ィ顔してんだ。」
「いえ!なんでもありません!」
私が真選組に入隊したいと思ったのも、土方さんとの出逢いがあったから。
下品で野蛮な野郎…失礼、男達に絡まれていた私を、巡回中だった土方さんが助けてくれた。
男が刃物を振り回しても、煙草片手に華麗にかわす。仲間を呼びつけて一斉に殴りかかられても、土方さんは汗ひとつかかず、全員を峰打ちで気絶させて逮捕した。
「怪我はねェか?」
声をかけられて、事が終えたことに気付く。私は眼前の光景に、目も胸も輝いていた。
「っあ、あの!」
「ん?」
「でっ、ででで弟子にしてくださいっ!!」
「……はァ?」
「感動しました!弟子にしてください!!」
「…意味わかんねェ。」
怪訝な顔つきで私を見る。
「頭でも殴られたか?」
「えっ!?や、違っ…ほ、本気です!本気で弟子にしてもらいたくてっ」
「わけ分かんねェこと言ってねェで、とっとと帰れ。」
煙草を吸い、「気をつけてな」と背を向けられた。
…マズい。この様子、私の気持ちが全く伝わってない!
「待ってください!」
土方さんの上着を引っ張り、引き留める。振り返る土方さんに、すぐさま頭を下げた。
「本気なんです!お願いしますッ!!」
「馬鹿言ってんじゃ――」
「あなたの傍で学ばせてください!!」
「…。」
土方さんが口を閉じた。ジッと私を黙り見る。私はその瞳に、熱意ある眼差しを送り続けた。
きっと…きっとこの沈黙は私を受け入れようと考えてくれている時間のはず……!
「断る。」
「!?」
違った!
「じゃあな。」
「っま、待ってください!どうしてですか!?」
「どうしても何も、弟子なんて取ってねェんだよ。」
「なら私を第一号にしてください!」
「いらねェ。」
「そう言わずに!!」
「いらねェもんは、いらねェ。そんな暇ねェし。」
「頑張りますから!私、必ず役に立ってみせますから!!」
「しつけェ!!」
断固として首を縦に振らない土方さんに、
「お願いしますっ!!」
私も譲らず。
土方さんがその場から立ち去ろうとしようものなら、隊服にすがりついて引き留めた。
「おいコラやめろ!」
「どうかお願いします!一生のお願いです!!」
「嘘つけ!!」
いくら引き離されそうになっても、
「お願いします~っ!」
絶対に手を離さなかった。
だって、今まで生きてきて、こんなにも胸が高鳴ったのは初めて。この瞬間を追わなければ、きっとこの先、私の人生はつまらない一生になる。…そんな気がするから、
「弟子がダメなら、表向きは真選組の隊士で構いません!」
とにかく必死だった。
「諦めろ、うちは女を取ってねェ。」
「え!?差別!?性差別!?警察なのに性差別して、女性は入隊できないんですか!?」
「くっ、…」
否定的な言葉には、ことごとく喰らいついた。
分が悪くなると、土方さんは無理にでも立ち去ろうとする。ならばと私は足にしがみつき、動きを抑え込んだ。
「あァ!?てめっ…重ェ!!」
「お願いします!!根性だけはあるんです!!」
「だろうな!」
どうやったらこの人の傍にいれる?どうやったらこの人に受け入れてもらえる?
しがみつきながら必死に頭を働かせていると、
「…副長、もういいんじゃないですか?連れて行ってあげれば。」
まるで天の声、もとい、いつからいたのか分からない山崎さんの声で流れが一変した。
「そろそろ行かないと、道行く人の視線も痛いですし…。」
「……チッ。」
舌打ちした土方さんが私を見る。
「…わかった、近藤さんには会わせてやる。」
「ヤッ」
「ただし!テメェで頭を下げて入隊許可を貰え。いいな?」
「ありがとうございます!!!」
こうして私は真選組へ向かい、
「へー!いいじゃん、女性の隊士も。」
近藤さんに、あっさりと入隊を認めてもらう。
「おい、もっとちゃんと考えてくれ!」
「考えてるよ~。俺、前からむさ苦しい連中だけより女性もいた方がいいんじゃねェかなって思ってたんだよね~。ほら、犯人にしろ被害者にしろ、女性同士で話した方がいい時ってあるじゃん?」
「そりゃそうだが……、……はぁ。」
土方さんは溜め息を吐き、眉を寄せた。
「じゃあ良いんだな?近藤さん。」
「良い良い!全然良い!」
「……はぁぁ、…わァったよ。」
あからさまに『仕方ない』と顔に書いた土方さんが頷く。だとしても、許可は許可だ。
……そうして入隊した私だけど、
太刀筋が云々とも言えぬほど、武術にズブの素人。ただ頑張る熱意と、土方さんへの想いだけは人一倍ある!
…という事実を知った時の土方さんと言ったら。
「…。」
絶句はもちろん、呆れと後悔、面倒さ等、ありとあらゆるマイナスの感情を顔に乗せていた。
「え、えへ…。」
「……はぁぁぁ~。」
鬱陶しいほどの情熱が、ようやく伝わったのかもしれない。
真選組から追い出されるようなことはなく、それどころか一から鍛え上げてくれることとなった。
おかげで私は時間とともに、それなりに成長。
直接的に隊に属さないものの、少なからず『役に立ちますから』と頼み込んだあの日の言葉に偽りがない程度の実力を身に付けることが出来た。
今となっては、土方さんと二人で市中見廻りをしていても…
「キャァァッ!!泥棒ォォーッ!!!」
「「!」」
「紅涙!」
「はい!」
率先して私を走らせてくれる。
当初は行かせてもらえなかったけど、今は煙草片手に「行って来い」と送り出してもらっている。信頼、信用を得たから…だと思う。
私は嬉々として罪人を捕まえ、土方さんが辿り着くまでに締め上げる。後からゆらゆらと歩いてきた土方さんが、
「手間をかけさせやがって。」
罪人を見下ろしながら煙を吐く。
「二度としねェよう反省するこったな。」
全うなことを言い、反省の色がない罪人に煙草を近付ける。その横で、私は被害者に話を聞きながら持ち物を返した。
この一連の流れが、今ではすっかり定着している。
「さて、」
短くなった煙草を手持ちの灰皿に押し付け、すぐさま新しい煙草を取り出す。
「帰るか、紅涙。」
夕陽を背景に、少しだけこちらに振り返って私を呼ぶ。
「はい!」
私が望んで手に入れた世界だった。
こうして手に入れた楽しい日々は、形を変えず、永遠に続いていくものだと思っている。…いや、思っていた。
「いや~、絶好の昼寝日和でさァ。」
「だねぇ~。」
ある日の午後。
私は真選組の一番隊隊長である沖田君と、陽の当たる廊下で横になっていた。
彼は私を快く受け入れてくれた偏見のない一人。隊長扱いすら不要だと言って、竹刀稽古にも嫌な顔ひとつせず付き合ってくれていた。
『どこまで良い人なの沖田君!』
はじめの頃は毎日のように崇めていたっけ。
沖田君は決まって腕組みをして、得意げに鼻先で笑っていた。
『まァ紅涙と違って、俺ァこの道のエリートなもんで』
『嗚呼、なんと眩しい!神々しいっ!』
あの時から、沖田君に対する印象は差程変わっていない。
相変わらずこの人は頼もしく、優しい。土方さんとまた違う優しさを持っている。
「…いつもありがとね、沖田君。」
アイマスク姿で寝転ぶ沖田君に微笑んだ。
「何でさァ、いきなり。」
「ふと言いたくなったの。」
「なんだそれ。死亡フラグでも立ちやしたか。」
「やめてよ、縁起でもない。」
「ならなんで言いたくなったのか詳しく話しなせェ。」
「え~、それはやだ。面倒くさい。」
「はァ~?」
「私も寝よっと!」
沖田君から貰った色違いのアイマスクを取り出し、目元に着ける。真っ暗になった世界に沖田君の声が響く。
「おいコラ紅涙。言わねェと襲うぞ。」
「襲わないよ、沖田君は。私のことを大事に思ってくれてるもん。」
「…大したタマでさァ。」
フッと笑う吐息が聞こえた。
私達は、互いをかけがえのない友人だと言える。
仲間を上回り、共に信頼し合える友だ。
長い付き合いではないけれど、恐れ多くも、時の長さなど気にならないくらい心が繋がっていると思う。だから、
「仕方ねェ、仕切り直しとしやすか。」
「うん、そうしようそうしよう。」
沖田君の隣は心地がいい。
アイマスクの下で、穏やかな空気に身を沈めた。
聞こえてくるのは鳥の鳴き声と、かすかな隊士達の声。瞬く間に眠りの波がやって……
『……ぅおい!』
…ん?
『おいコルァッ!』
……あ。
『何やってんだテメェらァァァ!!』
ドタドタと走る足音が近付いてきた。
どうやら向かいの廊下から見つけたらしい。けれど、私達に焦りはない。なぜなら、
「おいコラ!今は勤務中だろうが!!」
「勤務してますぜ、なァ?紅涙。」
「沖田君の言う通り、してます!」
こう見えて、ちゃんと仕事中だから。
私はアイマスクを額に上げ、起き上がった。沖田君は未だアイマスクも上げず、寝転んだままでいる。
「その姿のどこがどう仕事してっつーんだ!」
「目を覆うことで邪念を払い、研ぎ澄ました環境で近辺を警戒してるんですぜ。」
もっともらしいことを言う沖田君に、土方さんがわなわなと肩を震わせ始めた。
「…ああそうかよ。」
…あれ。今日は少し雲行きが怪しい。
「ね、ねぇ沖――」
「テメェらが研ぎ澄ましてるってんなら、」
起こそうとする私の前で、土方さんが静かに抜刀する。これはさすがにヤバい。
「おっ、沖田君、ちょっと」
「今どういう状況か分かってんだよなァァ?」
「沖田君!もう起きた方がっ…」
「紅涙、つまんねェですぜ。そのダジャレ。」
「へ!?今そんなこと言ってる場合じゃ――」
「表出やがれェェェ!!」
「沖田君ゥゥゥーッ!!」
土方さんが刀を振り上げる姿に、私は慌ててその場を離れた。
沖田君、ごめん!
でもあれ以上あの場にいたら絶対斬られて……
「チッ、人の昼寝を邪魔しやがって。」
「沖田君!いつの間に…」
って、昼寝って言ったらダメじゃん。
沖田君はダダッと私と同じように廊下を走る。
さすがは一番隊隊長だ。あの状況から起き上がって走り出せるとは。
「待ちやがれコルァァァッ!!」
「ヒッ…!」
迫る怒気に背筋が震える。足がすくんだ。
「紅涙!」
あっという間に前を走る沖田君が私に手を伸ばした。
「何やってんでさァ!早く走れ!!」
「っう、うん!」
沖田君の手を掴み、再び加速する。
こうして昼間の廊下を走るのも、もはや日課のようなものになっていた。
沖田君絡みの土方さんは怖いけど、息を切らすこの時間には妙な充実感がある。
「沖田君!」
「あァん?」
「楽しいね!」
「…そんな余裕あるならテメェの足で走りなせェ。」
「ああっダメダメ!絶対手ぇ離さないで!!」
私、ちゃんと真選組の輪の中にいるなって。幸せに思う。
それからしばらくして、すっかり土方さんが諦めた頃。
「沖田隊長!!」
座り込んで休憩していた私達の元へ、今度は山崎さんが駆け寄ってきた。
「テロですよ!テロ!」
「あ?」
「テロ~!?」
沖田君に話しかけているというのに、つい反応してしまう。こういう時の沖田君はとても冷静だ。
「誰でィ、そんなダサいことしてる輩は。」
「今調査中です!」
「目的は。」
「おそらく、うちかと。」
「「うち?」」
「真選組に恨みがあると叫んでいるそうで…とにかく今は出動準備してください!」
矢継ぎ早に伝え、「お願いしますよ!」と念押しして山崎さんは駆けて行った。
「真選組に恨みって…何だろうね。」
「なんでもいいけど面倒くせェー…。」
沖田君が溜め息を吐きながら立ち上がる。
面倒くさいと言いながらも、こういう時はサボったりしない。
「俺の昼寝タイムを奪ったこと、後悔させてやりまさァ。」
歩いて行こうとした沖田君に、
「…っあ、あの、沖田君。」
呼び止めて、聞いた。
「私も………行って…いいと思う?」
「…。」
…実のところ、これまで私が関わってきた事件は市中見廻りの延長線上にあるものだけだ。
当然と言えば当然の話でもある。
隊に属さない私には直属の上司がいない。身柄を預かる上司がいなければ、統率が取れず作戦の邪魔になる。だから行けない。一緒に行きたいのに…いつも行けない。
「私も……行きたいな。」
皆の背中を見送るのは、もう飽きた。
必ず役に立ってみせる。だから……っ、
「俺はいいと思いやすがね。」
沖田君がアゴで私をさした。いや、私の……後ろ?
「どうなんですかィ、土方さん。」
「!」
振り返ると、土方さんが煙草を咥えて立っていた。
「あっ、…。」
「…。」
「…、」
『一緒に行きたいです』
『ちゃんと役に立ってみせますから』
あの日のような図々しい程の熱意で言えばいいのに、こういう時に限って声にならない。
もし……もし今否定されたら、やはり私を認めていないことになる。いくら容疑者を検挙して手柄を立てても、大事な時に使えるほどの実力はないと思われていることになる。
それをまざまざと突きつけられるのは……怖い。
「紅涙。」
「っは、はい!」
土方さんが煙を吐いた。
「…遅れたら置いていくからな。」
「っ…!」
土方さんが背を向ける。私はその背に、
「ありがとうございますッ!!」
これが、私が真選組に入隊して初めて立つ大事件となる。
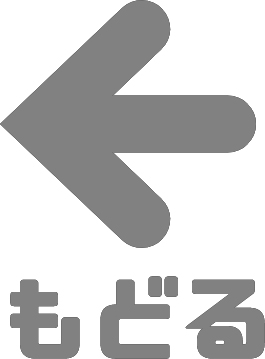 |
 |
 |
