腰間の秋水
「…何だ、これ。」
刀を抱き締めていた。刀は間違いなく俺の刀、村麻紗。
「刀を抱いて眠ってたのか?…気持ち悪ィ。」
こんなことは初めてだ。相当疲れていたのか、はたまた仕事の夢でも見ていたのか。
俺は自嘲し、畳の上へ刀を置いた。
「というか、どこだよ…ここは。」
目を覚ました場所が屯所じゃない。見覚えはあるような気もするが、思い出せない。
布団を出て、窓際へ歩み寄った。が、布団を出た時点で今度は妙な寒けに襲われる。見れば、
「はァ~っ!?たく…何なんだよ、服も着てねェじゃねーか。」
裸だ。日頃から裸で寝る習慣はない。
「…なんなんだ?」
襲われたか?
…なんて、一瞬でも考えた自分を鼻先で笑う。怪我もなくて全裸。何かクスリでも盛られない限り、起きてぶち倒す自信がある。
「気味悪ィな…。」
壁に掛けてある隊服を見た。あのスカーフの吊し方は俺だ。…だが上着がない。
「……?」
辺りを見る。上着はないが、布団の傍に脱ぎ散らかした浴衣があった。おそらく俺が着ていたのだろう、男物の浴衣と、
「女物の…?」
もう一着の浴衣。
…おいおいおいおい。女を連れ込んだってのか?
「…とにかく、服だ。」
布団から出て、隊服を着た。上着は後で探すとして、ズボンのポケットから携帯を取り出す。
18時。着信はない。
仮に女を連れ込んでいたとしたら、俺は昼間から女を…?
「……ないだろ。」
俺に限ってそれはない。…自分で言うのも何だが。
溜め息を吐きながら窓を開けた。
「ああ…ここだったのか。」
真選組で世話になっている旅館だ。ちょうど駐車場も見える。…警察車両が一台、止まってるけど。
「…マジか。」
アレは俺が乗ってきたアレか。
…本当にクスリでも盛られたんじゃねーか?もしくは催眠術か。そうでもないとこんなことしない。そのわりに身体の不調は感じねェが。
「不調どころか、むしろ何か特別な……」
特別なものを手に入れたような満足感がある。…不思議だ。何も分からないのに。夢を見た名残だとするなら、あまりに余韻が強い。
「…とりあえず戻らねェとな。」
気になる点はいくつもあるが、ここで考えても解決しそうにない。俺自身に害もないようだし、ひとまず部屋を出ることにした。
「あら、土方はん。」
廊下を歩いていると、女将に声を掛けられた。
「もう帰りはるの?」
「…おう、世話に…なったみてェだな。」
「泊まって行きはったらええのに。あの子はまだ部屋に?」
「あの子?」
…誰のことだ。
「ほら、なんやったかなぁ…。自己紹介してくれはったんやけど、ど忘れしてしもうたわ。」
口元を隠し、くすくすと笑う。
やっぱり俺は女を連れ込んでいたのか…。それも女将に対面させている。
「そいつ、どんなヤツだった?」
「……え?」
目を丸くする。
…そうだよな、自分が一緒にいた女を尋ねるなんて不自然すぎる。
「…実は、あの女に逃げられちまってよ。」
「ええ!?まさかそんな…」
「起きたらいなくなってたんだ。捜してェんだが、手掛かりも少なくて。」
「何も言わんと出て行くような子には見えへんかったけどねぇ…、なんか事情あったんやない?」
「……どうだろうな。」
「せやけど残念やわぁ…。あんなに『好き好き~』いう目してはったのに、お互い。」
「…お互い?」
「あの子もせやったけど、土方はんもだいぶ惚れてはったやろ?」
「……、」
なんだ、この感じ…。女将の話で何か…思い出しそうな……。
「うちで分かったことあったら連絡しますよってに、あまり気ぃ落とさんよう。」
「お、おう。」
「そしたらちょっと待っといてくださいね。すぐに持って来させますわ。」
…何をだ?
女将が従業員に声を掛ける。パタパタと走り、取りに行った物を女将に渡した。
「ちゃんと泥は落ちましたえ。」
そう言って俺に差し出す。隊服の上着と、深緑色の着流しだった。どちらも…俺の物。
「これ…、…なんで、」
「嫌やわぁ、とぼけて。まぁ今は思い出すんも…ちょっと辛いかもしれまへんけど。」
「……、」
なんで…、……なんでなんだ?何がどうなってる?
「落ち込んだらあきまへんで!」
女将がバシッと俺の背中を叩く。俺は礼を言って、旅館を後にした。
「わけ…わかんねェ……、」
一緒にいた女というのも、なぜか持ってきていた深緑の着流しも、警察車両のシートが砂だらけなことも。
「…まさか屯所に帰ってもこんな感じか?」
面倒くせェな…。と、思ってはいたのだが。
「おお!お帰り、トシ。」
「えらく遅ェお帰りで。」
屯所の中は大して変わらなかった。
「…ただいま。」
近藤さんはいつも通りだし、総悟は相変わらず生意気。旅館の時みたいに、謎の女の話は出てこない。
「一人で警察車両乗り回してどこ行ってたんですかィ?」
「わかんねェ。」
「…はい?」
「俺にも分かんねェんだよ。何してたか。」
溜め息を吐きながら、副長室へ向かう。
「…なァ総悟。俺に変わったところはなかったか?」
「今。」
「……。」
「ナウでさァ。」
「…お前に聞いた俺が馬鹿だった。」
「とうとうイカれちまいやしたね、土方さん。」
「もういい。疲れんだよ、俺は。」
総悟をあしらい、部屋に入る。刀掛けに刀を置き、煙草に火をつけた。
「忘れた方がいいのか…?」
仕事に支障はなさそうだ。もし明日以降に問題が出たら、真剣に考えればいいか…。
「はァ~…ったく、妙なこともあるもんだな。」
結局、女の話は旅館の中だけだった。
それ以来一度も話題に上がらないし、尋ねてもこない。だったら忘れてもいいと判断した俺の脳は、女のことを徐々に頭の隅へ追いやっていった。
江戸の治安を護るために刀を握る日々が続く。
「今日も頼むぜ、村麻紗。」
どんな戦場も、愛刀を右手に。
「副長!俺達が先に出るんで、副長は後から…」
「馬鹿にすんじゃねーよ。先頭には俺が立つ。お前らは後ろに続け。」
「でもっ」
「心配すんな、こいつがありゃ俺は無敵だ。」
心からそう思う。
刀を握っていれば安心する。満たされる。だから率先して、刀を振れるような任務についた。
俺が朽ちる時は、この刀を握っていたい―――
これほどまで愛着を持った刀は、初めてだった。
そんな日を繰り返していたある日。
―――ガキンッ…
「!」
とうとう刃こぼれした。よく持った方かもしれない。
「どうしやす?鍛冶屋へ出しやすか。」
そうだな。このままじゃ使い物にならねェ。…だが、
「…いや、もういい。」
直さない。
「気に入ってたんじゃなかったんですかィ?」
「今も気に入ってる。…だから触らせたくねェんだよ。」
「…はい?」
「誰にも、触らせたくねェ。」
この刀だけは、誰にも。
「…さすがは妖刀。やられちまいやしたね。」
「なんとでも言え。」
やれやれといった様子で総悟が立ち去る。
俺は刃こぼれした箇所を指でなぞった。もはや切れない。
「直してほしいか?村麻紗。」
一人呟き、フッと笑う。
刃こぼれした村麻紗は刀掛けの飾りとなった。
だが毎日のように使っていた刀は、使わなければ腐るのも早い。いくら手入れしても、何度となく血を吸ってきた村麻紗は特段サビの回りが早かった。
このままだと刀としての形を留めておくのも難しいかもしれない。
「すまねェな…、村麻紗。」
お前には世話になったのに、こんな形で終わらせちまって。
「俺の最期には、お前も一緒に連れて行くからよ。」
責任とって、俺がお前を成仏させてやる。
「土方さん、飯ですぜ~。」
「今行く。」
障子の向こうで聞こえた声に応える。村麻紗を刀掛けに戻し、部屋を出た。
飯を食った後も書類整理に追われ、また今夜も眠るのは深夜になる。そうして数時間後には、もう日が昇るのだ。
「ん…、」
薄らと目を開く。障子の向こうはまだ暗く、時計の針は四時をさしていた。
「もう朝か…。」
身体が重い。昨夜の疲れが残っている。
「…今日は二度寝しよう。」
あと一時間だけ眠る。そうしたら疲れもマシになっているような気がする。掛け布団を鼻先まで持ってきて、目を閉じた。
「…はぁ……」
そうこれだ。この落ちる感じ、やっぱサイコー。
右に寝返りを打つ。何の気なしに、薄らと目を開けた。
「……、」
その視線の先に、思わず目を見開く。
「…おい、」
これは…、…この、姿は……。
「っ、」
頭よりも先に、心臓が反応した。
ドクドクと血を巡らせる鼓動が、俺の身体までもを小刻みに揺らす。そんな俺を見ながら、
「…土方様、」
そいつが小さな声で俺を呼ぶ。
「覚えて…ますか?私のこと。」
発する言葉の一音一音に、息を呑んだ。
張り裂けちまいそうな胸と、走馬灯のように頭の中に溢れ出る記憶が、今、ようやく俺の目の前に映る。
「刀のお役目が終わりましたので…参りました。」
薄地の黒い布を羽織り、寒そうな素肌を透けさせて、そいつは…その女は不安げに俺を見る。
どうするかなんて、何も考えなかった。
「っ、」
掛け布団を引き剥がし、女の手を掴む。力任せに自分の元へと引っ張った。
「っ、土方様!?」
「っ…」
身体に埋め込んじまいそうなくらい、強く抱き締める。そして、女の首筋に顔をうずめ、
「…おかえり、紅涙。」
その名を呼んだ。
曇りない声が、俺に答える。
「はい、…ただいまです!」
(ようかんのしゅうすい)
→とぎすまされて曇りのない、腰にさした刀
2019.12.11加筆修正 にいどめせつな
 |
 |
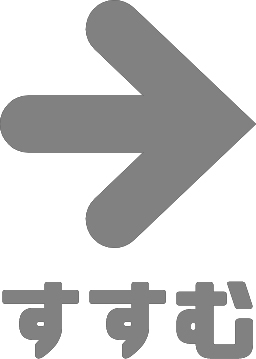 |
