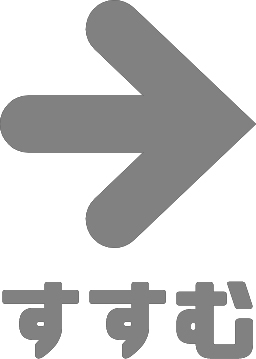おかえり
「まさか、今日戻ることになるなんて…」
この一ヶ月、あんな想いで過ごした時間が嘘のよう。
「今過去に戻れたら…教えたい。」
『心配しなくていい、全部うまくいく』って、安心させたい。
それくらい、異動日が決まった日から…つらい日々だった。
「早く来い。」
私は荷物から手土産を取り出し、土方さんと共に副長室に向かった。
「土方さん、」
部屋へ入る前、
「預かっていた手土産、先に近藤さんに返してきます。」
土方さんに声をかける。
土方さんは私の手元を見て、首を左右に振った。
「あとでいい。」
「でも」
「どうせ食堂に置く。数も少ねェし、こっちで食っちまえばいい。」
「っで、でも…」
「それより手伝ってほしいことがある。」
手伝って…ほしいこと?
副長室の襖を閉めた。
振り返ると、土方さんが押し入れに手を伸ばしている。
「缶、覚えてるか?」
「カン…?」
「四角いブリキの缶だ。前に見せただろ?お前への手紙とか、そういうのをガサッと入れてたやつ。」
「!」
あ、あれは…
「先月辺りから探してるんだが、どうにも見つからなくてな。持ち運ぶわけねェし、失くすはずなんてないはずなんだが…なぜか見つからねェ。」
その原因は…私だ。私が持っている。
土方さんが二度目に搬送された時、こっそり部屋に入って…
『…預かっておきますね』
必要以上に私を思い出させないように、そして薩摩で心の支えにするために、部屋から勝手に持ち出した。今は…私の荷物の中にある。
…なんてことはとても言い出せない。
「ど…どうして必要なんです…?」
「中のメモを見たい。」
「メモ…」
「何かある度に書き留めてたメモだ。紅涙がここにいない4年を知れるように。」
土方さん…
「記憶も戻ったし、それ見ながら話したかったんだが…どこにやっちまったんだ。」
「…、」
……言い出せない。私が持っているとはやはり言い出しづらい!
「お…お気持ちだけで…充分ですよ。」
「あァ?んなこと」
「それより覚えてるんですね、この数ヶ月のこと。」
「そりゃ……まァな。」
溜め息を吐き、土方さんが腰を下ろした。
私は内心、少し話をそらせたことに安堵する。
「忘れちまいたいことまで覚えてる。」
「そんなことが?」
「あっただろ。いろいろ…酷ェこと。…お前に。」
「そのようなことは―――」
思い返す。
自分でも信じられないくらい、明るい出来事が思い浮かばなかった。
「…仕方ありませんよ、状況が状況でしたし。私のことだけ忘れちゃったんですから…」
「…、」
「っあ、いえ、すみません!責めるつもりじゃないんです。ただ純粋に…気になってるから……」
「それについては分かったような気がしてる。」
「えっ?」
「紅涙のことを思い出した時、他にも思い出したことがあったんだ。まァ…今思い返したら覚えてるってだけで、それ自体をいつ思い出してたかは定かじゃねェが。」
それは、土方さんが重傷を負った任務の日の記憶だった。
新人隊士を庇い、斬られた直後から途切れていた記憶が、今は頭の中で繋がっているらしい。
「その記憶と私に関係が?」
「おそらくな。負傷して後、すげェ耳鳴りがしてた。その時に昔のことを色々思い出してて…今思えば走馬灯ってやつだったのかもしれない。」
土方さんの生死は紙一重のものだったと近藤さんが言っていた。本当に走馬灯だったかもしれない。
「そう悪いもんでもなかったんだが…紅涙のことだけが酷くて。」
「酷い…?」
「あの日の…別れた日のことしか思い出せなかった。紅涙の泣き顔と、俺の後悔と…色々、嫌なもんばっかりだ。もっと他にもあるっつーのに、俺の頭はなぜかそれしか吐き出さなかった。」
土方さんが小さく笑う。
「土方さん…。」
「おそらくこれが『始まりの記憶』に当たるんだろうよ。」
『人間というのは不思議なもので、忘れた記憶だけを思い出すことはそう出来ないものです。忘れることになった始まりの記憶を思い出さなければ、そこに含まれる記憶にも手が届かない』
「駅前の桜と紅涙の光景は、俺に記憶のフタの開け方を思い出させた。…そういうことだと思う。」
「なるほど…」
「つまり俺が紅涙を想ったせいで、紅涙のことだけが飛んじまったってわけだ。…悪かった。」
「っあ、謝らないでください!その…安心、しました。」
「安心?」
「土方さんの中で私の存在が薄くなっていたから忘れたのかと…そう思っていたので。」
「…フッ、そりゃ真逆だったな。」
土方さんの手が、私の頬に触れる。
「この4年、お前のことを考えなかった日なんてなかった。」
「土方さん…、」
「…おかえり、紅涙。」
触れたその手に私は両手を添え、
「はい、…ただいま、戻りました…っ。」
額に優しい口付けが落ちる。
目を開けると、今にも吸い込まれそうな瞳と見つめ合った。必然のように距離が近付いた時、
現実が呼び戻す。
思わず土方さんの胸を押した。
「どうした?」
「…あ…、…の…話、」
「?」
「………栗子さんの話…聞かせてください。…なぜ、真選組を辞めたのか。」
「あァ?このタイミングでかよ。」
「っ、場合によっては…こんなこと……しちゃダメなので。」
「?…まァいいが。」
気怠く溜め息を吐き、土方さんが座り直す。
机の上に置いてあった灰皿を引き寄せて煙草に火をつけた。
「事の始まりは、俺が倒れて搬送された日だ。病室で栗子と二人になった時。」
おそらく私は、その時間を少し知っている。
病室の前で聞いていた、あの時間のことだと思う。
「その時、俺は栗子に全部話した。紅涙の記憶だけ失くしてること、思い出そうとすると頭が痛ェこと。」
「えっ…そうだったんですか?」
「ああ。婚約の話もあったし、隠したままってのは気持ち悪ィから。」
「っ…そ、その……婚約の…話は…?」
「?」
「どんなことがあって…そういう話に?」
「……そこは知らなくていい。」
「っどうして、」
「つまんねェから。」
「…。」
「……はァ。…ったく、」
黙り込む私に、大きな溜め息を吐いた。
「いつもの天秤だ。真選組の安泰か、それ以外か。記憶が飛んでる時の俺は真選組のことしか頭にねェもんだから、当面の安泰を手に入れるために、とっつァんの話に乗った。」
「…、」
「聞いたのはお前だぞ。そんな顔すんな。」
「……すみません。」
土方さんの考え方が…悲しい。
いつも自分の身を真選組に捧げすぎているように思う。
そうすることが自身の幸せだと言われたら…それまでだけど。
「…じゃあ、今朝は栗子さんと婚約で…?」
「本気で言ってんのか?」
ハッと笑い捨てる。
「ねェよ。潰れた。」
「!?つ、潰れたって…」
「栗子が潰した。」
「栗子さんがっ!?」
「アイツが呆れたんだ、俺の価値観に。」
煙草を咥え、煙を吐き出す。
『栗子は呆れました!そういう話なら、どうして閉じ込めてでも引き留めないのですかっ!』