彼なりの+最後の温もり
そのことを自室にやって来た栗子さんに話していると、
「そんなに早くに行ってしまわれるのですか!?」
また目をうるませた。
大きな瞳に溜めた涙は、まるで宝石のように光り輝く。
「ご迷惑をおかけします。」
苦笑して頭を下げると、すぐさま「やめてください!」と私の肩を掴んだ。
「栗子はまだ…、…、」
「…?」
「…っ諦めませぬ!」
自身の前でギュッと握り拳を作る。
「紅涙さんのおかげで、栗子は強くなることが出来ました。だから…っ、だからちゃんと言ってみせまする!」
「何を…」
『出逢った頃から、どこか入り込めない雰囲気にも寂しさを感じておりました。ゆえに今、お伝えしたいのです』
『諦めないという気持ちを』
ああ…、
「…はい、」
土方さんの話。
「頑張ってください。」
「…紅涙さん!」
勢いそのままに呼ばれる。
「紅涙さんはなぜ―――」
そこへ、
『…ちょっといいか。』
声が割り込んだ。
この声…
「マヨ…副長様でございまするね。」
「…、」
二人で襖の向こうを見る。
久しぶりに聞いた声音に、胸が少し高鳴っていた。どちらかというと、緊張に近いけど。
「どうぞ。」
上擦りそうな声で言う。
「…邪魔して悪ィな。」
どことなく気まずそうな土方さんが顔を出した。
「早雨に…手伝ってもらいてェ仕事がある。」
「私に…ですか?」
「ああ。」
「…、」
「忙しいのか。」
「いえ、そういうわけではありませんけど…」
もう私にしか出来ない業務はないはず。
土方さんが声を掛けてくるのは、栗子さんの手がいっぱいの時だと思っていた。まだ引き継げていないものがあったのなら問題だ。
「わかりました、副長室に向かいます。」
「…頼む。」
「では栗子は部屋へ戻っておきまする!」
勢いよく立ち上がった。その背を、
「待ってください、」
呼び止める。
「栗子さんも一緒に来ていただいた方が良いかと。」
「どうしてでございまするか?」
「私がいなくなってしまうと、出来る人がいなくなりますので。隣で見て覚えていただければ助かります。」
「必要ない。」
土方さんが遮った。
「栗子が覚えるような仕事じゃねェよ。」
「で、でも」
「栗子はいらねェ。」
「……わかりました。」
そこまで言うのなら、そういう仕事なのだろう。…よく分からないけど。
「では失礼いたしまするね。」
栗子さんが頭を下げた。
土方さんの横を通り過ぎる直前、
「栗子、あとで話がある。」
声を掛けられている。
栗子さんは土方さんをほんの少し黙り見た後、「承知しました」と部屋を出て行った。
「…では副長室に。」
「ああ。」
部屋へ入るなり、
「それをやってくれ。」
普段栗子さんが使っている机に、ドンと紙の束が置かれた。内容を見る。
「…?」
いつもの書類だ。
誤字を確認したり、判をついたり、提出先に出す準備をする作業。
さらに紙をめくる。二枚目も、三枚目も同じような書類が続いていた。
「…土方さん、」
「あァ?」
土方さんは自分の机に向かい、こちらに背を向けたまま返事する。
「この書類で…合ってますか?」
「合ってる。」
「そう…ですか。」
ならば、いつか特殊な作業が出てくるのだろう。ひとまず書類整理を始めることにした。
そうしてしばらく経った後、
「…土方さん。」
作業が終わる。
「なんだ。」
「…、」
私は終えた資料を整えながら、土方さんの背を見た。
「…これ、栗子さんも出来ます。」
やり終えたものの、特殊な作業はなかった。
どうして私を呼び出したのか分からない。さすがにこの内容が栗子さんに出来ないとは思ってないだろう。
「まだあるようなら、栗子さんに代わりますね。」
立ち上がろうとする私に、
「なんでだよ。」
土方さんが振り返った。
「誰がやってもいいだろ。」
「でも…栗子さんの仕事ですので、私がするのは…」
「副長補佐の仕事だ。栗子に限った話じゃねェ。」
「それは…そう…ですけど…。」
栗子さんの立場として、自分が取り組んでいる範囲の仕事に触られるのは…気分が良くないかもしれない。
「付き合えよ。」
「……え?」
「もう一緒に仕事する機会なんてないかもしれねェんだから。まだ付き合え。」
「…、」
一緒に…仕事するために私を……
「……、」
「嫌なのか。」
「っ、そんなことありません!…いっぱいします、仕事。」
「そりゃ助かる。」
フッと鼻先で笑って、
「飽きるほどあるからな。」
自分の横に積み上げた書類をトントンと叩いた。
確かに、いつもの気持ちで取り組んでいたなら飽きたと思う。
でも今日は特別に思う。
大した会話もないし、ろくに休憩も取らない。
昼食すら忘れて、机に向かった。
この場所から離れたくなかった。一秒でも長く、ここで仕事をしていたかった。永遠に続けばいいとさえ思えるほどに。
けれど、集中して作業すれば、
「…すげェな。」
「どうしました?」
「あれだけあった書類、全部終わっちまった。」
「!」
しなければならない作業も、なくなってしまう。普段では想像できないくらい早く終えてしまった。
「これで終いだ。」
手渡された最後の書類を受け取る。
「…薩摩に行く日は決まったか?」
受け取った書類を机に置き、私は頷いた。
「末日付けという話になりました。なので、25日には発とうと思います。」
「もう来週か…早ェな。」
「…そうですね…。」
「…。」
「……ありがとう、ございました。」
「あァ?」
「こうして副長補佐として働くことが出来たこと…心から感謝しています。」
あまり話すと、また症状を誘うかもしれない。
気をつけながら…言葉を選んだ。
「迷惑を掛けることも多々ありましたが、長い間…本当にありがとうございました。」
「…やめろ、そんな言い方。」
土方さんが呟く。
「まだ仕事は終わってねェんだ。…礼なんて早ェよ。」
不貞腐れたような顔つきで煙草を取り出す。
まだ火のついていない一本を口に咥え、
「……お前は、…、」
「?」
「…、」
火をつけた。
深刻な顔つきで、ゆっくりと視線を上げる。
「…どういう…意味ですか?」
「ああ…悪ィ。これは仕事とは別の話だ。」
「え…」
「お前にとっちゃ嫌な話だろうが、薩摩へ行く前に聞いておきたい。本当に…俺のことが好きだったのか?」
「……違いますよ。」
今も、好きです。
「違う…のか?」
「はい。…、」
ここからいなくなる私の気持ちなど、知らなくていい。
「私達は、よく周りから冷やかされていたんです。だから…流されてしまって。」
いつかまた会いに来た時、『一緒に仕事したよな』と、かすれた記憶で昔話する程度で充分。だから、
「そう…だったのか?」
「そうです。だからもう気に留めないでください。」
この機に、おしまい。
「……、」
土方さんは煙草を吸って、目を閉じた。
潔く答えた私の言葉を飲み込んでいるんだと思う。驚きながらも、これが真実だったのかって噛み砕きながら。
「腑に落ちねェ。」
パチッと目を開けた。
「ならこれは何だ…?」
自身の胸元を握る。
「この痛みは…何だって言うんだよ。」
『痛み』…?まさか、
「っ痛いんですか!?」
「うずいて仕方ねェ。早雨といると…いつも痛くなる。」
「きゅっ、救急車を!」
慌てて立ち上がろうとした私の腕を、
「落ち着け。」
土方さんが掴んで止める。
「そういうんじゃない。」
「でもッ」
「ガキじゃねェんだ、痛みの違いくらい分かる。これは……アレだ。早雨を……、…そういう…、……。」
言いづらそうにして、視線をさ迷わせる。
私はさぞ怪訝な顔をしていただろう。土方さんは諦めたように溜め息を吐いてから、
「…俗に言う、……『胸きゅん』てヤツだ。」
そう言った。
「胸…きゅん?」
「…おう。」
「…、」
瞬きを数回して、
「っ…ああ!」
ようやく告げられていることに気付く。
「…い…今の……胸の痛みが…胸きゅん?」
「今だけじゃねェ。ずっと前から。」
「前から…」
まさか、これまでの胸の痛みは…全部これ?
「頭は…?」
「頭?」
「頭は痛くありませんか?」
「痛くねェけど。」
「…、」
頭痛は、記憶喪失から来る痛み。
でも胸の痛みは…私を…想ってのこと……だったの…?
「…つまりアレだ。」
土方さんが煙草を揉み消す。
「俺の片想いだったってわけだな。」
「…どうして…そんな話に?」
「紅涙は流されてただけにも関わらず、俺は記憶を失ってまで胸を痛めてる。どっちが重いかなんて、考えなくても分かるだろ。」
「…、」
嬉しい。嬉しいのに…やっぱり苦しい。
「俺を好きになる予定はないか?」
「……ありません。」
「はっきり言いやがって。」
鼻先で笑った。
「俺をこんな邪険に扱うのはお前くらいだな。」
「邪険だなんてそんな…」
「いいんだよ、それで。…お前だけで。」
笑みを描く唇で煙草を吸い、
「最後の書類、頼んだぞ。」
書類は、ほんの数分の作業で終わる。
「出来ました。」
終えた書類を手渡し、「以上ですか?」と聞いた。そばにあった書類の山は、見事に消えている。
「これで以上だ。」
「では失礼します。」
立ち上がる。
土方さんも立ち上がり、
「お疲れさん。」
おもむろに右手を差し出してきた。
「…お疲れ様でした。」
私も手を差し出し、握手する。
仕事納めの握手。どことなく気恥ずかしい。思えば、土方さんと握手をしたのは初めてかもしれない。握手する機会なんてそうないし……
「今までお世話になり――」
―――グイッ…!
「っ!?」
唐突に握っていた手を引かれる。
まるでいつかの再現のように、私は土方さんの胸へ倒れ込んだ。
「っ、土方さん!?」
身体をよじったその時、
「……世話になったな。」
「!」
耳元に聞こえたのは、
「ありがとよ、…早雨。」
しっとり滲む寂しさと、
「薩摩まで気をつけてな。」
別れの言葉だった。
それは、もう会わないことを示している。
私が薩摩へ発つまで。…薩摩へ発つ日すら、見送らないことを意味している。
「はい…、…お元気で…っ。」
途端に込み上げた寂しさが、視界を悪くした。
「ありがとうございました…っ。」
私は、残酷なほど優しい体温に涙した。
 |
 |
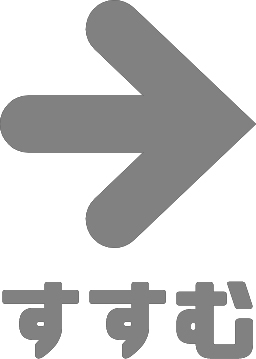 |
