江戸にて
紅涙に告げた後、水溜まりから発する光は俺の目を突き刺した。
「くっ…、」
瞬間、視界も頭の中も真っ白。耳鳴りまでする。目を開けているのか閉じているのかすら分からなくなって、ひどく辛い。…なのに、
「っ…?……こ、こは…」
パッと視界が開けた途端、苦痛は嘘のように消え去った。まるで夢から覚めるみたいに。しかも、
「なんで…ここに……」
なぜか自室じゃない場所にいる。
「……食堂、か?」
屯所の食堂だ。不思議なことに、いつもと大体同じ場所に座っている。
「……?」
窓から差し込む白い光。周囲のガヤガヤカチャカチャする騒がしさを見ると、朝食の時間帯…なのだろう。
「どういうことだ…?」
俺はさっきまで紅涙といて、別れた時は夜だったはず……
「どっ、どわァァ!?副長ォォっ、何でェェェ!?」
「…あァ?」
うるさい声に眉をひそめる。
「っせェぞ、山崎!」
声がした方を睨みつけた。すると山崎は思いのほかすぐ傍に立っていて、
「……、」
なぜか頭からマヨネーズをかぶっている。
「何やってんだ、お前。」
「それコッチのセリフゥゥ~!」
「?」
「副長、手。」
向かいの席に座っていた原田が俺の手元を指した。辿り見れば、自分の右手にマヨネーズがある。
「副長が山崎にかけたんすよ。」
「…俺が?」
山崎にマヨネーズを?
原田が言うには…
いつも通り白飯にマヨネーズを掛けようとしていた俺が、何を間違えたか上向きに持ったまま握り締めたそうだ。そのまま無表情で力一杯握り締められたマヨネーズは、急激な圧力が加わって噴水の如く上空へ昇り、滝の如く山崎の頭に降り注いだのだとか。
「俺が…そんなことを?」
「ええ。なんかブツブツ言ってんな~と思ってたら、急に。で、あんな感じに…。」
「……、」
原田と二人で山崎を見る。山崎は「酸っぱ臭いっ!」と言いながら必死にマヨネーズを拭っていた。
…失礼なやつだ。いやその前に。
「俺がやるわけねェだろうが。」
全く記憶にない。
「マヨネーズだぞ?そんな勿体ない使い方をするわけがねェ。」
「いやいや、それでも副長っすから。俺見てましたし、何より実際にそれ。」
原田が俺の手を指す。確かに俺の手にはマヨネーズが握られていて、なんだったら手にマヨネーズが垂れている。
本気で俺がしたってのか…?
「…山崎、」
「は、はい。」
「そのマヨネーズ、勿体ねェから全部舐めろよ。」
「ええ!?かっ、勘弁してくださいよォォ!」
一体何がどうなってんだ…?こっちの世界に戻るのはてっきり夜で、自室に戻れると思ってたんだが…。
俺が知らぬ間に食堂まで歩いてきたのか?
「……、」
とりあえず、一旦部屋へ戻ろう。
「…あれ?副長どこ行くんすか。」
「部屋に戻る。」
「全然食ってないじゃないっすか!」
「食欲なくなった。」
席を立ち、トレーを返す。
残した飯を見て女中の心配を受けたが、大丈夫だと笑っておいた。
「…はァ。」
わけが分からない。紅涙と別れたばかりだというのに、余韻に浸る間もなかった。
「あの言葉をゆっくり考えたかったってのによ…。」
『言っておけば、良かったな…っ』
気になる言葉を残しやがって。最後に残す言葉じゃねェだろ…。
「紅涙…、」
「お?トシ、飯は済んだのか。」
局長室の前を通りがかった時、近藤さんに声を掛けられた。中には総悟も座っている。
「終わったなら始めやしょうぜ。」
「始める?何をだ。」
「何って…」
「トシから言い出したことだろ?局中法度を見直すって。」
はァ?
「言ってねーよ、そんなこと。」
「勘弁してくだせェ。昨日の今日ですぜ?」
昨日?
「昨日は俺、ここにいなかったはずだろ。」
「あーらら。あの目は本気ですぜ。どうしやすか、近藤さん。」
「…疲れてるのか?」
「疲れてなんて――」
…いや、疲れてるのか?…違うよな。俺は昨日、紅涙と過ごしていた。あの変な世界で紅涙といたんだ。
「俺は……、…。」
「その様子じゃ局中法度の見直しなんて到底出来そうにありやせんね。お開きってことでいいんですかィ?」
呆れ口調で総悟が言う。
「朝礼の時からボーっとしてるとは思ってやしたが、日付の感覚まで失くしちまって。タルンタルンに弛んでまさァ、うちの副長は。」
おかしいのは…俺なのか?
「…大通りの、」
「なんだ?トシ。」
「俺が総悟と大通りの事故処理をしたのは、一昨日だったよな?」
「そうですぜ。」
「その後の俺は…」
「屯所に帰って書類整理、だったろ?」
覚えてるよな?と、近藤さんが表情で問いかける。
…悪い、近藤さん。
「それ、俺じゃねーわ。」
「はァ!?」
「ト、トシ…?」
「俺は昨日、別の次元にいたんだ。この街と別の街を半分ずつくっつけたような場所で――」
「ままま待ってくれ!何の話を…している?」
「だから昨日の俺がいた場所だって。そこで向こうの世界の女と…一日一緒にいたんだ。」
「向こうの世界の…女?」
「ああ。」
あの世界を分かってもらおうとは思わない。俺だってコイツらが理解できるように話せる自信はねェ。だが、ここにいたのは俺じゃないってことは伝えておきたい。
「じゃ、じゃあ俺達が一緒に過ごしたトシは誰だと言うんだ?」
「わからねェ。けど……」
可能性として、思いつくヤツがいる。
「…天人じゃねェかと思う。向こうでも俺と瓜二つの天人を見た。」
「天人…。」
「昔、似たような件がありやしたね。」
「あの時とは少し違うがな。っつっても俺自身、何が起きてたかよく分かってねェから仮説でしかねェが…。」
俺がこの世界から抜けている間に出来た穴を、天人の俺が埋めていた。空白の時間を作らないために、都合よく。
何のためにこんな流れが出来ているのか、
本来は目に見えない世の常を俺が見ちまっただけなのかは知らねェが、簡単に入れ替われちまうということは…俺と紅涙が過ごしたあの場所も、この世界『銀魂』と同じ次元にあるのかもしれねェ。架空の…都合よく創られた世界。
「で?土方さんは、いつその世界から戻ってきたって言うんですかィ。」
「さっきだ。気付いたら食堂に座ってた。」
「「……。」」
二人が口を閉じる。近藤さんは心配そうに眉間を寄せた。
「トシ、お前…」
「まァ待ってくだせェ、近藤さん。」
シレッとした顔で総悟が制止する。
「土方さん。早い話、アンタはその女に惚れちまったってことで?」
「…そんなことはどうでもいいだろ。」
「図星ですかィ。わかりやしたぜ、こうなった原因。」
「なに!?」
コイツ、この程度の話で全貌を理解したというのか!?
「最近、刀を変えたんじゃありやせんか?」
刀?
「俺がか?」
「そう。土方さんが。」
「…いや?変えてねェけど。」
「なら打ち直したとか。」
「してねェ。」
「…ありゃ。」
「なんなんだよ。」
「いやね、前にそんな夢を見たことがありやして。」
「「夢?」」
「『自分の刀が女に化けた』とか言って、土方さんがのぼせ上がっちまう夢。で、どんどんガリガリになって死に近付いていくって夢でさァ。」
ニタニタと笑みを浮かべながら総悟が話す。
コイツ…夢の中でも俺を殺そうとしてんのか。
「正夢になったのかと思ったんですが、違いやしたか。」
「違うな。どさくさに紛れてとんでもねェこと言ってんじゃねェよ。」
「トシは疲れてるんだろ。今日は一日休むといい。」
「あ、それ夢の中の近藤さんも言ってやしたぜ。」
「お前は黙ってろ。…あと近藤さん、俺は疲れてるわけじゃねェから。まァ部屋には戻って考え直してみるよ。」
話を切り上げようと軽く片手を上げ、背を向けた。しかし、
「待て。」
近藤さんの声に阻まれる。
「今日くらい休め。な?トシ。」
「いいって言ってんだろ?」
「単なる休暇だ。お前の話を信じてないわけじゃない。」
「……。」
…仕方ねェな。
「わァったよ。」
とは言って部屋へ戻ったものの、
「はァ~……、」
休暇を貰ったところでやることなんてない。普段の休暇ですら仕事で潰すくらいなのに。
「とりあえず書類でも片付け……ん?」
俺の机の横に何かが落ちている。灰色の…なんだあれ。服?
「…あ。」
広げて、思わず頬が緩んだ。
「…なんだよ、やっぱり夢じゃなかったんじゃねーか。」
紅涙に借りたパーカーだ。
いつ脱いだか覚えてねェが、ちゃんと残っていた。
…良かった。これくらいしか、あの世界を留めておけるものは残ってねェから。
「……大事にしねェとな。」
このままだと忘れていく一方だ。いずれ紅涙のことまで忘れちまう日が来るのだろう。日常のゴタゴタに埋もれて、少しずつ記憶が上書きされていって…。
「忘れたくねェな…。」
隊服の上着を脱ぎ、パーカーに腕を通した。あの時と同じ格好をしても、あの世界へ行けるわけじゃないが。
「紅涙……、」
お前は今、どうしてる?自分の世界へ戻った時点で忘れちまったか?それとももう…二度と会えない俺のことなど……
「二度と会えない…か。」
溜め息が漏れる。懐に手を入れた。
「チッ…、ここは向こうのままかよ。」
煙草がない。買いに行かねェと。
だがその前に着替えよう。休みの俺が隊服で動き回るわけにはいかない。着流しに着替える…が、
「…これはまだいいだろ。」
パーカーは脱がない。上から着流しを羽織った。妙な格好になったが…まァよしとして、俺は『大江戸マート』へ向かった。
『大江戸マート』は紅涙と出逢ったコンビニだ。元から俺の世界にあるコンビニ。…なのに、
「なんつーか……、」
頭が混乱する。あの世界にもあったせいで、紅涙までここにいるんじゃないかと勘違いしてしまう。
「…来ねェかな。」
あの時みたいに、店の前で煙草吸ってたら。ふらっと歩いてくるんじゃねェか?……なんて。
「バカバカしい。…ん?」
コンビニの端の方で誰かが座り込んでいる。赤髪の…子どもか?
「おい、どうし……」
顔を上げたそいつを見て、
「なんだ、お前か。」
溜め息が出た。坂田のとこのチャイナ娘だ。
「何してんだよ、こんなところで。」
「関係ないネ。」
フンッと顔を背ける。
この生意気さ、総悟とそっくりなんだよな…。
「オマエこそコンビニに何用アルか。サボりか?サボりなのか三白眼。」
「三白眼やめろ。久しぶりに言われたわ。…俺は煙草だ。」
「煙草なら自販機でも買えるアル。」
「……。」
何も知らねェくせに痛いとこを突いてきやがる。
…そうだよ、煙草ならその辺の自販機でも買えんだよ。それでも俺はここのコンビニで買いたかったんだ。コンビニに来たかったからな!
「…カートンで買うためだ。」
「ふーん。」
自分から聞いておきながら、この興味のない返事…。これだからガキは苦手だ。
「…なんでもいいが、変なヤツに付いて行くなよ?最近多いんだからな。」
「大丈夫アル。私、強いネ。ショタコンがハァハァ言いながら声掛けてきたら、神楽神拳を繰り出せばいいだけアル。」
そうだった…コイツは夜兎。いらねェ心配だったな。
「まァこんなとこで長居なんてせずに家へ戻れよ。じゃあ…」
な、と言おうとしたところで、チャイナ娘が傍に置いていたピンク色の小瓶を手に持った。そこに黄緑色の棒…いや、ストローのような物を突っ込む。
何だったっけな…それ。
「何見てるアルか。」
「いや……」
どこかで見たことがあるような…。昔…そう、すげェ昔に…どこかの庭先で……
「じっと見られてたらキモいネ。」
「…お前、言葉遣いに気を付けねェとマジでいつか痛い目見んぞ。」
チャイナ娘は俺の話を聞き流し、黄緑色のストローに口をつけた。途端、いくつものしゃぼん玉が吹き出される。…ああそうだ、しゃぼん玉だ。
「なかなか懐かしいもん持ってんじゃねーか。」
「懐かしくないネ。ナウでヤングな流行りヨ。」
「いつの言葉使ってんだよ…。つーかコンビニの店先で吹くな。やるならテメェの家でしろ。」
「家の中でしたら銀ちゃんに叱られたアル。」
部屋の中で吹くヤツがあるか…。アイツも大変だな。
「とにかく店先はダメだ。営業妨害で訴えられるぞ。」
「訴えられた時に立ち退けばいいネ。」
「タチの悪い輩みてェなこと言うな!ほらっ、さっさと退け!」
「うるさいアル!」
言うや否や、チャイナ娘が俺に向かってしゃぼん玉を吹きかけてきやがった。
「っわ、ぷっ、」
大量のしゃぼん玉に襲われる。手で払うが、いくつものしゃぼん玉が顔に当たって割れた。
「…おいコラ、ガキ――」
『十四郎、』
「!」
不意に、義兄の声が聞こえた。いや正確には鮮明に頭の中で再生された。
『十四郎、しゃぼん玉はいくつ飛んでいるんだい?』
目の悪い義理の兄は、よく縁側に座ってしゃぼん玉を飛ばし、それを俺に数えさせていた。
『八…あ、七つ…、っあ五つ!五つ飛んでるよ、兄さん』
途中で割れちまうもんだから、数えるのに苦労して。
『残った五つはどんな色をしてる?』
『んー…緑とか青とか色々。皿を洗ってる時みてェな色かな』
『ははっ、そうか。私には分からないけど、五つはどれも違う色をしてるんじゃないか?』
『してるしてる!虹色みたいだったり混ざってたり、なんかモワモワしてんだ。色が動いてるみたいな、ずっと同じ色じゃねェの!』
『それはな、光の干渉によってそう見えているんだよ。十四郎が吹いたしゃぼん玉は毎度、さらには一瞬一瞬で色が変わっているんだ』
…そういえば、しゃぼん玉の色も光の干渉だな。
『じゃあ同じしゃぼん玉は作れないってこと?』
『そうだよ。今お前が見ているその輝きは、二度と再現することが出来ない。言わば奇跡の塊だ』
あの頃は分からなかった義兄の言い回しも…
『まるでしゃぼん玉の一つ一つが人生のようだろう?』
今なら分かる。
「紅涙…、」
やっぱり俺は…お前にまた逢いてェ。
「紅涙って誰アルか。」
「!?」
思い出に溺れる頭が、コンビニ前の退屈な江戸に引き戻された。
…忘れていた。コイツの前だった。
「女アルか?女の名前アルか?」
「…そうだ。」
「どこの女ネ。」
「…この街じゃない。」
「ここじゃないなら、どこアル。」
「分かんねェよ。分かってたら…とっくに逢いに行ってる。」
「恋人アルか?」
「……違う。」
たぶん…違う。
「死んだアルか。」
「死んでない。…つーかお前!アルアルうっせェんだよ!」
「死んでないならまた会えばいいだけの話ネ。」
「!」
チャイナ娘は深く考えずにそう言ったんだろう。だが俺は、
「生きてるなら、必ずまた会えるアル。」
雷に打たれたくらいの衝撃だった。
思えば簡単な話だ。会いたいなら、会えるようにすりゃいい。絶対に会えないとは言いきれないんだから。
「…そうだよな。」
会いたい、…いや、会う。会ってやる。
二度と会えないなんて誰にも分からねェ。言いきれるもんじゃねェ。やってみなけりゃ分からねェじゃねーか。
「これ、やるヨロシ。」
唐突にチャイナ娘がしゃぼん液を差し出してきた。
「吹けば気分も上がるアル。」
…なんだ、コイツなりに気遣ってくれてんのか?優しいところもあるんだな。
「フッ、いらねーよ。お前のだろ?」
「あげるアル。吹くヨロシ。」
「いらねェって。お前が楽しめば――」
「私は飽きたからもういらないネ。」
「結局その程度かよ!」
ったく、何なんだ。……ん?
「おい待て。やっぱりそれ、俺が貰ってやる。」
「…イイ大人が天邪鬼なんて引くアル。」
「うっせェ。寄こせ。」
ピンク色の小瓶を受け取った。
「それじゃナ。」
「待て。」
「まだ何か用アルか。」
「ちょっと協力してくれねェか?」
「協力?」
「しゃぼん玉を大量に作りたい。」
紅涙の世界に溢れ出しちまうくらい、大量のしゃぼん玉を。
「…私、アホに付き合う暇はないネ。」
「思いっきり暇してただろうが!…いいからちょっとだけ付き合ってくれ。これが……俺の好きな女に会う方法かもしれねェんだ。」
「やっぱりアホになったアル。」
「…好きに思え。とにかく俺は大量のしゃぼん玉が欲しい。お前の人並み外れた肺活量があれば、短時間でそこそこの量が作れる。」
あの日、本当に俺の世界の物が紅涙の世界へ流れ出たのかは分からねェけど…、
「力を貸してくれ。」
やるだけの価値はあると思う。
「…はァァ~。…酢昆布1ダース。」
チャイナ娘が人差し指を見せた。俺はそれを鼻先で笑う。
「1ダースでも1箱でも買ってやるよ。」
「フォ~ウ!!なら1箱ネ!1箱買うヨロシ!」
「わかったわかった。」
安いものだ。これで紅涙に会えるのなら。…まァ一度したくらいじゃ会えねェだろうが、何度でも飛ばしゃいい。今後の戦力は酢昆布でいくらでも釣れる。
「ちょっと待ってろ。先にコンビニでしゃぼん液を買ってくる。」
「はい隊長ッ!」
俺は早々としゃぼん液を買い占めに行った。買ってきた物はコンビニの隅で開封し、付属のストロー全てに液を付ける。そしてチャイナ娘に「吹けるだけ咥えろ」と手渡した。
「ふぉえふぁへんはいへ。(これが限界ネ)」
「…よ、よくやった。」
口いっぱいに咥えたが、コイツ…吹けんのか?
俺は残った数本のストローを口に咥えた。
「いいか?とにかく短時間で大量に作ってくれ。一度吹き終わったら、すぐに液体を付けて吹き直す。可能な限り途切れさせたくない。」
「ふぁはへうふぉおふぃ。(任せるヨロシ)」
「優しく吹けよ?しゃぼん玉として飛ばなきゃ意味がねェからな。…よし、始めるぞ。」
スっと息を吸い、俺達は一斉に…
「「ふ~……」」
しゃぼん玉を吹いた。直後、大量のしゃぼん玉が舞う。どれも光の干渉で虹色に輝いていた。
これは…いける!
手応えを感じた。しゃぼん玉は風に乗り、コンビニ前や道路の方へと四方八方に飛ぶ。もはや今の俺の頭に『営業妨害』という言葉は微塵もない。
「よし、次!」
「はい隊長ォォッ!」
拭き終えてはストローをしゃぼん液に浸し、再び吹き出す。
この状況を俺の知り合いが見たら、確実にバカにするだろうな。特に総悟。アイツは絶対、面白おかしく尾ひれを付けて触れ回るに決まってる。
…だとしても仕方ない。また紅涙に会えるまでは、しゃぼん玉を吹き続けるしかねェんだから。
「…紅涙……」
届いてくれ。また会いたいと思ってるのは、俺だけじゃないはず、…だろう?
「……、…信じてるぞ。」
俺は出来る限り、流れていく全てのしゃぼん玉を視界に入れた。紅涙がどれを見てもいいように。僅かな可能性も逃したくはない。
「ぐっぐるじいアル…!」
「頑張れ、チャイナ娘!」
絶え間なく全力で吹き続けているチャイナ娘の顔は真っ赤になっていた。しかしおかげで大量のしゃぼん玉が風に乗り、流れている。今も太陽を受け、どのしゃぼん玉も光の干渉で輝き……
「っ、あれは…!?」
一つだけ、輝きが違う。見つめるほどにギラギラした、強い輝き。…この感じ、
「まさか…、っ、」
期待に息を呑んだ。突き刺す眩しさに耐えかね、まばたきする。直後、
「……。」
願いは、叶っていた。
「マジ…か……?」
呟く。だがその声はまだ誰の耳にも届いていなかった。
幻か?…いや違う。きっと違う。そう信じたい。
未だこちらに背を向けるその後ろ姿を、俺は視界から消さぬよう必死に見つめ続けた。瞬きしても消えちまいそうで、息すら上手く出来ない。
「…紅涙?」
そっと名前を呼んでみる。
振り返ってくれ。声が届く現実であってくれ…そう願いながら。
「……紅涙、…なのか?」
俺の問いかけに小さく肩を揺らす。そして、
「土方…さん……っ。」
振り返った。
…そうだ。その声が、また聞きたかったんだ。
紅涙を抱き締めた時、自分の手が少し震えていることに気付いた。
情けねェ…。まだ離れて間もないというのに。これまで死を覚悟して生きてきた俺が、紅涙と会えたくらいでこのザマか。
「会いたかった…っ!」
ああ…、
「俺も…会いたかった。」
『十四郎、』
『今お前が見ているその輝きは、二度と再現することが出来ない。言わば奇跡の塊だ』
絶対のない存在、しゃぼん玉。
『まるでしゃぼん玉の一つ一つが人生のようだろう?』
不確かな偶然が繋いだ、紅涙。
「お前は俺のしゃぼん玉だ、紅涙。」
~side.土方~
せっかく再会したというのに、紅涙は今後も元の世界へ戻ると言った。この世界の決まりを考えたら…当然のことだろう。だがそうなると、会う方法はきっちり決めておかなければならない。
例えば、しゃぼん液の濃度。
ひとことに市販の液と言っても、俺の世界の物とは違うはずだ。
…うん?なら、しゃぼん液じゃない方がいいのか。この辺りも考えた方が良さそうだ。ああ面倒くさい。だが紅涙の意思は尊重してやりたい。たとえどれだけ面倒な作業であっても、またあんな悲しい別れをしないためにきっちり決めておかねェと……、…あ。
「…そう言えば紅涙、あの時も何か言おうとしてたよな。」
「あの時…?」
「俺達が自分の世界へ戻る時。別れ際に言ってただろ?『言っておけば良かったな』って。」
「!?だ、だからそれを……、…次の機会に。」
「あァ!?」
「すみません!」
紅涙は焦った様子で目を泳がせ、
「…聞こえてたんですね。」
ボソッと言う。
「聞こえてたし気になってた。…何だったんだよ。」
「だ、だからあれは…そのー……」
「何だ?」
「うっ…、……、」
「?」
そこまでの隠し事か?
あんな切羽詰まった状況じゃないと言えねェような秘密…ってことなのか?
「そ、の、……っ、」
紅涙は散々目を泳がせた挙句、俺をチラりと見て息を吸った。
「っ、土方さんが…っ、…っ…好きです!」
…『好き?』
「そう…言いたかったなと……思ってたんです、あの時。」
「……、」
…なんだ、
「そんなことかよ。」
「そっ、そんなこと!?」
「紅涙、声デカい。気をつけろ。」
「うぐっ、…すみません。」
くくっ、素直なやつ。
あんな別れ方したんだから、同じ想いだってことくらい容易に想像はついていた。…ま、ちゃんと言ってないと公言できねェってのはあるが。
「紅涙、」
俺は、想い合うには不確か過ぎるこの世界にお前を繋ぎ続けるためなら、どんなことでもするつもりだ。いや、してみせる。
「なんですか?」
そしていつか、共に過ごせる方法を見つけ出す。必ずだ。
二人一緒に年を重ねる、そんな何でもない当たり前の未来を手に入れるために。
「俺も、お前が好きだよ。」
「はぅっ!!」
必ず出来るはずだ。偶然を壊し、奇跡を生み出した俺達なら。
…だからとりあえずその日までは、
「これからもよろしくな。」
2020.03.15加筆修正 にいどめせつな
 |
 |
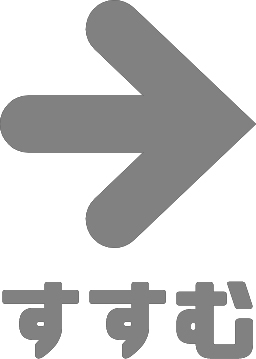 |
