私には、付き合って二ヶ月の彼氏がいる。
「あ、う、っ紅涙!」
「!」
照れ屋で恥ずかしがり屋の、嘘ひとつ吐けない真っ直ぐな人。それが、私の彼氏。
「そそその…今日はおっ…俺の家に…っ」
家へ誘ってくれるのは初めてじゃないのに、真っ赤な顔をして私を誘う。…愛しい人。
「うん、お邪魔します!幸村くん。」
「っうむ!」
ちゃんと私のことが好きだって分かる。ちゃんと、大切に想ってくれてるのが分かる。
「幸村くん、」
「なんであろう。」
「大好きだよ。」
「っ!?」
彼が好き。
「おおお俺はっ、紅涙よりも好きだ!大好きだ!」
「ふふっ、声が大きいよ。」
「もっ申し訳ござらん!」
…でも、
「うるせェ野郎だな。」
「!」
私には秘密がある。
「……土方、」
「よォ、紅涙。…と、犬。」
「…俺は犬ではござらぬが。」
「フンッ、犬だろ。ここがどこか分かってんのか?校内のロッカーだぞ、校内の。」
「…。」
幸村くんには言ってないことがある。
「こんなとこで朝っぱらからサカりやがって。犬以外の何者でもねェよ。」
…幸村くんは、知らない。
「お前もな、紅涙。」
「……。」

「…私達に何か用?」
不機嫌に問うと土方が笑った。
「コイツと話してる時とは随分違うな。」
「…用がないなら声かけないで。」
顔を背け、幸村くんの手を引いた。
「行こう。」
「よいのか?」
「うん。」
「…おいコラ、待てよ。」
「!」
土方が私の腕を掴む。すぐさまその手を振り払った。
「触らないで。」
「…。」
私がこんな態度を取る理由。
それは……土方が私をもてあそんだから。
まだ幸村くんと付き合う前の話。
私と土方は、よく一緒にいる仲だった。その頃はまだ単純に友人の一人として。
土方の素行は当時から悪かった。それでも今と変わらずモテてて、隣にいる子はいつも違うし、そういう子が同時に何人もいたりした。
「…ねぇ、そんな付き合い方は良くないんじゃない?本当に好きな子とだけ付き合いなよ。」
「マジメか、紅涙。」
「マジメとかそういう話じゃなくて、人として――」
「ならお前だ。」
「…え?」
「お前がいい、紅涙。」
真っ直ぐ私を見て、
「紅涙といたい。」
その声を私の耳に焼き付ける。
「な…によ……、…変な冗談やめて。」
「冗談じゃねーし。」
「…、」
「……。」
あの眼を見ると、いつも思考が止まった。それでも、戸惑いの中に小さな喜びが湧いたのも事実。
「…急に…そんなこと……言われても。」
「本気か?俺と一緒にいるのは同じ気持ちだからだと思ってた。」
「ちっ…違うよ!友達だから一緒にいただけ!」
「じゃあこれからは?」
「これからは…、……。」
「嫌なのかよ。」
「っ嫌じゃ……ないけど。」
「じゃあ決まりな。今からお前の彼氏は俺、お前は俺の彼女。」
「……、…うん。」
そんな始まり方をした私達の時間は、そこそこ濃いものになった。一緒にいるだけで互いを想い合ってるのがよく分かる。けど……
「何あれ…、」
そう思っていたのは、私だけだった。土方はやっぱり私だけの彼氏じゃない。平気な顔をして…他の女の子と腕を組んで歩く人。
「もう飽きたってこと…?」
結局私も、私が見ていた女の子達と同じだった。その他大勢の一人で、特別でも何でもない。
「…土方、話がある。」
「なんだよ。今日の放課後なら迎えに――」
「別れたいの。」
「はァ?何言ってんだ。」
「私は……、…っ、私は、ダメなの。そういう…他の子達みたいには……付き合えない。」
浮気も、女友達にしては親密すぎる友人関係にも…目をつむれない。
「……、」
「私と別れて。」
「…よく分かんねェけど、俺はお前が――」
「聞きたくない。」
「…お前が好きだっつってんだよ、紅涙。」
「喋らないで。」
「……、」
あの日と変わらない眼。真っ直ぐ私を見る眼。
…だとしても、惑わされない。今の私みたいな子を、私はたくさん見てきたから。
「…さようなら。」
…だけど、この話は幸村くんも知っている。
わだかまりは、その後に起きたこと。おそらく一生言えない…罪なこと。
「…こいつを返そうと思って待ってたんだよ。」
不機嫌な私に、土方がノートを突き出した。隣に立つ幸村くんが不思議そうな顔をする。
『いつの間に貸した?不仲でもノートは貸すのか?』
そう思ってるのかもしれない。いっそ聞いてくれればいい。そうしたら、『これはまだ付き合ってた頃に貸してたノートだよ』って言うから。『今はもう必要ですらないノートなんだよ』って。
「…ロッカーに戻してて。」
背を向けた。けれど土方が「無理」と即答する。
「お前のロッカー、どこか知らねェし。」
「……、」
仕方ない。
浅い溜め息を吐いて向き直った。すると、
「二十七番だ。」
幸村くんが私の前に立った。
「二十七番が紅涙のロッカーである。」
「…。」
「聞こえておらぬのか?ロッカーは奥から二列目の一番上。であったな?紅涙。」
「う…うん。」
凛々しい振る舞いに少し驚いた。おそらく、土方も。
「……。」
「いかがした、土方殿。そなたが戻せぬなら俺が預かるが。」
幸村くんが手を差し出す。その手を見て、土方はわずらわしそうに溜め息を吐いた。
「テメェと話してねェんだよ。」
「それはすまなんだ。しかし紅涙が困っているように見えたゆえ。」
「……あっそ。」
フイッと背を向け、土方は二十七番のロッカーへ向かった。が、歩いて数歩のところで立ち止まる。
「つーか、場所が分かっても開けられねェわ。」
振り返り、私の目を見て手を出した。
「鍵。」
ああ……、…。
「……わかった。」
足を踏み出した。けれど、
「待て紅涙、」
幸村くんが私の手を掴む。
「俺が渡そう。」
「幸村くん……、」
「俺に鍵を。」
「…ううん、大丈夫。」
「しかし」
「平気だから。」
心配してくれる幸村くんに微笑んだ。そこへ、
―――キーンコーンカーンコーン…
予鈴が鳴る。
「先に行ってて、幸村くん。」
「そっそれはならぬ!こんな輩と紅涙を二人きりになど」
「…こんな輩で悪かったな。」
「ありがとう、幸村くん。私も用が終わったらすぐ行くよ。」
「だがっ、」
「大丈夫。」
「くっ……、…承知した。」
手が離れる。土方の方を見た幸村くんは、険しく眉を寄せて立ち去った。その背中に、
「スゲェしつけされてる犬。」
土方が鼻先で笑う。私はそれを横目で睨み、ロッカーの鍵を開けた。
「もう返ってこないと思ってたノート、タイミング良くわざわざ返しに来てくれてありがとう。」
「……。」
「返して。」
手を出す。
「……。」
「早く。」
「…。」
土方がノートを差し出した…ように見えたけど、私が受け取る前にパッと手を放した。当然、ノートは地面に落ちる。
「ちょっと、何やって…」
―――バンッ!!
「ッ!?」
大きな音と共に、土方の顔が間近に迫った。視界の端に映る傍のロッカーは少しへこんでいる。
「…何のつもり?」
「お前……、」
鋭く光る瞳に、突き刺されるような錯覚。
「…お前、本気であんなのが好きなのか?」
何を言うのかと思えば。
「そうよ、大好き。」
「…。」
「それが何?短気で暴力的で、女にだらしない男より何百倍も魅力的。」
土方を睨みつけた。
一体どういうつもりで言ってるの?こんなことを聞いて何になる?いつまでも私が自分の手元にあると思わないで。なんでも自分の思い通りになると思わないで!
「…どいて。」
「…。」
「……もういい。」
土方を押しのけようと手を伸ばした。するとそれを阻むように、
「なっ、」
身体を押しつけてきた。顔を背けることすら出来ない近距離に、息が詰まる。
「っや、」
「俺よりアイツの方がいいって?」
「っ、」
辛うじて視線をそらした。頬に土方の吐息が触れる。
「離れてよ!」
「…なァ、紅涙。言っちまっていいか?あのこと。」
「!?」
私の耳元で囁く。
「言ったらどうなるんだろうな…アイツ。」
一度は想い合った仲だけど…今は、
「俺とお前がヤってること、言ってみようぜ。」
ただの、最低な男。
「っ離れて!」
突き飛ばそうと胸を押した。けれど土方の身体は軽く揺れる程度で動かない。
「…お前は何も分かってない。」
手首を掴まれ、
「っ、ん」
唇を押し付けられた。
「やめっ、っ…」
顔を背けても逃がさないよう顎を持ち直される。声を上げようとすれば舌が割り込んできた。
「っぁ、っ、ふっ、」
せめて視線で訴えようと、閉じていた目を開く。舌でも噛み切ってやろうか。そう考えたけど、
「……っ、」
土方の表情を見て、動揺した。
なんて顔…してるの?どうしてそんな…そんな苦しげな顔を?まるで…私が土方を傷つけてるみたいな……
「は、ぁっ…」
「……。」
土方が名残惜そうに唇を離す。自分の口を雑に拭い、私を見た。
「気付け、紅涙。」
「はぁ…っ、はァ…、」
「頭で分かんねェんなら身体で気付け。」
「っ、何言って…」
「俺とアイツの違い。分かんだろ。」
足が…崩れそう。こんなところ、誰かに見られたら大変なことになる。早く、…離れたいのに。
「っ…あっち行けバカ。」
手の甲で口を押さえ、土方を睨みつけた。
「…バカはお前だろ、バカ。」
落ちたままになっていたノートを拾い上げ、私に差し出した。
「お前を守ってやれるのは俺しかいねェんだよ。」
「…、」
「じゃあな。」
片手をヒラりと上げ、去って行った。
「……違う。」
私には幸村くんがいる。今はもう土方じゃない。土方なんて知らない。好きじゃない。…なのに、
「……、」
私と土方は、あの時確かに別れた。
…でも、その話には続きがある。私達は……別れた後にも関係が続いていた。
『さよなら』と言ったのに、土方は今と大差ない迫り方で変わらず私を『好きだ』と言い続けた。他の女の子の影があるのに、私を見る眼も囁く声も、何も変わらず迫ってきた。だから…流された。
結局、私も他の子達と同じになった。
しかもその関係は幸村君と付き合い出した頃にも一度だけあって……
『俺とお前がヤってること、言ってみようぜ』
あの言葉に繋がる。
…断ちきれなかった私が悪い。流された私が悪い。
関係を持った後、すごく後悔した。これでは土方と同類。そういうところが嫌で別れたのに、まさか自分が同じことをするなんて……
奈落の底へ落ちるような気持ちになって、私はようやく、土方との関係を絶った。
元々別れたはずの関係。どちらかが無視すればそれで終われる。会話を一切せず、廊下ですれ違っても目を合わせない。そうすれば数日後、土方はもう違う女の子と歩いていた。
「……。」
…そう思っていたのに、なぜかまたこうして私にかまい出した。
……どういうつもり?
女の子が途切れて暇になった?だとしても、わざわざ私にかまわなくても困らないはず。
「…。」
…わからない。わからないけど、巻き込まないでほしい。
「……か。」
私にはもう関わらないでほしい。私には…私にはもう……
「…た、……ぶか…、…。」
幸村くんが、いるのだから。
「紅涙、」
「っ!」
肩を揺すられ、ハッとした。幸村くんが心配そうに顔を覗き込んでいる。
「大丈夫か…?」
「あ…ゆ、幸村…くん、…、」
「やはりロッカーで何かあったのではないのか?朝からずっと浮かない顔をしている。」
「…ううん、大丈夫。ごめん。」
…そうだ、今はお昼休み。中庭で幸村くんとお弁当を食べようとしてたんだ。今朝のことなんて…もう忘れなきゃ…。
「…紅涙?」
「っ、…食べよっか!」
「…うむ。」
幸村くんは何か言いたげな顔をしつつも、自分の弁当箱に手を伸ばした。食べ盛りらしい大きな弁当は、いつもビックリするくらい豪華な作りになっている。
「今日も佐助さんがお弁当を?」
「左様!…おおっ、今日はカニであるか。」
赤いウィンナーで出来たカニを指で摘む。細やかに目や口まで付けてあった。
「すごいね~。私も欲しいなぁ、佐助さん。」
「なっ、…さっ佐助などより……、…。」
「うん?」
「っおお俺が…おりますゆえ、」
「幸村くん…、」
「…いつでも頼ってくだされ。微力やもしれぬが、紅涙のためならば全力で戦う所存!」
「ふふっ、…うん。ありがとう、頼りにしてる。」
「うむっ!」
満面の笑みで頷き、
「ではいただこう!」
パチンッと手を合わせた。
「「いただきます」!」
食べ始めようとしたその時、
「ぬアァァァッ!」
突如、幸村くんが叫ぶ。
「どっどうしたの!?」
「ない!!」
「『ない』!?」
何が!?
「箸がござらん!!」
「あ~…」
「これでは食えぬではないか!くっ、…おのれっ佐助!!」
ドンッと地面に拳を打ち付けた。
「落ち着いて、幸村くん。心配ないよ、私はお箸あるし。」
「?」
「ほら、こうやって…」
先程のカニさんウィンナーを箸で摘む。
「食べさせてあげられるでしょ?」
「!!!?ぬぁっ…」
ぬぁ?
「なりませぬ!」
「え?なんで……」
「左様に破廉恥なことっ、っまだ早すぎまするゥゥゥッ!!」
耳まで真っ赤にして猛ダッシュで駆けて行く。
「…どこ行っちゃったんだろ。」
そう思っていると、校舎の中から声が聞こえてきた。
「先生ェェ!!箸を一つ頂けないだろうかァァ!」
「ぅおい真田ァァ!テメェいつもうるせェんだよォォ!!」
「申し訳ござらんゥゥゥ!!」
「それがうるせェって言ってんでしょうがァァ!」
「坂田先生!真田君!二人とも静かにしなさい!」
「……ふふっ、」
職員室から戻るまで待っていよう。
弁当箱にフタをした。もちろん幸村くんの弁当箱にも。
そこへ背後から足音が近付いてくる。…もう戻ってきた?
「早いね、幸村く――」
「まだ食ってねェのか。」
「……、」
土方だった。ポケットへ手を突っ込み、気怠そうにして歩み寄ってくる。…なんでまた来たのよ。
「…関係ないでしょ。」
「冷てェの。」
「…。」
どうして放っておいてくれないの?
心の中でたくさん文句を言いながら、弁当箱をカバンへしまう。幸村君の弁当箱も私のカバンに入れた。
「何してんだよ。」
土方が私の横にしゃがみ込んだ。私は身の回りの物を片付けながら返事する。
「あっちに行くの。」
顔は見ない。
「アイツのこと待ってんじゃねーのか?」
「待ってるよ。でも土方のいないところで待つ。」
「…なんだそれ。」
起伏のない声と溜め息が聞こえた。
「…お前、そんなに俺のことが嫌いになったのか。」
「……、」
『嫌いになったのか』
「それは…、…ちがう。」
「……。」
違う気がする。土方は最低な男だと思うし、もう好きじゃないけど…嫌いじゃない。…ただ、
「一緒に…いたくないだけ。」
「…。」
一緒にいると…また傷つくから。
「土方といても、…いいことなんてない。」
…もう傷つきたくないの。
「だから、傍に来ないで。」
私の前に現れないで。これ以上…土方のことを考えさせないで。
「……じゃあね。」
カバンを肩に掛けた。
「勝手に終わんなよ。」
腕を掴まれる。
「話はまだ終わってない。」
「…私は終わった。触らないで。」
振り払おうと腕を振る。けれど掴む力が強くて離れない。
「…やめてよ、放し――」
睨みつけるように視線合わせた。瞬間、脳裏に浮かぶ。
『マズい』
距離を取ろうとした時には、もう遅かった。
「っちょ…ッ」
土方の腕の中に閉じ込められる。
「っ土方!」
「…なんで分かんねェんだよ。」
「っ、」
ここはロッカーのような閉鎖的な場所じゃない。たくさんの生徒がいる。たくさんの目がある。朝とは違って、きっと今私達のことを見ている生徒は大勢いる。
「っ、やめて!」
なのに、引き離そうとしても離れない。それどころか腰に手を回され、ピタりと身体をくっつけられた。
「土方っ!」
「紅涙、俺はアイツからお前を――」
「紅涙!!」
「っ!?」
幸村くんの声がする。
「土方!貴様…っ、紅涙から離れろ!!」
「…もう戻ってきやがったか。」
…見られた。土方とこんなことしてるの…幸村くんに見られた。
「っ放して!」
「離さねェ。」
「なんでっ…」
「お前を守るためだ。」
「!?…何言って……」
「何のつもりだ。」
「…よう、幸村。」
「俺の声は聞こえておるのだな。ならばただちに紅涙から離れよ。それとも、」
パキッと音が鳴る。幸村くんの右手にあった割り箸が折れていた。
「俺が引き剥がしても良いと言うのなら、話は別であるが。」
「……おもしれェ。やってみろ。」
「っ土方!」
いい加減にして!
身体をよじり、土方の腕から抜け出した。
「待て紅涙!」
止める土方を無視して、幸村くんの元へ向かう。幸村くんが伸ばしてくれた手を掴もうとした時、
「そいつが俺と紅涙を別れさせたんだ!」
信じられないことを言った。
「……え?」
振り返る。そんな私の手を、幸村くんが掴んだ。
「幸村くん…、」
「心配ござらん。」
「…、」
「紅涙、そいつが俺達を別れさせたんだ。」
「なに…言ってるの?言っていい嘘と悪い嘘があるよ。」
「嘘じゃねェ。幸村は俺より酷い。純真でも無垢でもねェ、ただ本能のままに生きる獣だ。」
……なんで…、
「なんで…そんな風に言うの?」
なんで幸村くんを悪く言うの?
「自分の思い通りにならないからって…そんな言い方……」
「事実を言ってるだけだ。それを知った上で俺を嫌うなら…仕方ねェ話だが、お前は知らないだろ?」
「…。」
土方の言葉は信じられない。信じられないけど…嘘を言ってるようにも見えない。…また騙されているのかもしれないけど。
「…幸村くん、」
「何でござろう。」
「……あんなの、嘘だよね?」
信じないわけじゃない。ただ…否定してほしい。嘘をつかない幸村くんの口から、『そんなわけない』って言ってほしい。だから…聞かせて。
「土方が適当なことを言ってるだけだよね…?」
「…うむ。俺は二人を別れさせておらぬ。」
やっぱり…!
「別れろと命じたわけではないからな。」
「……え?」
「別れることにしたのは二人の話。紅涙の意思で別れたのであって、俺が別れさせたわけではない。そうであろう?」
え…、……え、
「ちょっと…待って。」
どういうこと…?
「そいつは…幸村は俺に女を付きまとわせて、紅涙と別れるよう仕向けたんだ。」
「!?ま、まさかそんな……、」
幸村くんを見る。幸村くんはニッコリ笑って、頷いた。
「否定は致さぬ。」
「っ…、……なん、で…」
「紅涙を助けたかったのだ。所詮あのような男だと気付かせてやりたかった。」
…幸村くんは、照れ屋で純新無垢な嘘ひとつ吐けない真っ直ぐな人……だと思ってた。
「おかしいと思わぬか、紅涙。あやつは俺が仕掛けたと気付いておきながら、今まで言わなかったのだぞ?満更でもないと楽しんでいた証拠ではないか。」
「バカ言え。わざと泳いでやってたんだ、お前の化けの皮を剥ぐためにな。」
「よくも左様な戯言を。」
「あいにく俺は、紅涙と付き合ってから他の女にゃ興味ないんでね。」
…それは違う。
「嘘、だよね土方。…見たよ?腕を組んで歩いてるの。」
「だとしたら、そいつは幸村が寄こした女だ。妙にくっついてきてピーピーよく喋る女だったから。」
「…、」
「紅涙がどんな光景を見て、どんな話を耳にしたか知らねェが、俺はあの時も今もずっと紅涙だけを想ってる。」
「土方…、」
「惑わされてはならぬぞ、紅涙。あやつの性根はそう簡単に変わるまい。」
「その言葉そっくりそのまま返してやるよ、幸村。」
「……。」
「…。」
『気付けよ、紅涙』
『お前を守るためだ』
土方はずっと、このことを伝えるために…私のために……動いてたの?
「紅涙、早くそんなヤツから離れろ。」
「……、」
「幸村は紅涙を手に入れるためならどんなことでもするぞ。必要とあらばお前の人間関係全て潰してまうだろうさ。」
「っそ、そんなこと……しないよね…?幸村くん。」
「無論、紅涙を悲しませたくはないからな。」
ホッと胸を撫で下ろす。
「だが、そうせざるを得ない時でも心配はない。」
「えっ…」
「友人などおらずとも俺がいる。寂しい思いなどさせぬと約束しよう。」
「っ…、」
「くくっ、気に入ったぜ幸村。テメェは相当歪んでる。」
「歪んでなどおらぬ。俺はただ紅涙と共にありたいだけだ。」
幸村くんが私の頬へ手を伸ばした。けれど反射的に、
「っ、」
その手から逃れてしまう。
「…紅涙?」
半歩下がった。同時に繋いでいた手も離れた。
「ごめん…なさい。…私、幸村君がしたこと…少し考えたい。」
「……、」
「終わりだな、幸村。」
土方の言葉に幸村くんが眉をひそめた。
「…紅涙、俺はもう紅涙の恋人ではおられぬのか?」
「……ごめん…、…幸村くん。」
「……わかり申した。」
傷ついた幸村くんを見るのはつらい。でも今回のことを『ありがとう』とは言えない。わざとそんな環境を作るなんて……やり過ぎだ。
「左様な顔はしないでくれ、紅涙。」
幸村くんが困ったような顔で笑った。
「俺はどんな時も紅涙に笑顔でいてほしい。たとえそれが……俺でない男の隣であっても。」
「幸村くん…、」
「だからもし悲しそうな顔をしていた時は、再びあいまみえ、俺が紅涙を救う。」
幸村くんは自信に満ちた眼差しで私にフッと笑い、
「いつか必ず振り向かせてみせましょうぞ。」
颯爽と去って行った。その背を見送る土方が「しつけェ男」と呟く。
「…土方、」
「ん?」
「どうして…何も言わずに別れたの?」
言えばよかったじゃん。私が別れるって言った時にこのことを言ってれば、こうならずに済んだかもしれない。
「それは……、…待て。場所を変える。」
「え…?」
「周りを見ろ。」
アゴで私の後ろをさした。
「わ…、」
予想通りと言うべきか、やはり多くの注目を浴びている。
「……うん。」
『隠れ階段』は校舎の端にある非常階段で、利便性が悪いこともあってあまり使われていない。…付き合っていた当時、二人でよくいた場所でもある。
「ここ久しぶりだな。」
「…来てなかったの?」
「こねェよ。使う用事もねェし。…お前は?」
「久しぶりだよ。」
「……そうか。」
小さく笑った土方が階段の壁に背を預けた。
「いい天気だな…。」
風に吹かれて、土方の前髪が優しく揺れる。気持ち良さそうに目を細めるこの顔を、また傍で見ることになるとは思ってなかった。
「…ねぇ、」
「ん?」
「どうして幸村君のこと、言わずに別れたの…?」
「…言っても信じねェと思ったんだ。俺が…ろくでもねェ男だから。まァ今となりゃ幸村よりマシだがな。」
肩をすくめ、鼻先で笑う。
「でも言うだけ言ってくれれば良かったのに。」
「いや、俺の話を信じられない紅涙に『幸村はヤバい』って話したとしても響かねェだろ?『だから俺と別れるな』って言いたいがために、必死にコジつけてるようにしか聞こえない。」
それは……
「そうなると余計幸村の方へ行っちまうと思った。」
…そうかも。
「アイツが歪んでることは置いといて、紅涙に心底惚れてることと、大事にしたいと思ってることは本当だった。だから……裏を取るまでなら丁度いいと思って距離を置くことにした。」
丁度いい…?
「アイツといる時は、お前も幸せそうだったしな。」
「『丁度いい』って、何に丁度よかったの?」
「…、」
「土方?」
「……あの時、…お前と付き合ってた時の俺は、いつか…紅涙を壊しちまうんじゃないかと思ってたんだ。」
「……え?」
壊す?
「閉じ込めておきたいくらい、お前に依存してた。俺だけのものでいてほしかった。だから…幸村の歪みにもいち早く気付いたのかもしれねェ。」
「土方…、」
「…悪い。聞こえが良いように言ってるが、つまりは俺も幸村と同類なんだ。それが分かった時、別れるのもありだと思った。距離を取って、自制すりゃ変わるもんもあるんじゃねーかって。」
そう…だったの?土方がそこまで私を想ってたなんて…。
「引くよな。まァアイツが反面教師になってくれたおかげで、だいぶ自制できるようになったから。」
「…引いてないよ、驚いただけ。土方は私のことなんて大して好きじゃないんだと思ってた。」
「バカ言うな。食っちまいてェくらい好きだったさ。」
「食べたかったの?」
「ああ。二の腕くらいからガブッとな。」
「ふふっ、いいよ?少しだけなら。」
「…あんまそういうこと言うなよ、閉じ込めたくなるじゃねーか。」
「ぷっ、あはは!全然変われてないじゃん。」
「俺の鍵はお前次第なんだ。だからこれからは言葉に責任持て。いいな?」
「何それ。…ふふっ。」
笑いながら土方を見れば、真剣な目とぶつかった。
「俺、本気で紅涙と付き合ってから女とかゼロだから。」
「ゼロは…嘘でしょ。」
「はァァ!?ゼロだゼロ!」
「ほんとに~?幸村くんが差し向けた子達以外の子もいたんじゃないの?会話が弾んだ流れで一緒に帰ったり、そのまま…」
「してない。そもそも俺が女と会話を弾ませるくらい喋る男だと思ってんか?ただでさえ片思いしてるヤツのことで頭いっぱいだったっつーのに。」
か、片思い…。
「…、」
「…なんだよ、信じたか?」
「……ちょっとだけ。」
「あァん!?……まァ仕方ねェか、一からやり直す。」
「やり直す?」
土方は手を伸ばし、
「紅涙、」
私の髪を優しく撫でた。
「好きだ。俺はお前がいい。」
「……、」
言葉なんていらない、気持ちは伝わる……なんて、不器用な私達には到底できそうもない。こうして言葉にして、優しく触れて、やっと想い合えていたことが実感できる。
「付き合ってくれ、紅涙。」
「それとこれとは話が別だ。」
「…。」
「フッ。好きだよ、好き。」
illust…くろだうらら様
novel…にいどめせつな
2021.05.05 novel加筆修正
 |
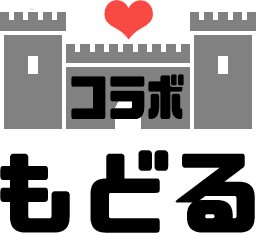 |
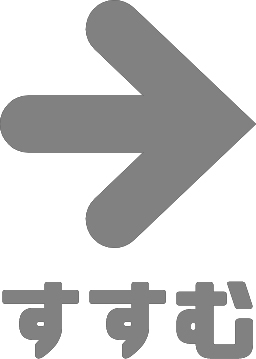 |
