不戦勝
―――バシッ
「った、」
頭を押さえる。叩いた当の本人、土方さんは私の手を引いて廊下を走る。反対の手にはケーキの箱も忘れず握られていた。
「あ、あれ…?」
「『あれ?』じゃねェ!隙を見て出ろっつったろ!?」
「そ、そうでしたけど…。」
すみません、全く隙が見つからなくて…。
「副長ォォ!早雨さ~ん!!」
「「?」」
走りながら振り返る。山崎さんだ。この機に乗じて逃げ出してきたらしい。手を振りながら嬉しそうに駆け寄ってきた。
「も~、置いてかないでくださいよ~。」
「お前は敵だろうが。」
「あっち行ってください!」
「えっひど!俺は敵じゃありませんよ!ただ沖田隊長には逆らえないっていう話で…」
「敵じゃねーか。」
―――ドンッ
土方さんが山崎さんを突き飛ばした。
「おわっ!?」
山崎さんは足を滑らせ、
「べぶッ!!」
顔面から廊下へ倒れこむ。
「や、山崎さん!?」
「行くぞ、早雨。」
「でも山崎さんがっ」
「待てやコルァァ!!」
「逃げんじゃねェェ!!」
「!」
「山崎は捨ておけ。バリケードになる。」
バ、バリケードって…。
「ふくちょ…、助け――」
「山崎、明日からの待遇が心配なら精一杯ここで食い止めろ。いいな?」
「えぇェェ!?」
「行くぞ、早雨!」
土方さんは私の手を引き、再び駆け出した。
「副長ォォォ~ッ!」
後ろでは山崎さんの絶叫が響いている。私達は振り返らず、廊下の角を曲がった。
「このまま俺の部屋に入る!」
「はい!」
先にある副長室へと駆け込む。
「はぁっはぁっ、」
きっちり障子を閉めると、土方さんは刀を立て掛けてストッパーにした。山崎さんの部屋で見た行動と同じ。
「ほんとに山蔭さんだったんですね…。」
「違う。あの山蔭が俺だ。」
私を見てフッと笑う。…いちいちカッコいいな、もう。
「さてと、」
土方さんは手に持っていたケーキを机の上へ置く、いや置こうとしてやめた。
「置く場所がねェな…。」
そう、置く場所がない。なんなら座る場所も狭いくらいだ。全ては土方さんへの誕生日プレゼントのせいで。
「すごい量のプレゼントですね…。」
ケーキっぽい箱から、手作りの雰囲気漂う包装の物、何かをケース買いしたのかダンボールのままで届けられている物まである。
「このダンボールの中身は何でしょう…?」
「マヨネーズだろ。それだけは毎年ありがてェんだ。」
「マヨネーズ…、」
マヨ…ネーズ……、
「あ!」
「ん?」
「っい、いえ…何も。」
誕生日プレゼント、私もマヨネーズ関連の物にすれば良かったァァー!分かりやすい好物がある人なのに、なんで忘れちゃったかな私!!
「仕方ない、ここでいいか。」
土方さんは畳の上にケーキの箱を置いた。
「早雨、フォークを探せ。」
「フォーク?」
「ここにあるプレゼントのどれかに付いてるだろ。」
ガサガサと探り始める。
そんな上手いことあるかな?フォーク付きの親切なプレゼントなんて……あ。
「あった!」
小さな箱に一本のフォークが付いている。
なんて気の利いたプレゼントなんだ…。
「よし、食うぞ。」
「え!?」
何言ってんだこの人は!
「食べてる場合ですか!?いつ襲撃してくるか分からないんですよ!?」
話しながらも振り返り、障子に気を配る。今にもぬっと人影が現れそうで落ち着かない。
「…そうか。知らねェんだな、お前は。」
「……何がですか?」
「フェーズ五のルールだ。俺が副長室に戻った時点で、この面倒事は終了する。」
……え?
「じゃ、じゃあ土方さんは今ここに戻ってきてるわけだから……」
「終わりだ。」
そう言い、伸びをした。
「今年も疲れたなー…。」
え、や、ほんとに?
「本当にもう終わりなんですか?」
「終わりだ。」
「でもまだ半日しか経ってませんよ?早くないですか?」
「終わりだっつってんだろ。それとも何か、お前はまだ鬼ごっこがしてェのか。」
「っまさか!即刻やめたいです!」
「なら終わらせろ。誰が何と言おうと、年に一回の悪夢は終了した。俺が戻ってきたんだからな。」
ふぁ、とあくびをする。珍しい。
「ったくよォ、誕生日ならもっと穏やかに暮らしてェっつーのに、毎年毎年…」
「アイドルみたいですね。」
「やめろ、恥ずかしい。」
土方さんは鼻先で笑い、フォークの包装を開けた。
「早雨、そこの窓を開けてくれ。」
「窓…?」
「部屋の匂いが変わっちまってる。」
うん、確かにこの部屋は色んな匂いがする。特に香水系。自分をアピールするためにプレゼントへ染み込ませあるのだろう。と言っても、大半は土方さんの煙草の匂いがするけれど。
「それじゃあ窓、開けますね。」
私は立ち上がり、壁際にある机近くの小窓を開けた。しかしその先の景色に、
「ひッ…!?」
思わず後ずさる。
「どうした?」
「あっあの…庭に……すごい状況がっ!」
なぜか物干し竿に隊士達が吊り下げられている。彼らは皆一様に、下着一枚。脱がされたズボンに腕と洗濯竿を通され、十字架を背負うかの如く吊り下げられている。
「ま、まさかこれが…」
「吊るし刑。捕まったヤツらは全員そうやって晒し者にされんだよ。」
こわっ!というかどうやって持ち上げてるの!?相当重いはずだよアレ…。
「すごい…ですね、何かと。」
「そうだな…アイツらはいつも未知数だ。」
やれやれと首を振る。
少し離れたところには、タスキ掛けをした年配の女性達が立っていた。見張り。中には屯所の女中もいる。どうやら今年も裏切られたらしい。
「…みんな大丈夫なんですか?」
「問題ない。怪我をしても、大抵は子どものケンカ程度だ。」
「あんなに血が飛び散っていたのに!?」
「あれは大半がケチャップ。アイツら、目潰しに使ってきやがんだよ。目に入ると相当痛ェらしい。」
「うわぁ…」
じゃあ至るところに付いてる『赤』はケチャップの赤だったのか…。
「でもなんか…みんなグッタリしてますよ。」
子どものケンカのわりに、誰も彼もがうつむき加減に目を閉じている。今年は酷かった…ってこと?
「そいつは羞恥心のせいだろうな。全員、現実逃避してんだろ。」
「ああ…。」
痛い…。肉体的にも精神的にも痛い刑だ…。
「近藤さんはいるか?」
「えっ…?こっ、近藤さん級の人にまでお構いなしですか!?」
「なしだ。アイツらは邪魔者を例外なく執行対象にする。」
な、なんと非道な…。あの中に近藤さんがいるかもしれないなんて、とても信じられな――
「…いました。」
いちゃいましたよ、近藤さん。身体が大きいから見つけやすい。
「そうか…。」
土方さんは溜め息を吐き、煙草に火をつけた。
「近藤さん……。」
本当に近藤さんも他の隊士と同じように吊り下げられている。しかし目を閉じている表情はどことなく違った。満たされているというか…なんとなく幸せそうに見える。
「嫌じゃなかった、のかな…?」
まさかね。単にそんな顔に見えるだけ?
「ああ?」
「あ、いえ。近藤さんの顔が妙に穏やかだなぁと思って。」
「…やっぱりか。」
やっぱり?
「今年は準備万端で挑んでたからな。満足してんだろ。」
「やるだけやった達成感ってことですか。」
「いや、……。」
「?」
「……ケツ毛だ。」
「……え?」
「去年、捕まって吊るし刑を受けた時に『こうなるならケツ毛を手入れしておけば良かった』と相当落ち込んでな。」
「ええ!?」
そっち!?
「あの人には『魅せケツ毛』と『おさぼりケツ毛』があるんだってよ。で、去年フェーズ五以降は特に気ィ遣って、来年に向けた手入れだと言って、やれトリートメントだコンディショナーだと隊の経費を1/3使い込みやがった。」
「す、すごい…。」
それも経費で落としちゃうのか…。
「おかげで勘定方がとっつぁんに目ェ付けられる始末だ。今年は絶対に近藤さんを吊るし刑から守れと隊長クラスに散々言い聞かせてたっつーのに…ックソ!」
ギリッと煙草を噛み切りそうな苦い顔をする。
「これでまた一年、経費がケツ毛の手入れに消えちまう!」
……かける言葉が思いつかない。
土方さんは雑に頭を掻き、心底疲れた様子で溜め息を吐いた。
「やめだやめ。もうフェーズ五は終わったんだ。だろ?」
「そ…そうですね。」
「終わったことを今さら考えても仕方がねェ。それより、」
畳の上に置いていたケーキの箱を前に置いた。
「早くコイツを食わねェと。」
余程楽しみにしていたのか、顔がニマニマしている。…でも、
「どうせ食べるなら、他の方がプレゼントしてくれた大きなケーキから食べてみたらどうですか?」
よりどりみどりな状況なのだから、べつにこれから食べなくても…
「いい。」
「?」
「これが食いてェんだ。」
土方さんは死守してきたケーキを見ながら、
「俺、甘ェもんが苦手だからよ。」
とんでもないことを言う。
「どえぇっ!?だ、だったらこのケーキもダメじゃないですか!!」
「こいつは別だ。なにせ特別なケーキだぞ?」
フッと笑う。
『特別』
私がプレゼントしたケーキは、特別。
―――トゥクン…☆
そ、それはつまり…つまりなんじゃないか!?おおおお、落ち着け私の心臓。
「じゃ、じゃあ…土方さん、」
「ん?」
「もう一度、渡し直してもいいですか?ケーキ。」
「んだよ、またかよ。…ったく、」
煙草を消し、開けたばかりのケーキの箱を再び閉じる。私の方へと箱を寄せてくれた。
「これで最後にしろよ。」
「はい。では…、…土方さん、」
「ん。」
さっきと大差ないシチュエーションでも気にしない。
「お誕生日、おめでとうございます。」
スッとケーキの箱を差し出した。
「ありがとな、早雨。」
はうっ!
土方さんはすぐさま自分の方へ引き寄せる。誰にも渡さないと言わんばかりに抱え込んだ。
「もう食っていいか?」
そんなに早く食べたいのか…。
「…どうぞ。」
「いただきます。」
箱を開け、フォークを突き刺した。
「っあ、待ってください土方さん。そう言えばロウソクを…」
「いらねェ。」
会話もそこそこに、土方さんは少し黄身がかったケーキをひときれ切った。パクッと口へ放り込む。
「……、」
「どうですか?」
私が作ったわけじゃないけど。
「やっぱうまい…。」
「食べたことあるんですね、あそこのケーキ。」
「ああ。」
何を買うか指定するくらいだもんな。…甘いのが苦手なわりに。
「早雨がこれを買った時、最後の一つだって言ってただろ?」
「あー…」
『…おっと、これは最後のホールケーキでしたね。よろしいですか?』
「そう言ってましたね。」
「あそこのケーキ屋、五月五日だけラストワン賞を作ってあるんだ。」
「ら、ラストワン賞?」
何のための賞なんだ…。
「最後の一つだけ特別なケーキを出す。五月五日限定でな。」
『特別』
……あ、そっち!?そっちの『特別』なケーキ!?私関係なし!?
「このケーキ、マヨネーズケーキなんだよ。」
「マヨネーズ!?」
だから執着してたのか!
ということは何か。土方さんはマヨネーズケーキだからウキウキしていたのか。私が買ったケーキだからとかではなく、ただマヨネーズだから……っ、くそぅ!
「見ろよ、このクリーム。全然マヨネーズに見えねェだろ?通常のマヨネーズを二時間かけてホイップ状に軽く泡立てるらしいが――」
「どうでもいいわ!」
「!」
し、しまった。ついテンションそのままで本音が…。
「すみません、なんかちょっと…驚いちゃって。」「だよな、分かる。」
土方さんは幸せそうに目を細め、ケーキを見つめた。
…うん、たぶん…いや全く分かってない。まぁ…喜んでもらえてるからいいか。そう思って自分を慰めておこう。
「…紅涙、」
「えっ…」
名前……
「は…い、」
初めて、名前で呼ばれた。
「今日はありがとな。このケーキと、あと色々世話かけて。」
「あっいえ、私は何も……」
「お前のおかげで去年より良い誕生日になった。マシなフェーズ五だったよ。」
「そう…なんですか?」
「ああ。早く切り上げられたし、何よりお前と逃げるのは楽しかった。」
「土方さん…。」
土方さんは小さく笑い、再びフォークでひと口分のケーキを切った。そしてそれを私に差し出す。
「お前にもやる。」
「えっ、」
「食えよ。」
「やっ…、うーん…」
「今回だけの特別だ。誰にもやりたくねェくらいの好物だが、お前には食わせてやる。」
「うっ…」
そこまで言われたら……食べるしかない。
「ありがとう…ございます。」
差し出されたフォークに手を伸ばした。すると、サッとかわされる。
「俺が食わせてやるよ。」
ええっっ!?
「でっ、ででででもっ」
「食え。」
「やっ、でもっですね、」
「遠慮すんな。」
「っそ、そんなこと言われてもっ」
「とっとと食え。じゃねーと口に突っ込むぞ。」
「ッ…、……い、いただきます。」
差し出されたフォークに顔を近付ける。急激に頬が熱くなった。あーんってするの、結構無防備で恥ずかしいんだよね…。
「……、」
口を開き、ケーキを食べた。味は……想像を超えない味だった。
「どうだ、うまいだろ?」
「…マヨネーズの味がします。」
「マヨネーズケーキだからな。」
土方さんが満足げに頷いた。
「紅涙、口の端にクリーム付いてるぞ。」
「えっどこ…」
「待て。」
拭おうとした手を止められる。首を傾げる前に、土方さんの顔が近付いてきた。
「っな、」
「動くなよ。」
―――チュルッ
「ッッ!?」
い、ま……っ、
「うまい。」
「っな、なななっ」
今私の唇の端を…っ、土方さんの唇が吸い上げた!
「なななななっ」
一体何事!?
「このケーキは誰にもやりたくねェくらい好物だって言ったろ。」
「だっ、だからってなっ、ななななななっ」
「『なななな』うるせェよ。」
なんてことを!!
興奮で舌が回らない私を、土方さんが鼻先で笑う。
「拭くなんて勿体ねェことさせるか。」
そういう問題だけでこんなことする!?
「っ……っ、」
口を開いては閉じる。
土方さんはおそらくもう綺麗になっているであろう私の口の端を、親指でグイッと拭いた。
「じゃあ残りは全部俺が食うから。」
あ然とする私を横目に、マヨネーズケーキを食べ進める。
これは…普通のことなのか?土方さんにとって、口の端に付いたものを舐めとることは日常生活の一部なのか!?
「……、」
わ、私は…どうリアクションすればいいの?意識しない方がいい…のかな。
「ご馳走さま。」
土方さんが手を合わせる。見れば、ケーキがなくなっていた。
「っはや!」
「これでも普段より味わった方だ。」
普段の食べ方が異常すぎでしょ!
「ふぁ、」
土方さんはあくびをすると、
「ちょっと寝るわ。」
「え!?」
唐突にゴロンと横になった。
「だっ大丈夫なんですか!?寝ちゃっても。」
「お前がいるだろ。」
目を閉じながら話す。
そりゃまぁ…念のために見張っておくつもりではいますけど、いくらルール上で終わったことになっているとしても寝るなんて恐ろしすぎる。
「なんだかいつもに増してマイペースですね…土方さん。」
「俺の誕生日だからな。毎年今日だけは少し…ワガママに生きる…ことにしてん…だ……よ。」
途切れ途切れに話した後、寝息が聞こえてきた。早くも眠ったらしい。
「寝つきのいいこと…。」
相当疲れていたんだろう。私は寝息を立てる土方さんを小さく笑い、向かい合うように寝転んだ。
もちろん見張りはするつもりだ。けれど座ってする気はない。寝転んでても、見張りは見張り。…なんて言うと『怠けたことを言ってんじゃねェェ!』と怒られそうだけど。
「あいにく、今は寝てるし。」
腕を伸ばして土方さんの前髪に触れた。
「ん…、」
小さくうめく。なんだか愛おしい。
「…土方さん、」
小さく呼びかけてみた。反応はない。それでいい。
「お誕生日、おめでとうございます。」
何度だって口にしたかった。
私、今日ここにいられて良かった。土方さんの誕生日を祝えて良かった。
「来年も祝わせてくださいね。」
部屋の番人なんて、いくらでもしてあげます。だからどうか来年も、土方さんの些細なワガママを叶えられる、たった一人に任命してください。
「…好きですよ、土方さん。」
なのに私は一人恥ずかしくなって、畳に額を擦り付けた。
2020.12.25加筆修正 にいどめせつな
~山蔭の行方~
紅涙が一人悶絶してから、僅か五分後。
すぅすぅと二人分の寝息が響く副長室の襖をそっと開く者がいた。
「…仲良く、眠っていらっしゃる。」
山蔭だ。今の今まで、副長室の押入れに身を潜めていた。
「早雨さんは強いな…、…僕と違って。」
土方の影武者に起用された山蔭は、計画通り副長室で待機していた。しかし屯所へ突入してきた土方ファンに見つかり、吊るし刑に……となるかと思いきや、山蔭のあまりのビビリ様を見た女性達から『可哀想だ』と同情され、見逃される結果に。以降は、ずっと副長室の押入れで隠れていたのだ。
「隊士の僕が一般市民に…それも敵対する人達から情けを掛けられるなんて…。」
山蔭は、皆のように吊るされることもなければ、拘束されることもなかった自分を惨めに思う。
「早雨さんは副長と戦って、もうあんなことまでしたのに…。」
二人の一部始終を見ていた山蔭は、静かに溜め息を吐く。だが見られていた事実を当事者二人が知る日は来ない。なぜなら山蔭は、
『辞表願い』
その日を最後に、真選組を辞めるつもりでいたから。
「僕には向いてなかったな…。…あ、副長の隊服は後ほど送りますってメモしておかないと。今脱いじゃったら着て帰る服、ないし…。」
ボソボソ独り言を話し、山蔭はメモを残す。そうして二人仲良く眠る姿に背を向けると、
「お幸せに…。」
後に、きちんとクリーニングされた土方の隊服が送られてきたことは言うまでもない。
2009.05.07
2020.12.25加筆修正 にいどめせつな
 |
 |
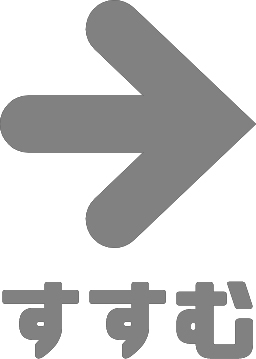 |
