俺の話を聞いてくれ
神様はどうして俺ばかりをこんな目に遭わせるのでしょう!
「ええ、…ふふ。そうなんですよ?」
そりゃあ『彼女ほしいなー』とか思ったりしましたさ!
監察って単独行動が多いし、俺ってどっちかというと真選組では陰キャラ扱いだし!やっぱ日頃の疲れを癒されたいじゃん!?
でもだからって…っ!
「退さんったら、すっかり朝はあんぱん生活で。」
だからってこんな…っ!
「放っておけば、夜ご飯でも無意識にあんぱん食べちゃってるんですよ?」
「…へえ~、そりゃあ身体壊し兼ねねェ話だ。なァ?山崎…。」
「はっはひ!すびばせんっ副長!!」
こんな鬼を背負った彼女なんて求めてないんですけどォォー!
「あら?どうしたんです、退さん。汗が滝のように…」
「アイツなら心配ないですよ、紅涙さん。さっき水かぶってたの見ましたから。だろ?山崎…。」
「まぁ…水を?」
「あ、あーうん!いやっ、暑いなァと思ってさ!アハ、アハハハハ!」
「そうだったの?言ってくれれば良かったのに…。ちょっと待ってて。」
紅涙さんはすぐにタオルを持ってきて、俺の髪を優しく拭いてくれる。
ああ…こういうのいいなぁ……。
心地良さに目を閉じかけた時、タオルの隙間からロンギヌスの槍の如き視線を感じた。
「!?」
「……。」
こっ殺されるー!!いやむしろ、もう俺の身体を突き抜けた気がするー!!
「あっあの紅涙さんっ、大丈夫!自分で拭くから!」
俺は慌てて彼女の手からタオルを奪い取る。紅涙さんは少しだけ寂しそうに「そう?」と笑った。
なんか……申し訳なかったな。
「ご…ごめんね、紅涙さん。ありがとう。」
「ううん、私の方こそ…気付かなくて。」
「いやっ俺の方こそ……」
「私の方こそっ…、」
「……、」
「…ふふっ。」
「ははっ、」
二人で笑う。その和やかな空気を、副長の声が見事に割いた。
「紅涙さん。灰皿、いいですか?」
「あっごめんなさい!今日洗ったんです、持って来ますね。」
「すみません。」
「ふふ、遠慮なさらないで。うちの灰皿は土方さん専用ですもの。」
「なおさら申し訳ないですよ。」
立ち上がる紅涙さんに、副長が苦笑する。
…だが俺は知っていた。
この人は全くもって申し訳ないと思っていない!なぜなら申し訳ないと思っている人は、喫煙者のいない他人の家で煙草なんて吸わないからだ!
この人はただ単に、紅涙さんに自分の匂いを付けたいがために吸っている!
「…やり方がズルイんだよな。」
「何か言ったか?山崎。」
「ヒッ!!」
しまった…!紅涙さんがいないから鬼に戻っているっ!
「ったく…、面倒くせェな。」
「…それなら本当のことを言えばいいじゃないですか。」
「んなことしてみろ、紅涙が困惑するだけだろうが。」
副長はライターで机をコツコツと叩きながら、「なんで山崎が」とか「胸クソ悪ィ」とかを俺に聞こえるぐらいの小声で呟いてきた。
かと思うと急に顔を上げ、眉間に皺を寄せまくった鋭い視線で俺を睨む。
「お前…、紅涙に何もしてねェだろうな?」
「ももももちろんですよ!」
「万が一…いや京(けい)が一にでも嘘吐いててみろ…。」
「いやっほんと!本当に何もないですからっ!1ミリもありません!」
「ほう…なら1ミリ未満はあるのか。」
「へ!?そっそんなまさか!1マイクロ…っいや1ヨクトだってありませんよ!」
「…なんだよ、『ヨクト』って。」
「あ、メートル法の最小単位です。」
「あっそ。」
「……。」
疲れる…。だが俺は、
『どうして副長に、俺の彼女である紅涙さんとのことを口挟まれなきゃいけないんですか!』
などとは一片たりとも思わない。
その理由は一つ。副長と紅涙さんが兄妹でシスコンだから、というわけではなく、はたまた権力的にあがなえないからというわけでもなくて。
「…いいか山崎、忘れんなよ。」
副長にとって、紅涙さんが特別な存在だからだ。それは真選組に関わる者なら誰もが知っている事。
「紅涙はお前の彼女じゃねェ。」
そう、俺の彼女である紅涙さんは……
「俺の女だ。」
そういうことだからだ。
この悪夢のような日々が始まるきっかけは、忘れもしない三月も末の、よく晴れた日のことだった。
あの日の俺は屯所の屋根修理なんて専門外のことまで請け負っていて、猫の手を借りたいほど忙しかった。ようやく修理を半分終えて地上に下りてきた時、
「今日は一段と忙しそうですね~、山崎さん。」
呑気な顔で桜餅を片手に、局長室から紅涙さん…いや、早雨さんが出てきた。今思えば、そこで出会ってしまったのが運の尽きだ…。
「早雨さんはユルいね…、顔に『春』って書いてるよ。」
「実際、春ですからね~。近藤さんに桜餅もらっちゃったし。」
ウヒヒと嬉しそうに笑い、早雨さんは手のひらに乗せた一つの桜餅を見た。
…って、せめて皿とかに乗せようよ!
「だけど一つしか貰えなかったんですよねー…、桜餅。」
お?珍しく俺の分も気遣ってくれて……
「土方さんに見つからないようにしなきゃ!」
ですよねー!俺のためになんて考え、皆無でしたよねー!
「あ、あのさ、早雨さん。」
「はい?」
「桜餅自慢なら、向こうでやってもらえる?俺、忙しいんだ。」
「もうっ、わかりましたよ。手伝います!一瞬だけね。」
そんなつもりで言ったんじゃないんだけどな…。
いつもなら、こんな助けは断っていた。だがその時の俺は忙しかった。とにかく、忙しかったのだ。
「じゃあ、あの屋根の上にある箱を取ってきてくれる?」
俺は先程まで登っていた屋根の上を指さす。まだハシゴも掛けたままだ。
「えー?なんであんなところにあるんですか~?」
「今修理中なんだけど、下で使いたい道具を持って下りるの忘れちゃって。」
「もー。抜けてるなぁ、山崎さん。」
「…う、うん…そうだね。ごめんね。」
俺は頬を引きつらせて頷く。そんな俺を気に留めることなく、早雨さんは気怠そうに溜め息を吐きながらハシゴに足を掛けた。
……え、
「ちょっ、早雨さん!?」
「何ですかー?」
「桜餅持ったままなんて危ないよ!」
片手に一つの桜餅を乗せたままなんて危険すぎる!
「平気ですよー。置いておくと言っても、そんな場所ありませんし。」
「なら今食べちゃうとかさぁ!」
「お茶を飲みながら食べるって決めてるんでー。」
知らねェよ!それくらい我慢しろよ!
片手で登ろうとするなんて無謀すぎ―――
「おっと…」
「!?」
二段目から三段目に足を掛けた時、早雨さんがバランスを崩した。けれどすぐに体勢を立て直す。
「ふ~、危ない危ない。」
しっ心臓に悪い!もし早雨さんに何かあったら、俺は副長に殺される!
「じゃっじゃあ桜餅は俺が持っておいてあげるから!」
「お断りします!そんな何触ったか分からないような手に預けられません!」
「そ…そりゃそうだけど…、…なんか傷つく。」
ついさっきまで屋根の修理してたし、綺麗とは言えないけどさ……。
…と、俺がへこまされてる間に早雨さんは屋根の上へ登りきっていた。
「これですかー?」
「あ、それじゃなくて、もう少し下がった所にある道具箱の方で。」
「はーい。…あ、そういえば山崎さんって『退』と書いて『さがる』なんですよね~?」
「え?ああ…まあ…そうだけど。」
「珍しい読み方じゃないですかー?学校で先生が悩みそう。」
その通りだ。
毎度、一発で名前を読めた人はいない。だが見方を変えれば印象に残りやすい名前ということ。いい名前じゃないか。ありがとうお母さん!
…でもこんなに存在感ある名前があっても、俺はどうしてか真選組で存在感に欠ける。……あ、これが世にいう名前負けか。
「もしもーし?聞いてますか、退さん。なんつって。」
早雨さんが屋根の上から顔を出した。イタズラにニヒッと笑った彼女だったが、
「あっ…!?」
屋根の端で手を滑らせ、
「っわ!」
「えっ!?ちょっ…早雨さん!?」
「わああああっ!!」
―――ガシャンッ!!
道具箱と一緒に、早雨さんは屋根の上から落ちた。慌てて助けに入ったが支えきれず、俺も早雨さんも地面に打ち付けられた。
「い、たたた…。大丈夫?早雨さん。」
派手な音に驚いた隊士達が部屋から飛び出してくる。縁側には局長や副長も立っていた。
「なんだなんだ、何事だ?」
「あァ?山崎、何して…って、紅涙!?」
副長が靴も履かずに駆け寄ってきた。俺の上でぐったりしている早雨さんの身体を起こす。
「おい紅涙!しっかりしろ!」
「あっ副長、あまり動かさない方が…!」
「あァ!?」
「ヒィっ…!いや、あああのっ屋根から落ちたんで頭とか打ってたら大変なことに……」
「屋根から落ちただと!?テメェ何させてたんだ山崎!」
「ヒーッ!!すみませんっ!!」
「謝って済む問題じゃねェ!もし紅涙に何かあったらお前は――」
「ん……、」
「!…紅涙!」
「早雨さん!」
早雨が目を開いた。覗き込む副長と俺の顔を交互に見て、にっこりと微笑む。
よかった、大したことなさそう……
「あれ?…どうしたの?退さん。」
こうして、俺の悪夢は幕を開けたのだった…。
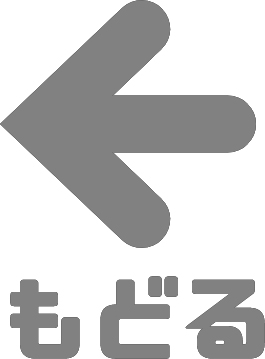 |
 |
 |
